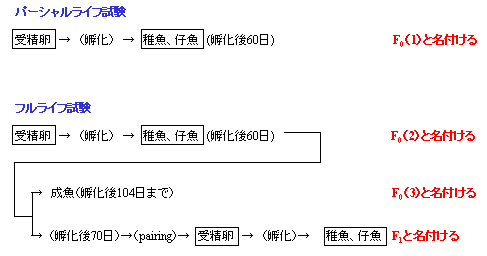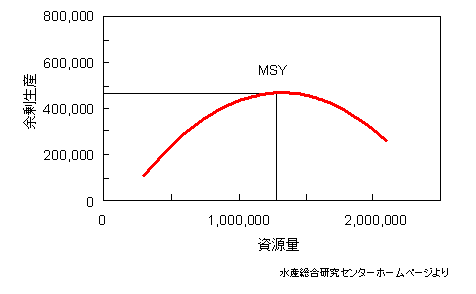3-155.雑感(その155 -2001.12.4)「奇妙な環境省のパブリックコメント」
OECDでのパブリックコメント
人から教えて貰って知ったのだが、環境省がノニルフェール(NP)のメダカへの影響、及び河川水中NPの濃度、および環境管理の目標にすべき濃度(この言葉正確ではありません。今、米国におり、手元にレポートがないのでお許しください)についての報告を、OECDの機関を通じてパブリックコメントにかけていた。その締め切りが11月30日。公示開始が10月15日となっている。
中味は、私が、このホームページで、数回に亘って生態リスクとはどう評価すべきかについて論じることになったきっかけの環境省の報告と全く同じで、英語に翻訳されただけのものである。
(環境省の報告は2001年8月、環境省のホームページで、平成13年度第1回内分泌攪乱化学物質検討会資料でみることができる。http://www.env.go.jp/chemi/end/index.html)
そのOECDのサイトがとても分かりにくく、私などは、アドレスを教えてもらっても、一回ではアクセスできなかった。奧の奧にある。因みに書くと、以下のようになる。
http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-document-524-14-no-24-19636-524,FF.html
期間も短いし、こういう奧の奧では、よほどのマニアでなければ気づかない。これを知って、私は日本国内でもパブリックコメントが求められていると思い、環境省のホームページを見たが、現在もそのような告知はないし、過去に行われたパブコメのリストの中にもない。一体これは、どういうことだろう?
外国の評価が重要と思っているとすれば、ひどい。日本国内には異論がないと思っているとすれば、大きな勘違いだが、そうではない。すでに、私などがホームページで意見を出しているのを、環境省の人は知っているからである。外国と言っても、このアドレスにアクセスするのは、政府関係者だけだろう。通常の学者が見る機会があるとは思えない。
慣習なのか否かは知らないが
今まで、OECDのパブコメというものに関心がなかったので、或いは、こういうことが度々あったのかもしれない。それも調べてみようと思ったが、ホテルの内線電話からの接続なので、しばしば切れて、うまく過去のリストに出会えなかった。
したがって、これが慣習的なものか、今回はじめてのケースかがはっきりしない。今回、NPについての報告書と一緒に、環境省は、トリブチルスズについての報告書も一緒にOECDのパブコメに出している。
例え、国内でパブコメを求めずに、OECDのパブコメを先に求めるのが環境省の通常の方法であるとしても、それは随分おかしなことだ。
特に、今回は、国中がここ数年パニックに陥ったほど重大な社会問題であったことで、関心も強い。しかも、学問的にもいろいろ議論のあることだ。また、OECDに出された環境省の報告書には、日本の委員会に出されたものだから、日本の環境濃度にも触れており、そこでは環境対策が必要とまで述べている。
毒性影響の問題と、その評価は外国での評価の方が信頼がおけると考えているのだろうか?
しかし、国内の事情が分からない人だけで論じても無理なことが余りにも多い。
例えば、環境濃度が測定されている地点の特性や方法。
指標に使われているメダカの意味。
何よりも、ここで得られた値を環境管理目標にするという、国内に大きな影響を与える政策判断が含まれていること。
他の生態リスクとの関係など。
一度も議論されていない
毒性評価のことについても、私がホームページで何回か述べた、エンドポイントを何にするかという問題の他に、実験室の実験結果の解釈、実験方法がいいのかという点にも議論がある。
一部の実験結果が、学術誌に報告されているが、環境省が基準値に採用した値が出された実験報告は、環境省報告書以外には掲載されていない。また、それらが学会で議論されたこともない。再三言うが、日本ではパブリックコメントにはかけられていない。
環境省の委員会で議論されただけである。
不信感
このOECDでのパブコメの話を聞いてから、ひどく環境省の態度に不信感をもってしまった。
これまでは、生態リスクはどうあるべきかについて、余り考えていないという意味の不信感だったが、今の不信感は違う。何か、誤魔化そうとしているという不信感である。しかも、広く意見を求めるというパブコメという手段を用いてである。
OECDでパブコメを求め、特段の反対もありませんでした。だから、日本で、NPをこの報告書で規制しましょうという態度だ。
そして、マスコミなどを使って世論ができあがったところで、何か、形式だけの国内向きパブコメを出すのではなかろうか。あまりにもひどいと思うのだが。
中西のホームページ内で、NPの「生態リスク」に関する記事へのリンク
雑感150「生態リスク(1)」、 雑感151「生態リスク(2)」、 雑感153「生態リスク(3)」、
雑感141「ベンゼン濃度の低減効果評価(梶原さんの研究)」
日経夕刊「あすへの話題」11月27日は「うれしい感想」でした。
3-154.雑感(その154 -2001.11.27)「立花隆先生、かなりヘンですよ」
"「教養のない東大生」からの挑戦状"という副題がついて、洋泉社から出版された。著者は谷田和一郎さん。東大在学中に出版する予定が遅れ、出版は卒業後になってしまい、正確には元東大生による本だという説明がついている。
この本が面白い。立花隆さんの論理、癖を徹底的に批判しているのだが、嫌みがない。揚げ足とりではない。それに、すごい解析力である。やはり東大生はすごいな(?!)という感じの本である。
環境ホルモンと組み換え遺伝子導入食品
立花さんは、凶悪少年犯罪も鬱病も環境ホルモンのせいだ、環境ホルモンは「人類の存続に関わる唯一最大の環境問題」といい、
一方で「農薬のような化学物質には、大なり小なり、発ガン性、催奇形性、環境ホルモン効果などの毒性があるが、遺伝子組み換え食品にはそのような危険性はない」という。
そして、遺伝子組み換え食品の安全性に疑問を投げかける人に対しては、無知だ、知識がないと非難する。
立花さんの、環境ホルモンの危険性に対する警告と、組み換え遺伝子導入食品の安全性に関する楽観論という、正反対の態度に、多くの人が驚いたと言っていた。それが、なぜかということを、谷田さんは以下のように解析している。
谷田さんの立花論
(谷田さんの書いていることを、中西流にまとめてみる)
立花さんが、環境ホルモンに対して警告を発するのは理解できる(と谷田さんは言う)。
彼は本来アラーミスト(警告者)だ。ではなぜ、遺伝子組み換え食品は擁護するか?それは、遺伝子組み換え技術が必要だと考えているからだ。漠然と、必要と考えているというのではない。それは、彼のこれまでの論理構成のなかで必須のものだ。
彼の論理の骨格は、三つから成る。①進化、②パラダイムシフト、③二極分化。
この最初の二つは強く結びついていて、進化によりパラダイムシフトも起きると考えられている。彼の言う進化とは、ただ単に進歩するとか、変化するというような生易しい概念ではなく、人間自身が新しい人類に進化するという内容を含む。
コンピュータも今の人類がもつ脳以上の機能をもつ人工頭脳の可能性として位置づけられているし、遺伝子組み換えも、人間を変える手段として位置づけられている。
3番目は、この進化に遅れる人間は、もう新しい人類ではないので、二極分化が起きるとなる。
こういう論理の中で、遺伝子組み換え技術の進歩が遅れたら人類は進化できないので、遺伝子組み換え食品の安全性を問題にする奴は、とんでもないということになる。
人間はケミカルな存在という認識
環境ホルモンが彼の興味を引くのは、(と谷田さんは言う)、「恐らく"人間はケミカルな存在である"という事実だろう。すなわち、人間の"精神"を科学で分析しうるのではないかというテーマである。
それは、これまで哲学のフィールドとされてきた人間の"精神"に、科学がメスを入れることが可能ではないかという期待なのである。
ここが立花氏の思想の琴線に触れるのだ」。
面白い
この解析、面白いですよね。私にとっては、環境ホルモンへの立花さんの攻撃は理解できないものだったが、逆に遺伝子組み換え食品についての立花さんの楽観は、予想どおりだった。
それは、一連の科学雑誌で繰り広げられていた、新しい科学に対する軽率とも思える楽観的な評価を読んでいたからである。
その、延長上で、環境ホルモンも、技術の副産物として受け入れると思っていた。でも違った。その理由として、谷田さんのような深い洞察には至らなかったが、私はこんなふうに受け止めていた。
現状と過去は、彼にとってすべて非難と攻撃の対象になる。そして、それが酷ければ酷いほど、未来に対する期待が大きくなる。
彼の仕事は、未来を描いて見せることだから。もし、彼が20年前に生まれていたら、化学産業を夢の産業と評価したかもしれない。
未来を描くためには、技術の可能性を語るしかない。自然科学者は、自分で技術を生み出さねばならないから、そんなに技術がすばらしいものではないことを知っている。
技術を生み出すのが、一歩一歩、いきつもどりつのプロセスであることを知っている。そして、どんなに努力しても止まってしまう技術があることも知っている。
しかし、技術を自分で生み出したことのない立花さんには、それが分からない。人の苦労が生み出した技術の、いいとこだけ取っていくことをやっている人には、それが分からない。私が考えたことはここまで。
この指摘は納得できる
人工知能が可能、人間の進化が可能だと考える立花さんにとって、微量の環境ホルモンで人間がいとも簡単にだめになるというのは、実に分かりやすい話であり、自説を補強する恰好の事例だったというのは、谷田さんの本ではじめて教えられた。そこまでは気がつかなかった。なるほどと思う。
立花さんの本は好きだった
立花さんの初期の仕事は好きだった。特に好きだったのは、「宇宙からの帰還」である。「脳死」も最初の一冊はいいと思った。が、その後、どうかなと思う仕事が増えてきた。
所謂、先端科学もの、つまり「科学朝日」とか、サイアスに掲載された、先端の科学技術者のインタビュー記事も、本当に研究者が言いたいことを、立花さんは理解していないという印象が強くなり、興味が薄らいでしまった。
「知の巨人」と言われるようになってからの仕事は、もう目を覆いたくなるほどの粗さで、とてもついていけなかった。さらに、環境ホルモンについての論調は、まじめに考える気もしなかった。
こういう議論を信用する人がいるとは思わなかったのだが、そのうち、東大立花ゼミで本が出て、学生が信じている様子で、実はひどく驚いた。
東大のある教授に聞いたことがある。「本当に東大生は、立花さんの環境ホルモンについての意見を信じているのか?」と。その先生は、「立花ゼミには東大生はあんまりいないんですよ。主力は他大学生です」と。
本当かどうか知らないが、ともかくこういう答えだった(東大は不滅です、東大生は神聖です、か。)。
谷田さんの本を読むと、立花さんの原点は、「宇宙からの帰還」にあるということで、そうだとすれば、私がこの本を読んで感動したというのも、浅慮ということになるのかもしれない。
脳死の一冊目も臨死体験から始まる。これも、私は面白いなと思った。それが、立花さんのオカルト思想の原点だとすれば、尚更浅慮ということになる。
原点はそこにあるとしても、彼がこのように進んでしまったのには、日本での評論家という仕事の特殊性があるように思えてならない。立花さんは評論家としての名声を維持するために、ある種「進化」せざるを得なくなり、今のようになったとも思うのだが。
日経「あすへの話題」11月20日は「イカ釣り」でした。
狂牛病2頭目。当然起きることで、特に問題とは思わないが、相変わらずマスコミは「安全性に疑問」などと騒いでいる。何かおかしい。すでに、私がHPで書いた如く、やはり北海道だった。「ホクレン」の餌を追跡すべきと書いた筈だが。
中西のホームページ内で、「狂牛病」に関する記事へのリンク
雑感149「狂牛病試験」、 雑感148「野生動物と狂牛病」、 雑感146「狂牛病(風評被害を食い止めるために)」、
雑感145「狂牛病続報(ああ、農水省、またか!)」、 緊急追加!!「狂牛病の日本での発生について」、
雑感137「狂牛病から人間への感染リスク(英国)」、雑感120「狂牛病とジクロロメタン」、
雑感69「もう一つの英仏牛肉戦争」
日経「あすへの話題」で狂牛病について取り上げたのは、7月3日(火)夕刊「狂牛病と野生生物」
講演会で狂牛病についての講演は、CRM(産総研化学物質リスク管理研究センター)第一回講演会
3-153.雑感(その153 -2001.11.19)「生態リスク(3)」
ノニルフェノールの生態影響についての環境省方針についての根本的疑問
―生態系保護はどうあるべきか(第3回目)-
●無事、米国から帰国しました。ワシントンDCに着いた翌日にNYCでAAが墜落したのには驚きましたが。
環境省の実験
環境省は、メダカを対象にして、NP(ノニルフェノール)の影響を調べるために以下のような二つの実験をしている。(環境省総合環境政策局環境保健部、ノニルフェノールが魚類に与える内分泌攪乱作用の試験結果に関する報告、平成13年8月による)
1) パーシャルライフ試験
2) フルライフサイクル試験(確定試験)
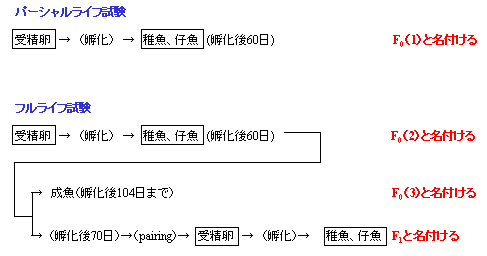
そして、得られた結果は表の通りである。(F0(1)とF0(2)は本来同じ試験。)
表 二つの実験のまとめ(数字はNPの濃度で、単位はμg/L)
パーシャルライフ
| |
F0(1)孵化後60日まで |
|
| 死亡率 |
44.7まで影響なし。 |
|
| 成長 |
23.5以上で体重減少 |
|
| 性比 |
23.5以上でメスに偏り |
|
| 精巣卵産生 |
11.6以上あり |
|
| ビデロジェニン生成 |
11.6以上あり |
|
フルライフ(1世代)
| |
F0(2)孵化後60日まで |
F0(3)104日まで |
| 死亡率 |
17.7以上で増大 |
総産卵数 影響なし。受精率17.7で影響あるかもしれぬ(当面、統計的に有意さなし)。 |
| 成長 |
183まで影響なし |
| 性比 |
51.5で偏りあり |
| 精巣卵産生 |
17.7以上であり |
| ビデロジェニン生成 |
記述なし |
フルライフ(2世代)
| |
F1 孵化後60日まで |
|
| 死亡率 |
17.7まで影響なし(高濃度実験なし) |
|
| 成長 |
17.7まで影響なし(高濃度実験なし) |
|
| 性比 |
記述なし |
|
| 精巣卵産生 |
8.2であり |
|
| ビデロジェニン生成 |
記述なし |
|
そして、結論は
そして、以下の結論が導かれる。
(ノニルフェノールが魚類に与える内分泌攪乱作用の試験結果に関する報告(概要))
「メダカのパーシャルライフサイクル試験で精巣卵、ビデロジェニン産生が有意に認められた水中濃度11.6μg/Lを性分化に関する影響の最小作用濃度とする。
この場合の最大無作用濃度は6.08μg/Lとなり、また、予測無影響濃度(PNEC)については、安全係数1/10を乗じた0.608μg/Lとする」
まず、驚くのは、パーシャルライフの試験結果とフルライフサイクルの実験結果がかなり違うことである(同じ一世代で)。
私は、メダカの実験をしたことがないので、よく分からないが、これでいいのだろうか?それであれば、これで基準値を決められたらたまらないなとも思う。
それは、専門家の判断を仰ぐとしよう。
大事なのは死亡率または、受精率
前回まで述べてきたように、個体群レベルの管理をすることが目標になれば、精巣卵ができることが問題ではなく、個体数が減少に向かうか否かである。
このような、影響がはっきりしないendpointをもってきて、環境基準や排出基準を決めるのは、あまり聞いたことがない。
生態系について、個々の生物を全部生かす、全部健康にするということを目標にするのではなく、それぞれの生物の全体数が減少し続けることがないようにすることを目標に管理すべきだということを述べてきた(個体管理ではなく、個体群管理をする)。では、どういう状況なら個体群(種)を維持できるか?
それは、計算できないわけではないが、この計算について、多くの国や機関が納得した、一定の計算方法があるわけではない。
そこで、現状では、やはり個々の個体(生物)に関する毒性試験結果ではあるが、個体群の数に影響が大きいと思われる死亡率、産卵数、受精率、生長率などが、身代わりとして環境基準設定に使われてきた。
これも、個体の毒性試験の結果だから、私は満足していない。しかし、次善の策として、これを一定期間用いることは、ある程度やむをえないと思っている。
どこの国の規制担当部局も、このことを考えていると思う。つまり、個々の毒性試験ではあっても、個体群の数に関係するような指標を用いている。
ところが、今回の環境省の報告には、こういうことに関する配慮が全くない。いや、そもそも知らないのではないかと思われるほど無神経に、精巣卵の産生をendpointにして、環境基準らしきものを論じている。
精巣卵が、死亡率に影響しているとか、産卵数に影響しているとか、或いは、(予想されることだが)受精率に影響があることを証明して、だから精巣卵産生をendpointにするというのなら、まだ分かる。
死亡率との関係は実験によって全く違っている。受精率の影響を見ようには、そもそもの実験のdesignができてない。この実験とその後の推論をみると、何のために、生態系を保存するのかという考えが全くないように見える。
気になることのいくつか
やや疲れていて、長く書くことができないが、さらに気になるいくつかについて箇条書きしておく。
1)内分泌攪乱物質の影響を調べるために、無影響濃度を調べる時の餌の問題である。
餌にある程度エストロゲン活性のある物質が含まれているとき、もし実験で10μg/Lで影響有りとすれば、餌に含まれる分が50μg/Lに相当すると、実は無影響濃度は60と言えないこともない(完全な和ではないかもしれないが)。
自然の餌にも内分泌攪乱物質はあるので、それも考慮しなければならないが、無影響濃度を調べるとき、餌を代えて実験をやるということを義務づけなくてもいいか。
2)NOEC(無作用濃度)が実験的に出たとして、こういう値を一律の基準値として、日本全国の川に適用することは、コストがかかるだけで、無意味だと思うが、どうも、そのように環境省は考えているようである。これは、おかしい。
3)メダカが特にエストロゲン活性物質に反応するという。とすれば、メダカで試験し、その結果をつかうことの意味が却って問われることになると思う。その場合の安全係数10の意味は何だろう?
11月13日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は、「次善の策」でした。
環境gooにインタビューが掲載されています。(http://eco.goo.ne.jp/navi/index.html)
番外(2001.11.12)「すみません」
忘れ物
今、米国のBaltimoreに来ています。今日、ここで生態リスク(3)を書くつもりで、今コンピュータに向かったのですが、そのための資料を忘れてきているのに気づいた。
日本を出発する直前まで読んでいて、尚かつまとめておいたものを忘れるとは何事だ!と自己嫌悪。大変、申し訳ないが、生態リスク(3)は次週とする。もの忘れは少ない性質と思っていたのだが。
尤も、成田まできてパスポートを忘れたことに気づき、1日遅れでヨーロッパに行ったことがある。JTBの人に、正規料金でチケットを買っておいてよかったと言われた。
Baltimoreの話を書けばいいのだが、なにしろ昨日午後着き、それから後コンピュータの接続を確認しただけで寝てしまい、今に至っているので、外も歩いていない。書きようがない。Baltimoreは二度目なので、大体の町の様子は分かっているが。
空港のcheck
化粧用のかみそり、つめきりなどを手荷物にもっていても駄目という話を聞いていたので、それはすべてトランクの方に入れたので、私の場合はcheckがかからなかった。
電子製品、コンピュータなどについて、かなり厳しい。コンピュータに電源を入れて、何も起きないことを確かめさせることがあると掲示があった。
成田(NH004):ANAのカウンターでのcheck inの手前、トランクのsecurity
checkでは、今回は手荷物も磁気検査機を通す。その上で、トランク、手荷物を開けて調べる。
袋の上からさわって、靴ですね、衣服ですね、と言う。トランクの中のポケットも全部手を入れて調べる。電子製品を一つ一つcheck。終わったあと、私が鍵はどこにいれたか探していると、そちらのバッグに入れましたよときた。プロだな。
入国審査の前の、security checkで手荷物のcheck, body check。
飛行機に乗る時、もう一度手荷物を全部開けて調べ、body check。
Chicago(着):出る時は、特になし。
Chicago(発):シカゴで再び国内線に入る。荷物検査。Computerは荷物から出してほしいとの指示。
Washington DC(ダレス国際空港):町へ。
米国の空港には、むしろ、はりつめた感じはあまりない。通常の感じである。米国から出るときは、ちがうかもしれない。
とりあえず、一日の休みを戴いたということで、ゆっくり眠ることにします。
(11月12日 Baltimore 午前1時半、日本時間12日午後3時半)
11月6日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は、「ついばまれた果実」でした。
3-152.雑感(その152 -2001.11.6)「生物濃縮についての誤解」
「水俣病の科学」
今日は、生態リスク(3)を書くつもりだったが、そのための文献を読み終わらず、次週にさせていただく。少し別のことを書くこととする。
西村肇さんが(岡本達明さんと共著で)「水俣病の科学」(日本評論社)を出版した。周囲の人にはこの本が如何にすばらしい本かを宣伝しており、講義でも使った。このHPでも書こうと思いつつ、他の話題に追われて書きそびれていた。先週の日曜日の毎日新聞によれば、毎日出版文化賞を受けた。嬉しい。
この本には二つの主題があると思う。一つは、反応装置の中を推定し、どのくらいのメチル水銀が生成し、排出したかについての推定したこと。
1940年代からアセトアルデヒド製造工程が動き、水銀が排出されていたにも拘わらず、劇症水俣病や胎児性水俣病が1950年代に集中して発生した理由が分かる。また、同じような製造法の工場が多くあったにも拘わらず、水俣で患者が集中して発生した理由が、今回の本で初めて分かる。
もう一つのポイントは、どのように魚介類にメチル水銀が蓄積・濃縮するかのメカニズムである。その考察の中で、いろんなことが明らかになり、まさに目を見張るような考察なのだが、私がここで強調したいのは、生物濃縮のメカニズムである。前者については、また機会を改めて書く。
食物連鎖一辺倒
環境科学の教科書には、必ずと言っていいほど生物濃縮(重金属やPCBなどが、生物に濃縮する現象)の話が書いてある。
ところが、これがすべて食物連鎖によると書いてある。だから学生たちは、生物濃縮のメカニズムは?と聞くと、100%食物連鎖と答える。しかし、この寄与が大きくないことも多々ある。
それ以外には何か?呼吸である。エラ呼吸と言ってもいいだろう。水中の酸素はエラを介して吸収するが、その時、メチル水銀が溶けていると一緒に吸収されるのである。
実は、このメカニズムが大きく作用していることは、水銀の研究の中で明らかになった。
私も最初は食物連鎖を通じた濃縮の話ばかりを耳にしていた。裁判の過程での議論も、そうだった。ところが、沖合のマグロの水銀値が高いことが分かり、このエラ呼吸が大きな役割をしていることが明らかにされた。
エラ呼吸で酸素とともにメチル水銀などの溶解成分が、血液中に移ることはすでに、大昔から知られていたに違いない。生態学の古い教科書にも書いてある。汚染と絡んで考えられたのが、水銀問題の時だと言っているのである。
そして、生態学の専門家でない私も知るようになった。ところが、どういうわけか、このことが環境科学の本に一切でてこない。どこを見ても、食物連鎖。
なぜだろう?不思議だ。
この本に書いてあること
この本には、食物連鎖にしてもエラ呼吸にしても定量的に扱わなければいけないということが強調されている。ただ、水の中の濃度と魚介類中の濃度の比をとって、食物連鎖とか言ってはいけない。もしそうなら、それだけ餌を食べているかの検証が必要だと。
そしてカタクチイワシの例
カタクチイワシは、口から吸い込む水から、呼吸によって酸素と溶解性のメチル水銀を吸収し(エラ呼吸)、同時に水の中に含まれる動物プランクトンを餌にするとのこと。この動物プランクトンもメチル水銀を含むので、ここからもメチル水銀を摂取する(食物連鎖)。
この量を比較しよう。
<呼吸量>:カタクチイワシの酸素取り込み速度は、1300
[mgO2/kg hr]である。水中の酸素濃度は約10 mg/L、水中の溶解性メチル水銀濃度は10 ng/Lであるとしよう。
とすると、酸素に比べメチル水銀は100万分の1。つまり、毎時間体重1kg当たり1300mg×[100万分の1]=1300ng吸収することになる。
分解がないとすると、1年で1300ng/kg(体重)×24×30×12=11.23×106[ng/kg]=10ppm、メチル水銀値は10ppmにもなる(因みに魚介類中の水銀の許容暫定値0.3ppm)
<一方、動物プランクトンから入る量>:動物プランクトン中のメチル水銀濃度は、水中の濃度の10万倍濃縮している。
しかし、動物プランクトン自体が海水中に0.1ppm程度しかないので、同じ水から餌の動物プランクトンと酸素、溶解性のメチル水銀を吸収する限り、
動物プランクトン中のメチル水銀:水中のメチル水銀=0.1ppm(プランクトンの量)×105:1=100:1となり、動物プランクトンからのメチル水銀吸収は、エラ呼吸からの吸収に比べ無視できるほど小さい。
註1:ここで仮定した水中メチル水銀濃度は、汚染されていた水俣湾の海水中濃度の推定値。
註2:この動物プランクトン量ではカタクチイワシの餌としては不足する。後で調べてみる。わからなければ、西村さんに聞いてみる。(プランクトン量(濃度)がもっと高く、メチル水銀濃縮率がそれに逆比例して小さいのではないかと私は思う。)
まとめの表
| |
濃度や量 |
| 水中メチル水銀濃度 |
M |
| 水中動物プランクトン量 |
1×10-7 |
| 動物プランクトン中メチル水銀濃度 |
M×105 |
| エラ呼吸でのメチル水銀吸収量(1) |
=C×M |
| 動物プランクトンからの吸収量(2) |
=C×1×10-7×M×105
=C×M×10-2 |
(1):(2)=100:1=エラ呼吸による吸収:食物連鎖による吸収
水俣病研究
西村さんの話では、所謂水俣病研究者は、この本についてだんまりを決め込んでいるという。
旧環境庁は、20年か30年、毎年水俣病調査費として予算をとり、水俣病研究者に配布してきたが、水俣病の機構解明の研究はほとんど行われなかったという話だ。
勿論、原田正純さんも、西村さんも、のけ者にされたままである。この研究費は何に使われたのだろうか?
(いろいろ噂は聞くのだが。)
10月30日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は、「はぎ寺」でした。
3-151.雑感(その151 -2001.10.31)「生態リスク(2)」
生態系保護のための化学物質管理は如何にあるべきか
-ノニルフェノールの生態影響についての環境省方針についての根本的疑問―
(第2回目)
個体レベル管理と個体群レベル管理の違い
個体レベルでの保護と個体群レベルでの保護との違いは、何か?漁業を考えると、一番分かりやすい。
我々は自然の生き物である魚を食べて生きている。それらを全く捕獲していけないとなると、日本人は蛋白源がなくなる。蛋白源がなくなるからといって漁獲しすぎれば、種が途絶え、将来の日本人の食料がなくなってしまう。
だから、種が絶滅しないように、また、一定以上の漁獲が続くように漁獲管理をすることが漁業資源をできるだけ永続的に利用するためには望ましい。漁業管理の研究では、以下のことが分かっている。
枯渇しないで獲り続けることができる量があって、それはMSY(最大持続収穫力)と定義されている。資源量と余剰生産力との関係は、図1のようになっていて(厳密に本当かどうかは知らないが)、それぞれの資源量で余剰生産力が決まる。
ここでは、個体群の数を130万程度に維持し、MSYを漁獲することが最も有効な資源の利用法になる。MSY以上に漁獲すると、個体群の数は減少し、やがて、絶滅することになる。
ここで、200万程度の個体数を維持したければ、この曲線上の値、例えば、30万程度を持続的に漁獲できる。
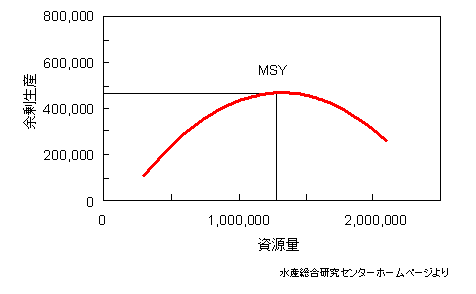
図1 Maximum Sustainable Yield 最大持続生産量
この曲線で示す余剰生産量までの漁獲量なら、あるレベルの個体群の数を長期に維持できる。そして、これで生物の種の多様性も保たれる。
追記:このあたりの説明は、私はあまり正確でないかもしれない。中澤港さんのホームページを見ていたら、とてもいい表現があった。以下引用
例えば、クジラは食べていいか?という問題について、絶滅の危機に瀕しているから食べてはいけないという批判があるが、クジラの種類によっては増えすぎて餓死しているものもいるし、増えすぎたクジラによって魚が減少しているという指摘もあるので、心理的な側面を別にすれば、問題は「どれくらい食べてもいいか」ということなのだとわかる。
マサバなども、乱獲すれば激減してしまうが、適正に獲っている限りでは個体数が維持され、安定した漁業資源となるので、「どれくらい獲るのが適正か」ということは大きな問題である。資源管理とはこの問いに答える考え方である。
ヒトによる捕獲を捕食と考えれば、この問題は、自然の生態系に対して1つの被食捕食関係を追加した場合に、どこまで捕食圧を高めても生態系が安定していられるか、という問いに帰着する。
現実には
このような管理を行っていれば、種の数が減少することも、生物の個体数が減少することもないのだが(自然の減少量を超えての意味)、現実には、その許容量を超えて木を伐採し、魚を獲り、ダムを作って水をとり、毒物を出して、環境を破壊してきたし、今後もそれを完全には止めることができないだろう。
何故、完全に止めることができないかと言えば、自然を壊すことによって得られるメリットを、ゼロにすることが難しいからである。
農業も止められない、漁業も止められない、川から水をひくことも止められない、木を切ることも止められない、人間が生きる以上、殺菌剤はある程度は川に出さなければならないだろう、それに何よりも、人間の廃棄物もまた、他の生物にとって有害である。
しかし、今後はできるだけそれを減らそう。そのために、まず最高の目標として、それぞれの種の個体群数を、例えば、最高値の1割以上は減らさないとおこう。
そうすれば、余剰生産を利用できる。それも駄目だ、2割減というところに目標を置こう。さらに自然を利用できる。3割はどうか?一時はいいが、その後は却って利用量が減少してしまう。4割になると、どんどん減少する。
とすれば、やはり限度がある。ここを管理目標にしよう。私の主張は、厳密にそれを求めようというのではない。原理としてそういうことを考えて、個体群管理という目標をまず、設定しようと言っているに過ぎない。具体的に、どういう目標値になるかについては、ここでは議論しない。
個体レベルの管理なら、一匹でも殺すな、さらには魚をいじめてはいけないというような目標になってしまう。これは、どう考えても無理だ。
Suterの論文
私が、個体群レベルの管理を目標におくべきだという考えを持ちはじめていたとき、具体的にどうすればいいかを知ったのは、Glenn W. Suter Ⅱの論文によってだった。
そこで、私は1995年、彼を訪ねてOakridge National Laboratoryに二ヶ月滞在し、いろいろ勉強させてもらった。
Suterの12年も前の論文だが、その一部を以下に引用する。内容はさらに進化しているが、古い論文の方が、分かりやすい。
論点の1)
評価エンドポイントは、保護すべき価値の表現であり、推定されるべき影響であり、削減すべき影響である。
環境ハザード評価(現在行われている方法。PEC(環境濃度)とPNEC(無影響濃度)との比較)では、評価者が評価の最初の段階で、どういう影響を予測しようとしているのか、とか、結論でどういう影響が起きると予測しているのかを特定することができない。
ハザード評価法では、影響の表現は、生物的な影響を及ぼさない最大のテスト濃度(PNEC)である。または、そのテスト条件下での生存、成長、再生産に重要な悪影響を及ぼさない最高の濃度である。
結果として、保護されるべき種、成長段階、プロセスと保護の程度は、用いられる毒性試験に依存する。
論点2)
リスク評価では、評価者がどういう影響を評価しようとするのかというエンドポイントがはっきりしている。
人の健康と工学のリスク評価では、エンドポイントは明瞭である。人の死、傷害、または反応器のmeltdownのような工学システムの失敗である。ところが、生態リスク評価ではこの点がはっきりしない。
環境リスク評価では、多くの場合、漁獲量の減少や危惧種の絶滅のような個体群特性が最も有用である。最もいい例は、EPAのNational Crop Loss Assessment Networkで、そこでは一連のオゾンと亜硫酸ガスの基準と関連した穀類の収穫の減少量を推定している。
論点3)
エンドポイントを明瞭にすることはリスクマネジメントと意思決定に明確な基礎を提供するという利点がある。
リスクマネジャーは、その決定がもたらすであろう結果についてしることができるのみならず、コストとベネフィットの比較や、過去に受け入れられた、または受け入れられなかったリスクとの比較もできる。
また、化学物質の排出、水力発電、冷却水の影響、捕獲などの複数のハザードの魚類の個体群漁への影響を統合することができる。これに対して、PECがPNECを超えるという知識は、何も導かれない。
Glenn W. Suter Ⅱ
Environmental Risk Assessment/Environmental hazard Assessment: Similarities and Differences, Aquatic Toxicology and Risk Assessment, Thirteenth Volume, pp.5-15 1990
以上(次週につづく)
10月23日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は、「風評被害」でした。
トップページに戻る