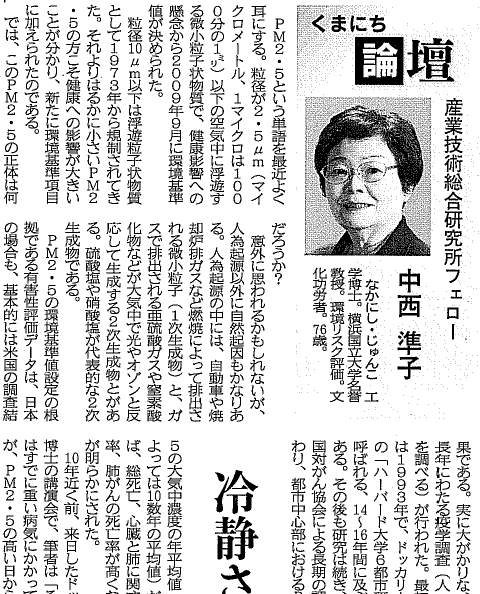 PDF�t�@�C��
PDF�t�@�C��
�G��685-2014.8.5�u�F��@���@�Z���N�V�����i�S3���j�|�F�䂳��̔w���ɂȂ����א�m�[�g�|�v
�F�䂳��Ɠ�̐����a
�V��Ђ���A�\���3���{���ł��B�����V���ɍL�����o�āA�������ƍl���Ă������A�F��I�q����i������j�Ɣ�������i������j���A���̉����ł�speech���ɂ��ĉ�����A����3�������B
���Ȃ�Ԍ����āA���ׂĂ�ǂ킯�ł͂Ȃ����A�]��x���Ȃ�̂��ǂ����Ǝv���̂ŁA���̒i�K�Ŏ����̊��z�������Ă݂��B�F�䂳��̒���Ƃ��ẮA����u���̋L�^�u���Q���_�v���L�������A����ɂ��Ă̋L�q�͔��ɏ��Ȃ��B
��͂�A�𐬂��Ă���̂́A�����a�̌������������ƁA�������瓱���o���ꂽ�A���Q�̎Љ�\���Ɋւ��邱�Ƃł���B
�킪���ł́A��x�����a�����������B��͌F�{�������A������͐V����������B�F�䂳�g���A�����͖T�ώ҂��������A�V���͓����҂Ƃ��ē������ƕ\�����Ă������A������������A�ٔ��ł̏ؐl�ȂǁA��т��Ă��̒��Ŋ��������̂͊m���Ɉ�����ł���B
�{�l�́A���������߂āA�����ł͖T�ώ҂ƌ����Ă������A����͂Ƃ�ł��Ȃ��B�m���ɁA���������͌F�{��w��w���̌����ǂ̌��тł���B�������A���̌�̍ٔ��ő傫�Ȗ������ʂ����A���������̂��߂̕����}�̂悤�Ȃ��̂�������͉̂F�䂳��ł���B
���̐}�̗��ɁA�d�v�Ȑl�����������B�����ی����ɓ��@�Y�����A����Ƀ`�b�\(��)�a�@���א�ꔎ�m�Ȃǂł���B�����āA�א씎�m�̋L�^�i�א�m�[�g�j�����ɏo�邫��������������B
�^���́u�א�m�[�g�v
���̏d�v�ȋL�^�����̃Z���N�V�����̒��ɂ���B
��́A3���̖`���Ɏ��^����Ă���ʐ^�ƌK���j������́u�F�䂳��̗��j�����������v�ł���B�K������́A�u�����ĈȌ�A15�N�Ԃ�����u�����������A����͂��ɓ��勳���ɂȂ�Ȃ����ʂĂʖ��̂܂I����Ă����悤�Ȍo�߂�����܂��āE�E1962�N8��11���͔ނ̐l���̗��j�����������ł������Ǝv���܂��v�Ə����Ă���B
�`�b�\�̍H����ŁA�H��r�����l�R�ɗ^������������{���Ă��āA�܂��ɐ����a���o���B���̎����͓r���Œ��~�������A�閧�ɂȂ��Ă����B�����m�����F�䂳�A�@�������߂ċ����ɖ߂��Ă���ꂽ�א씎�m��K�˂��B
�ŏ��͌����Ȃ������א씎�m���A�����ɂȂ�A�F�䂳��Ɍ������B���̏u�Ԃ������ɏ�����Ă���B���̃m�[�g�͒����ɂ͌��J����Ȃ����A�₪�āA�ٔ��ōא씎�m���،������邱�ƂɂȂ�B
���̃m�[�g��ڂɂ������Ƃ��A�����āA�א씎�m�̐������ɐڂ������Ƃ��A�����čא씎�m���F�䂳���M�p���Ă��̃m�[�g11�������������Ƃ��A�F�䂳����x���������Ǝv���B
�����ɕx�c���Y���i�F�䂳��̃y���l�[���j�u�����a�v�̏��_�������^����Ă��Ȃ����A�{���ɂ́A���̎������ʂ����^����Ă���B�א�m�[�g�͉F�䂳��̐����a�����̔w���ɂȂ����B�B���Ă��K��������A�����������̂������悤�Ƃ���ǐS�Ǝ��O�B�������Ǝv���B�����Ă������A1962�N8��11���B
�F�匤���ǂ́A����1962�N�����A���̏����O�Ɍ����������A���`������ŁA���ꂪ�H�ꂩ��o����Ă������Ƃ�˂��~�߂��B
�l�R�̂�����
������A��P��18�łɂ���u�R�����@�l�R�̂�����v�B�F�䂳��ƍא씎�m�Ƃ��V���������K�˂����́A���C���悢�ƌ����̂��A�����Ƃ���悤�Șb�B
�����̉ƂɃl�R�����Ȃ����ƂɋC�t�����א씎�m���A�u�l�R�����܂���ˁv�Ƃ����ƁA���̉Ƃ̂��������A�u�ςȎ��ɕ��������̂���㑱�����̂ŁA�l�R���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���āA�����̂���߂��̂��v�ƌ������B
�u���̃l�R�͂������v�ƕ����ƁA1�C�͒n�k�̑O�ŁA�����P�C�͒n�k�̌ゾ�Ƃ����B�����A�k��O�O�������A�����쐅���a���n�k�ɂ��Ƃ��������o���A�傫�Ȕ������Ă�ł����̂����A�����ŁA���ꂪ���낭�������B
������̉F�䂳��̖�
��1���̃^�C�g���́u���_�Ƃ��Ă̐����a�v�B
��2���́A�u���Q�ɑ�O�҂͂��Ȃ��v�B���Q�̎Љ�E�o�ϓI�ȑ��ʁB
��3���́A�u���Q�҂���̏o���v�B
��1���A��2���ɔ[�߂�ꂽ���e�́A�܂��ɂ��̖ʂł̓��{�̐��҂Ƃ��Ă̒n�ʂƋƐт������Ă��邪�A��3����ǂނƁA�F�䂳��Ƃ��Ă�肽�����������Ȃ������A������̖������������Ƃ�������B
���̊��́A�T�D���鉻�w�Z�p�҂̑����A�U�D�Z���^���̍��Ȋw�A�V�D�K���Z�p�̍l������3�͂��琬��D��������́A�F�䂳��̂�����̗��z�A�����͋Z�p�҂Ƃ��Ă����{�ō��������ɂ��肽���Ƃ������z��Nj�����p�����邱�Ƃ��ł���B
���Q�Nj��̌��ʂƂ��āA���̔��ʂƂ��ėǂ��Z�p�Ƃ͉����Ƃ��������������o����A���ꂪ�D�ꂽ�Z�p�ݏo�����ł���ƍl���Ă����Ǝv���B�������A�����œ|�ꂽ�B���̗��z�͗����ł��邪�A���Q�����ƕ��y�����Ŕ��ʘZ�]�̊����̂�����A����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A�����l���Ȃ��Ƃ��낪�F�䂳��̌����͂������B
�F�䂳��̂��������ʂ��A3���ł݂邱�Ƃ��ł���B
�u���Y�t�H�͔����Ȃ��ƍ���̂ł��v
�F�䂳��̕��͕͂��Ղŕ�����Ղ��B����A�����̐l�ɓǂ�ł��炢�����Ǝv���B�������A���^����Ă��镶�͂̈�ЂƂ͒Z�����̂������B�ǂ�����ǂ�ł�������A������₷�����͂ł���B
�F�䂳��̕��͂ɂ��āA�v���o�����Ƃ�����B
�F�䂳��͕��͂���肾�����B�q���̍��A����������Ɋ��������������܂�Ă��āA���̉e�����āA���͂͂����Ƃ��Ă����B�ꕶ��200�����炢�̒����̕��͂����������B����͂ƂĂ��ǂ��A�_���I�ł��炵���������A�����ْ����ēǂ܂Ȃ��ƁA�Ō�܂Ŏv�l�����Ă����Ȃ��Ƃ����������������B
������A�ҏW�҂��O�҂��A���̕��͂͂��������Z���������������ƌ����Ă��A�����Č������Ƃ��Ȃ������B���ꂱ�����A���͂��B������m��Ȃ��҂́A���͂������Ȃ��Ƃ������Ă����B
�F�䂳�A���Y�t�H�̌��e�����������Ƃ��������B�b�����ĕԂ��Ă������e�����ĉF�䂳��͌��{�����B���e�́A�^���Ԃ̍Z���L���ł����ς��ɂȂ��Ă����B��̕��͂́A3���S�ɕ��f���ꂽ�B���̏�A���鏊�ɉ��s���������B
�F�䂳��́A����ɓ{���ēd�b�����B�₪�āA���t�̕ҏW�҂��G��1���������Ăӂ��ƌ��ꂽ�B�F�䂳��́A�܂��A�{�����B�b�����āA���̕ҏW�҂��A���̎G���i�������t�j���J���Ęb���n�߂��B
�u�F��搶�A���ꕶ�t�ł��A���Ă��������A�����ł��傤�B�����A�搶�̕��͂����̂܂܈������ƁA���ʂ͐^�����ɂȂ�܂��B���t�͔����Ȃ��ƍ���̂ł��B��������A100���̍w�ǎ҂�����̂ł��v
�F�䂳��́A�т����肵�ĕ��t�̎��ʂ����������B�����āA�b�����āA�������_�����A�ҏW�҂̒����v����F�߂��B
�F�䂳��̕��͂́A���ꂩ��A����ɕ�����Ղ����̂ɂȂ����B
�����3���̒��ŁA���o�u���Y�t�H�v�Ƃ���̂͂�����B1����130�ŁA�u��������������̂͒N���v�B���̎��̂��Ƃ�͂悭�����Ă��邪�A���e�͉����Ă��Ȃ��B�������A�����A���ꂾ�����̂��Ǝv���B
�G��366-2006.11.13�@�u�F�䂳�肪�Ƃ��|�F�䏃����̎��𓉂ށv(�������N���b�N)
�u�F�䏃�Z���N�V�����v�S3��
���_�Ƃ��Ă̐����a [1] (Amazon�ւ̃����N)
���Q�ɑ�O�҂͂Ȃ� [2] (Amazon�ւ̃����N)
���Q�҂���̏o�� [3] (Amazon�ւ̃����N)
�G��684-2014.7.29�u�w�p��c�V���|�ł̕�upload �|�������l�Ȃ��̃��f���ƃ��X�N��e�̉ۑ�|�v
���{�w�p��c���ҏW���ďo���Ă��錎�����u�w�p�̓����v7�����Ɍf�ڂ��ꂽ�A���̏��_�u�������l�Ȃ��̃��f���ƃ��X�N��e�̉ۑ�v���Aweb��̃V���N�^���NGlobal Energy Policy Research (GEPR)�œǂނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
http://www.gepr.org/ja/
���̏��_�́A��N�i2013�N�j9��5���A���{�w�p��c��ÂŊJ���ꂽ�V���|�W�E���u�Љ������郊�X�N�Ƃ͉����v�Řb�������Ƃ̗v��ł��B
�u�w�p�̓����v7�����i���}�́j�ɂ́A���̎���speaker�Ǝi��̎R�n��������̕��f�ڂ���Ă��܂��B
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/
�����̑̕��ɁA���W�̎�|�^���S�ڕW�̍\�z�^�`�F���m�u�C�����̂̌o������^���q�͉ߍ����̃��X�N�ɂ��ā^���X�N�̑I���Ɗw�p������܂��B
����A���̒��̒����̕����A���{�w�p���͍��c�̋��āAGEPR��upload���ꂽ�̂ł��B
�G��683-2014.7.28�u�Ό˗@�L�ҁi�����j�̒��J�Ȏ���ŁA�_�����N���A�� �|�����O�C���^�r���[�Ɓu���҂̂��Ƃv�|�v
�����O�C���^�r���[�́A7��22���i2014�N�j��web�Ō��J����܂����B
http://mainichi.jp/feature/interview/news/20140722mog00m040006000c.html
�������̗[�����ɁA�u���҂̂��Ƃv�Ƃ��āA�ْ��u�������̂ƕ��ː��̃��X�N�w�v���Љ��܂����B�^�C�g���́A�u�Η����甲���o���Έāv�B
���̃����O�C���^�r���[�̒��ŁA����܂ŏ������Ƃ̂Ȃ��������ɂ��āg�������h�i�����Ӗ��ł͂���܂���j������A�{���o���O�A����Ɍ����A�N5�~���V�[�x���g�Ƃ�����Ă��o���O�ɁA���낢��Y�݁A�l�������Ƃ�b�����ƂɂȂ�܂����B
���̃C���^�r���[�́A�ʐ^���~���ł��邱�Ƃ���������邩�Ǝv���̂ł����{���o�������4���͂��߂ɍs��ꂽ���̂ł��B
�ΌˋL�҂̎���́A�����ڕW�l���o������ŁA�ڏZ�̑I��������Ƃ��Ă��邱�Ƃւ̎��₪���Ȃ�̒����ɂȂ��Ă��܂��B
5�~���V�[�x���g�ȉ����e�Ƃ��A�ڏZ�̑I������F�߂邱�Ƃ��������Ȃ��̂��A��Q�҂Ɉ��̃��X�N�����e���Ă���ƌ����͉̂��̂��A����́A�u���d�⌴������𐄐i�������̑�َ҂��Ƃ����ᔻ�����邪�v�A�܂��A��p�Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ȃǂł��B
�ڏZ�̑I����
�u�A�����́E�E���X�N�w�v�̒��ł͂��܂苭�����Ă��܂��A���͂��Ȃ�ȑO����A�u�ڏZ�̑I������F�߂�ׂ��v���咣���Ă��܂����B���ꂪ�A�傫����肠����ꂽ�̂́A�ȉ��̓�ł��B
�G��628�i2013.3.12�j�ǔ��V���@�����O�C���^�r���|�u���̏����ڕW�@�V�����ڈ��Łv
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak626_630.html#zakkan628
�G��629�i2013.3.14�j�����V���C���^�r���[�@�u�ڏZ�̑I�����@�p�ӂ��ׂ����v
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak626_630.html#zakkan629
�܂��A����̖{�̑�3�͂ŁA������w�y�����ѓc�הV����ɓo�ꂵ�Ē����Ă��܂����A�ѓc������u�l�������Ă���̂́A���S�ɏ������\�Ȃ�A�����ɏZ��ł����l�����͋A�҂���O��Ƃ����X�L�[���̍��ʐ��ł��v�i195�Łj�Əq�ׂāA��p�v�Z�Ɏ��g��ł��ꂽ�̂ł��B
3�͂̃^�C�g���́u�����́w�A�҂��ڏZ���x���l����|�o�ϊw�̎��_����v�ł��B�ѓc����ɂƂ��Ă��A�ڏZ�̑I������F�߂邱�Ƃ��A�o���_�������̂ł��B
���̉ۑ�Ɏ��g�ނƂ��̊����ɂ��ẮA����܂Řb�����Ƃ�����܂���ł������A�ΌˋL�҂̎���ŁA���̂��Ƃ��ڂ����b���@��ł������Ƃ��������v���Ă��܂��B�@
�u���d�Ȃǂ̑�َ҂Ƃ����ᔻ�v
���̃C���^�r���[��ǂ�ł��������B�܂��A�������Ȃ����Ƃ��A���ꂽ���ɂƂ��Ă����̂��Ƃ������Ƃ��l���Ă݂Ă��������B
�����������X�N�_�Ƃ́H
�Ȃ��A���X�N��e�̕K�v�����咣����̂��H�t�@�N�g�ɍS��͉̂��̂��H����������ł����B
�����āA�u�����̂��߂ɕK�v�ȃ��X�N�_�v�Ƃ������_�ɒH�蒅�����̂ł��B
�G��682-2014.7.21�u��Â��ق���PM2.5���v�i���܂ɂ��_�d�j
�u��Â��ق���PM2.5���v���A7��20���i���j�F�{�����V���́u���܂ɂ��_�d�v�ɏ����܂����B���̑S�����A�����Ɍf�ڂ��܂��B
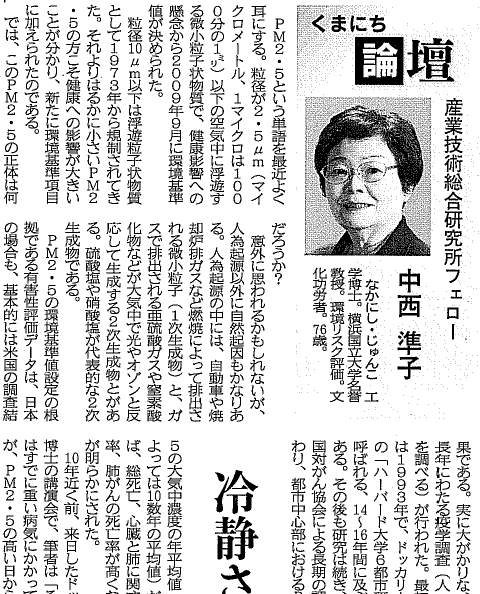 PDF�t�@�C��
PDF�t�@�C��
�G��681-2014.7.18�u�w��l�̂��炭��x�̂��Љ�v
�|���҂̂P�l�A�Y�������S�Ȋw���������C�������̏��싱�q����ɏ����Ē����܂����B���̂Ƃ���A���Ȃ�ǂ�����s���Ƃ̂��ƁB
�P�Ȃ�y���݂ł͂Ȃ��A���������m�I�Ȋy���݂��A�������������Ă����ł��ˁ[
�{�̏Љ�F�u��l�̂��炭��`���S�͂������Đ����ɂȂ����`�v
�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������@���S�Ȋw��������@���싱�q
���̂��сC�u�k�Ѓu���[�o�b�N�X����u��l�̂��炭��`���S�͂������Đ����ɂȂ����`�v���o�ł��܂����D��������̂����ӂɂ��C���̏�����肵�ďЉ���Ă��������܂��D
�{���́C���ː������C�ܖ������C��ʈ��S�Ȃ�10�̃e�[�}�����グ�C���̊�l�̍�����ǂ������̂ł��D��l�͎����������S�ɕ�炵�Ă������߂̏d�v�Ȋ�Ղƌ�����ł��傤�D�������C�u��l����/�����Ȃ��v�Ƃ��������Ƃ����ڂ���銄�ɂ́C���̍����͂��قǒm���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���D�u�C�ɂȂ��Ă������ː������̊���āC�ǂ�����Č��܂��Ă���́H�v����C�u����ȂƂ���ɂ�����Ȋ�l������I�v�Ƃ����Ƃ���܂ŁC��l�I�^�N�S�l���y���������ق����܂��D
�]���^�̉Ȋw�����Ŋ�l�͌��܂�Ȃ�
���i����j�͎Y�ƋZ�p�����������ʼn��w�����̃��X�N�]���Ɍg����Ă��܂����D���X�N���v�Z���Ċ���Ȃǂ̊�l�Ɣ�r����C�Ƃ������Ƃ��o�����邤���ɁC�u���̊�l�͉��������ɓ����o���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����_�ɂ������������悤�ɂȂ�܂����D�������M�҂̑���C�i��C�ݖ{�������@�ւ����Ⴆ�Ǔ��l���Ǝv���܂��D
��l���v���Z�X�ɂ́i���������̌��ʂƂ������j�]���^�̉Ȋw�����łȂ��C�ꌩ�[��������肪�����Ă�����i�����̐l�ɂƂ��āC�u�s�m�����W��10�Ŋ���v�Ƃ������葱���͂���ɓ����邩������܂���j�C����ł����́H�Ƃ������肪����Ă����肵�܂��D�܂��C��l�����܂������_�ł̎����\������{�̐H�����Ƃ������Љ�I�ȃg���[�h�I�t���l������Ă����肵�܂��D���̂悤�ɁC�o���G�e�B�ɕx��l�̍�����R�����āC���̔w�i�܂œ��ݍ��ނ��Ƃ́C���̓�����ł��菃���ɖʔ���������܂��D
���X�N�w�̓��发�Ƃ��Ă�
��l�́C��������ς���C�Љ������郊�X�N�ƘA�����Č��܂���̂ł��D�܂�C��l�����߂�v���Z�X��m�邱�Ƃ̓��X�N�Ƃ͉����C���X�N�]���Ƃ͉�����m�邱�Ƃł��D
�{���́C��̗Ⴉ�����C�V�����`�̃��X�N�w�̓��发�ƂȂ��Ă��܂��D���w�����������ɂƂǂ܂炸�C�H�����⎖�̂Ƃ������C�g�߂ł͂�����̂̏]�����X�N�Ƃ����ϓ_����͂��܂萮�����ꂽ���Ƃ̂Ȃ��e�[�}�����ꍞ�݂܂����D
���܂��܂ȕ���̊Ԃɂ���_�������O���ꏕ�ɂȂ�C�Ƃ����肢������C���̂悤�ȍ\���ɂ��܂����D
�uJournal of Taroten�v�ihttp://homepage3.nifty.com/turase/opi_j383.html�j�̊Ǘ��l�E����Ăɂ��ƁC�{���́u��������̊����X�N�_�̓�Ԑ������Ǝv�������C���ۂɓǂ�ӊO�ƒ��g�͑N�x������C�ǂ݂₷���v�Ƃ̂��Ƃł��i����Ă�C���Љ�肪�Ƃ��������܂��j�D
�ڎ��������ɂȂ��āC�����̂���͂���ǂ����D�v�킸�j�����Ƃ���R�������[���ł��D
�{���̊y���ݕ�
�{���͑��l�ȓǂݕ����ł��܂��D��l�ݒ�Ɋւ���Ă�����l�̒q�d�������Ȃ���m���t�B�N�V�����Ƃ��Ċy���ނ��Ƃ��\�ł����C�F�l�m�l�ɂ������I����ۂ̃l�^�{�Ƃ��Ă��悢�ł��傤�D
�������߂́C�����g�����X�N�̊Ǘ��҂ɂȂ�������Łu��������l�����߂�Ƃ���ǂ�����H�v�ƍl���Ȃ���ǂނ��Ƃł��D���̖{��ǂݏI��������Ȃ��́C����Ƃ������l�̍������C�ɂȂ��Ďd���Ȃ��Ȃ邱�Ɛ��������ł��D
�Љ���ȉ��̃T�C�g�ł��ǂ߂܂�
���L�̃T�C�g�������Ă������������D
�u����r�W�l�X�v�u���[�o�b�N�X�O�u���}���فc�O�������ǂ߂܂�
�ihttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/39614�j�D
�G���u�{�v�ł̏Љ�c���㓹�v�̏������Љ�ł�
�ihttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/39606�j�D
�u��l�̂��炭��`���S�͂������Đ����ɂȂ����`�v
���㓹�v�A�i��F�u�A���싱�q�A�ݖ{�[�������A�u�k�Ѓu���[�o�b�N�X�A�ō�994�~
�ڎ��F
��P�́@��������Əܖ������@�`�u���������v�̊�l�́u���������v�`
��Q�́@�H�����Ɗ�l�@�`��l��߂܂����H���{�l��߂܂����H�`
��R�́@�������̊�l�@�`�f�����ׂ����H�@���ꂪ��肾�`
��S�́@���ː������̊�l�@�`�u�b��K���l�v�Ƃ͉��������̂��`
��T�́@�ÓT�I�Ȍ��ߕ��̊�l�@�`�u���X�N�Ƃ͖��W�v�Ȋ�l������`
��U�́@��C�����̊�l�@�`�u�o�l�Q�E�T�v���߂��镑�䗠�`
��V�́@�������́u���Ə����v�̊�l�@�`�u���S���v�ł�����������̂��H�`
��W�́@���Ԍn�ۑS�̊�l�@�`�l�Ԃ̓s���Ō��܂�u������邩�v�`
��X�́@�댯������̋����̊�l�@�`�u�d�ԓ��̌g�ѓd�b�v���琅�f�X�^���h�܂Ł`
��10�́@��ʈ��S�̊�l�@�`�u�N�ԂS�O�O�O�l�v�͎�����郊�X�N���`
�R�����@�u�R�b���[���v�͉Ȋw�I���^�u������郊�X�N�v�̑傫���^���{�l�̕��ϑ̏d�͉�kg���^�p���؍ݗ�������l�̌��������^�����ɂ߂郁�^�{�̊�l�^���C�^�[�̗c����^�������X�N���H���͂������Ȃ��Ȃ�S���^�C���t���G���U�̏o�Ȓ�~���ԁ^�Z�N�n���̊�͂ǂ��ɂ���̂�