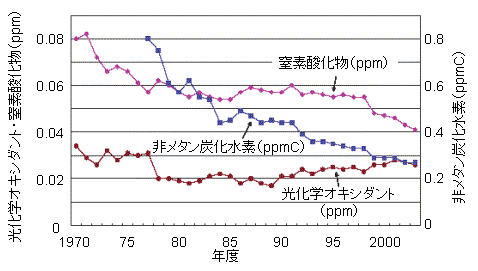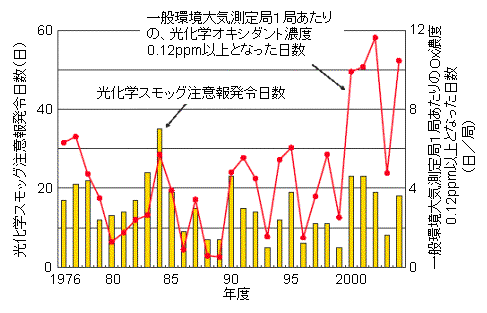雑感330-2006.1.16「ビスフェノールAの詳細リスク評価書−生態リスク評価算出手法が新しい−」
A. ビスフェノールAの詳細リスク評価書−生態リスク評価算出手法が新しい−
ある年賀状
ある方からの年賀状にこう書かれていた。“私たちの所(自治体)では、「環境ホルモンの名を出しては、予算がつきません」(予算査定の財務担当の方針)。”
こうなっちゃうのですね。余りにも大げさなことを言い、世間を騒がせて予算をとったから。今でも、内分泌攪乱物質の研究や調査のために、一定の予算は必要だろうが、反作用としてこのようになる。
しかも、この負の影響は内分泌かく乱物質だけでとどまらず、化学物質全体、または環境問題全体に対する疑い、ためらいになる。こういう場面を私は一度経験している。それは、1970年代の水銀規制である。
わが国は、水銀電極法によるカセイソーダ製造法を禁止した。それが余りにも急であり、事業者の負担も大きかったために、この後、実に長い間、日本社会が化学物質の調査や規制問題に、口を噤んでしまうのである。市民運動さえも、化学物質問題を避けてしまうという状況があった。その時期、旧環境庁の廃止も何回か話題になった。
地道にやることが一番。小さなことでもそれなりに研究を続けてゆくには、問題としている事柄のリスクを評価し、その大きさを理解してもらうことが必要だと思う。
地道な研究成果(ビスフェノールAの詳細リスク評価書)
地道にコツコツとの代表と言えるかもしれない。私の所属する化学物質リスク管理研究センター(CRM)から、旧年末、詳細リスク評価書「ビスフェノールA」が、丸善から刊行された(税込み3045円)。環境ホルモンとして問題になり続けた物質である。所謂低用量問題についても、CRMとしての見解を出しているので、是非読んで頂きたい。概要などは、http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1-10.html で見ることができる。
今回の出版は日本語だが、世界的に見ても重要だと考えて、英語版を出すことにした。数ヶ月後になるが(費用の点で出版はできないが)、CRMのHPからdownloadできるようにする。
これは、ヒトの健康へのリスク評価でも、また、生態リスク評価でも新しい方法を使っている。ここでは、生態リスク評価について述べる。
概要
概要には、生態リスク評価結果について以下のように記述されている。
「生態リスク評価では、3つの評価エンドポイント((1)ハザード比法での判断基準、(2)イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続可能性、(3)高濃度汚染地域での魚類の生息状況)を設定した。
水中のビスフェノールA(BPA)濃度が得られた1,100以上の地点においては、評価エンドポイント(1)の評価の時点でリスクは懸念レベルにないと判断された。評価エンドポイント(1)の評価では判断が保留された地点に対して評価エンドポイント(2)、(3)の評価を行った。
これらを総合的に判断した結果、BPAによる生態リスクは、水生生物(特に魚類)の地域個体群の存続を脅かすレベルにはないと結論付けた。」
新しい手法
上の記述の(2)の部分があたらしい*。(1)はしばしば用いられる方法だが、生物個体への無影響濃度以下かどうかで危険性を評価する方法である。これに対して、我々は個体レベルではなく、個体群レベルで存続が可能か否かを評価すべしと主張し続けた。
ただ、個体群レベルでの存続可能性を評価するためにデータがなかなか入手できない。そのような視点で調査が行われていないからである。そこで、既存のデータから如何に推定するかという方法を 、これまでの水産学での知見を用いて導き出した(この方法の最初のアイディアは、松田裕之さんから出ている)。
*この方法の基本的な考え方は、勝川、宮本、松田、中西(2004)魚類個体群の生態リスクの簡易評価手法,保全生態学研究,9:83-92の論文による。
データ補完の方法を図1に示した。
そして、結果を図2に示した。
|
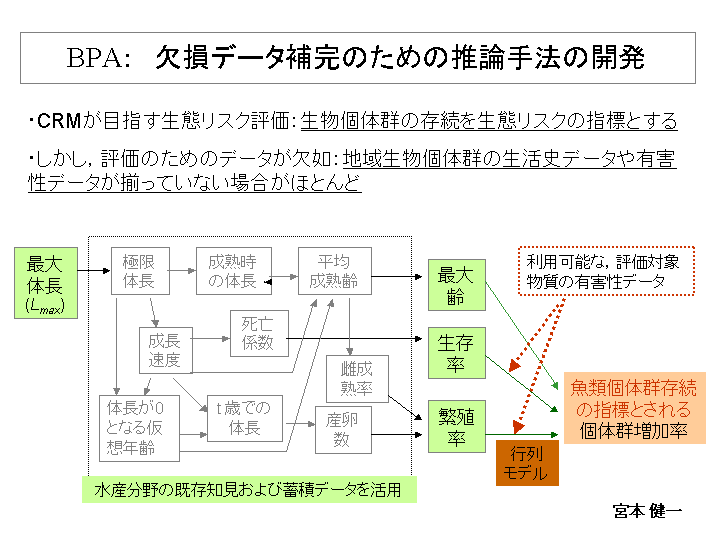
|
|
図1 |
|
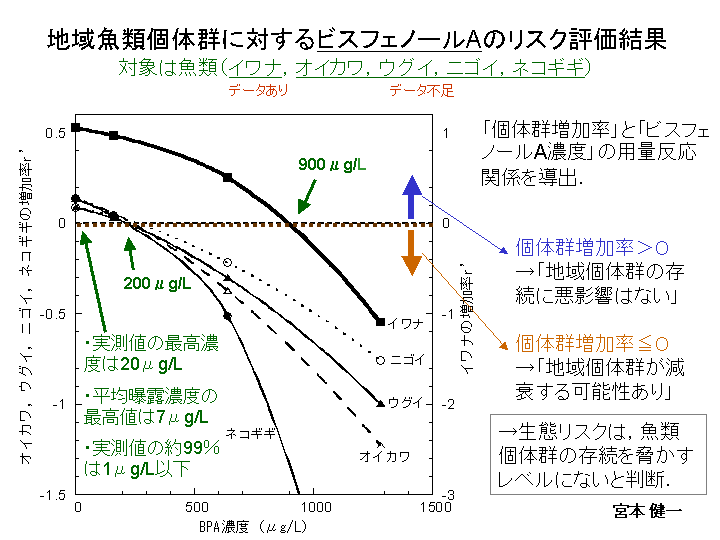
|
|
図2 |
横軸は、水中のBPAの濃度。縦軸は、個体群の増加率である。この値が、0以下(茶色の矢印)だと個体群は減少傾向を示すが、0以上(青の矢印)なら存続に影響がない。河川水中BPA濃度は、最高値でも20μg/Lで、いずれも個体群の増加率は正の値となるので問題がない。BPAの評価書で、また一つの扉を開いたことになる。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):皆様の力を貸してください。ご意見書提出のお願い。(ここをクリック。)
雑感329-2006.1.10「年のはじめに」
A. 年のはじめに
年のはじめに書きたいことがあった。アスベスト問題がおきると総懺悔、回転扉の事故が起きても総懺悔みたいになる。この総懺悔主義は一向に教訓にならないことを書こうと思っていたのだが、その前に、一つニュースが飛び込んだのでこれに替えた。
ニュースと言っても、別に新しい事件というわけではない。旧年11月25日に行われた毎日出版文化賞の授賞式における、私のスピーチを会場で録音した人がいて、それが送られてきた。それを文字にしたので、これを、新年の挨拶にすることにした。話しことばそのままなので、二度重なったりしている言葉もあるが、そのままとした。
スピーチ
この度は、非常に評判の高い賞をいただきまして、本当にありがとうございます。環境リスク学というものを自分で始めてきたわけですが、その一番の精神は、いつも言うことなのですが、環境問題に対するのに正義感で対処してはいけないということです。
環境問題というものは人類が最初から持っている問題であり、それは、折り合いを付けるという問題でしかない。従って、どうやって折り合いを付けるかという科学が必要であり、考え方が必要なのであり、なにか一方的に良いとか悪いとかという正義感で立ち向かってはいけない。そういうことをずっと思っておりまして、そのことを学問という形にしていったのが環境リスク学です。
先ほど辻井(喬)審査委員長からもお話がありました(*)ように、四面楚歌、まさに四面楚歌なんですが、そういう四面楚歌に私がある程度耐えられるのは、もう一つの四面楚歌、35年くらい前、公害問題と言えば国を滅ぼす気かと言われる様な時から環境問題をやってきたという気持ち、その気持ちが私を支えているものです。
今はやりの環境問題というものをやっているのではない。その時には正義感を持って公害問題に取り組んできた。しかし、環境問題の性質が変わってきてこういう理論が必要になってきた。そのことが、私の支えになっております。
今回、米本先生から選評を書いていただきましたが、やさしい暖かい気持ちで書いていただいたことに本当に感激しております。ありがとうございます。実は、私は1979年に、この毎日出版文化賞の最終選考にまで残ったのです。1979年6月に「都市の再生と下水道」という本を初めて出しました。それが、日本評論社でした。その後全く日本評論社では書いていなかったのですが、今度また日本評論社です。
どういうわけか日本評論社から出すと良いというような関係があるのですが、その本が最終選考まで残ったんですね。しかし、駄目でした。それで、ちょっとなんとなく、毎日出版文化賞というと忸怩たる思いをもってきたんですが、ここでリベンジを果たせたというような感じでございます。これで割り合い気楽に死んで行けるかなという気持ちもしております。
(死と言えば**)もうちょっと、リスクとか安全とか環境の問題というようなものに、死というものを真正面から取り上げて、科学というものを今後構築していきたいと思っているところです。
この出版にあたりましては、日本評論社の佐藤さんに非常にお世話になりました。本を出すつもりは全くなかったんですが、ともかく最終講義を本にさせてくださいという佐藤さんの熱意でこの本が出来ました。出版社の皆さんにも大変感謝しております。ありがとうございます。
(*)辻井喬審査委員長が、選評の中で、中西さんがこの文章を書き、発表した時は、それこそ四面楚歌であったと思うということを言ったことを受けた話。
(**かっこ内の言葉を補った)
B. 藤原帰一さんの視点
06年1月6日の朝日新聞朝刊「私の視点」に掲載された藤原帰一さん(東京大学教授)の「平和の時代へ『理想主義』を超えよう」という文章は、とても良かった。
C. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):反訴の理由(1)
私が松井さんに訴えられたのは04年03月16日だった。最初はただおろおろしていたが、第1回目の口頭弁論(5月27日)が開かれる頃には、この提訴の性格が大凡分かるようになってきた。松井さんが新聞記事について説明した(以下、「説明」と略す)というのは「事実ではない」ことは分かっていたし、どう考えても違法訴訟であると思ったので、反訴すべきとは思っていた。しかし、そこまで事を荒立てなくとも落ち着くのではともおもったりして、行きつ戻りつの思考の末、5月27日出した答弁書は、以下のようにした。
「なお、本件のような問題を訴訟の場に持ち込むことが不適当であることは明白であり、違法提訴にあたるものと考えている。被告としては、原告が、冷静さを取り戻して本件訴訟を速やかに取り下げることを期待するものである。」
つまり、取り下げを勧めたのである。
しかし、時を経るにつれ、松井さんの主張は強くなり、「説明」の内容は微に入り細をうがった詳しいものになり、ついには、甲第8号証として、口頭説明の要点と称する、slideのようなものまで提出された(7月15日)。
すでに、多くの方がこのことについて知っておられると思うが、そのような説明は一切存在しなかった。「説明」はなかったことの証拠として、シンポジウムの全過程の録音テープを提出することにし、反訴に踏み切った(反訴状提出05年9月21日)。
なぜ、反訴に踏み切ったのかの理由を私はまだ述べていなかった。
反訴状の内容は、応援団のHPにupされているが、そこには多くの文書があり、すべてに目を通すのは大変なので、今回と次回に分けて反訴状の内容を説明することにする。
「反訴原告の請求について」というところで、5つの理由を挙げた。被告だった私は、ここでは反訴原告になっている(ややこしいなあ)。つまり、松井さんは本訴原告、反訴被告になるらしい。
第1は、事実関係の確認と、事実と意見との区別である(省略)。
第2は、まさに「説明」の部分である。
”本訴原告(松井さん)準備書面1の中で、「原告(松井さん)らの研究成果からダイオキシンの毒性機構が判明しつつあるところそのメカニズムは有害性が懸念されるナノ粒子と共通性を持つことが推定されることを原告独自の見解として指摘した」と書いているが、そのような「詳細な説明は一切していないし、京都新聞についても何ら独自の意見を付することなく、そのまま新しい環境汚染が報じられたものとして紹介したのである。」(反訴状より)”
・・「これ以上何らかの説明をつけなかったことは、発言内容の録音テープから客観的に明らかである」(録音テープは証拠として提出)。
(つづく)
次回口頭弁論 1月27日(金)10:30〜(横浜地裁)
D. 小さなお知らせ
・ 東京FM 日曜日の朝
1月15日(日)と22日(日)午前6時10分から40分、「環境リスク学」について、中西が質問に答えます。
・ 研究所の研究員
研究所の常勤研究員を募集しますというようなことを書いて、それきりになっています。嘘つきみたいですみません。実は、常に、常勤研究員を探しています。私どもの研究センターで、常勤研究員として働きたい方は、研究センターの誰にでもいいですから、声をかけてください。両方の要求が適合すれば、win winです。また、PDも求めています。
雑感増刊号-2006.1.4「講演会申し込み締め切りのご連絡」
「1月20日に予定されております「詳細リスク評価書出版記念講演会−リスク評価の理念とノウハウ−」は、参加希望者数が500名に達したため、参加申し
込みの受付を締め切りました。またの機会によろしくお願いします。
雑感328-2005.12.27「国産牛肉のPRを見て考える」
A. 国産牛肉のPRを見て考える
12月1日号(11月24日発売)の「週刊新潮」に掲載された1頁のPRを見て、私は考え込んでしまった。それには、“「農家の顔が見える国産食肉は、安全で、安心なのですね。」―生島 ヒロシさん”という大きな見出しがついていた。
私が考え込んでしまったのは、
(1) このPR記事は、生島ヒロシが聞き手になっていたが、答える側の人が、食品安全委員会プリオン専門調査会座長の吉川泰弘さんだったからである。しかも、顔写真も掲載されていたからである。
(2) このPRの主体は、(財)日本食肉消費総合センターであったが、その下に、後援 農林水産省生産局と書かれていたからである。
(3) このPRが出たのが、政府が米国牛肉輸入再開を正式に決めた12月12日以前だったからである。
国産牛肉の安全性を言っているだけだが
もちろん吉川さんは、別に米国の牛肉が危険と言っているわけではなく、ひたすら、「日本は生産から消費まであらゆる段階で対策を講じています」とか、「国産牛肉の場合」というような言い方で日本のシステムが良いことを強調しているだけである。それでも、米国産牛肉のリスクと国産牛肉のリスクは同等かという諮問を受けて、長々と議論してきた食品安全委員会プリオン専門調査会の座長だから、米国との比較で言っているのだろう。
つまり、このPRを読むと、「日米牛肉のリスクは同等ではない」と言いたいのだなと受け取れる。尤も、見出しに「−生島ヒロシさん」と付いているのは、これは吉川さんの発言ではなく、生島さんの発言ですよという注意だとは思う。
吉川さんが、個人的に国産牛肉がより安全と思っているとしても、国産牛肉を推進するようなコマーシャルには出ない方がいいと考えるのが普通だろう。それにもかかわらず、ひどく目立つかたちで出ている。なぜだろう?
また、こういう時期(政府の決定が間近い)なら、なるべく中立的な立場を守ることが求められる農水省までもが、こういうPRになぜ名前を出すのか。それがなかなか理解できず考え込んでしまったのである。こういうことをすれば、プリオン専門調査会の中立性を疑わせることになるし、農水省の中立性も疑わせることになる。農林水産大臣が諮問し、また、政府の意思決定に大きな責任がある立場なのだから、発言に注意すべき時だろう。
敢えて、なぜ?
どうして、そういう疑いを抱かせるようなことをするのか、それが分からなくて考え込んでしまったのである。
米国産牛肉の輸入が再開されても、消費者が、米国産牛肉は危ない、国産牛肉が安全だと考えて、例え高くとも国産牛肉を買ってほしい。これはそのためのPRであろう。しかし、そのPRに、プリオン調査専門調査会座長を引っ張り出すことや、農水省の名前まで出すことは、食品安全委員会を完全に無視するというか、泥を塗るというか、そういうことになるのだが、なぜ、そういうことをするのかが私には分からなかったのである。
所詮リスク評価や安全性評価は、中立でなくていいよ。いや、政治に従属していいよというような声が、このPRから聞こえるような感じがするのである。
もちろん、完全中立なリスク評価がある筈はない。しかし、できるだけ中立であろうとする努力が大切だし、もし、食品安全委員会に冷静な中立的な立場で判断してもらおう、あるいは、その結論に敬意をもって接しようと考えていれば、ここに吉川座長を引っ張り出してはいけないと考える筈である。その配慮が全くない。
政治に振り回されたリスク評価
米国産牛肉の安全問題(リスク評価問題)は、科学的なリスク評価の課題としては、簡単な部類に属する。それが、これほどまでにこじれた一つの原因がここにあるように思う。
それは、リスク評価や安全性評価を、政治的な目的で操作していいと考える立場である。米国産牛肉のBSE問題は、そのリスクとは別の政治的な目的で、危険が過大に言われ続けた。
国産牛肉を奨励したいと考える人々がいて、その運動を展開するということがあってもいい。あるいは、それを国の政策にして、国内畜産業を保護するために、輸入食肉に関税をかけるという政策もあるだろう(自動車やその他多くの工業製品を輸出している日本に、そういう政策が許されるかは、WTOなどで決められるであろう)。
しかし、それはそれとして主張すべきで、だからと言って、この牛肉は危険だから輸入すべきでないという主張は許されない。だからこそ、中立とされる食品安全委員会にリスクに関する評価の諮問が行われたのである。このPRは、その前提を踏みにじっているとしか思えない。
プリオン専門調査会が長引いたのは
プリオン専門調査会では、米国産牛のリスクを巡って、人へのリスクとはほとんど関係がないことが、恰も重大な問題であるかのように延々と議論された。それは、学者の近視眼と思ってきたが、実は違うのではないか。このPRを見て、そのように考えるようになった。国産牛肉を奨励したい、米国からの牛肉は入れたくないという政治的意図で引き延ばされたのではないかと。
安心安全
あらゆる場で、安心・安全政策が声高に言われるようになっている。本当に安全を求めるならば、それがどのくらい安全か(逆に言えば、どのくらいリスクがあるか)について、できるだけ客観的に、可能な限り科学を使って判断することが求められる。求めなければおかしい。
しかし、一度これが大事となると、一切の客観的評価抜きで、目的のためにリスクの程度が作られてしまうのが現状である。政治目的でリスクの大きさが変化するようでは、リスクは減らない。まして、安全は望むらくもない。
リスク評価の第一歩は、評価者ができるだけ中立であろうとするところから始まると言ってもいい。それを、自分から崩すようでは話にならない。当たり前すぎて書くのも恥ずかしいのだが、食品安全委員会をこのように利用してはいけないと思う。
リスク評価とリスクマネジメント
リスク評価をできるだけ客観的に行っても、そのリスクの大きさのみを基準にリスク削減対策をとることはできない。そのリスク削減のために必要な費用の大きさや、そのリスク削減によって別のリスクが生じてしまうかなどを考慮しなければならない。
これこそが、リスクベネフィットと言われる管理原則である。だから、例え米国産牛肉のリスクがそれほど大きくないとわかったとしても、輸入をすれば他の問題がおきるというのであれば、輸入禁止を続けることもありうる。そういう場合には、それは米国産牛肉のリスクが大きいからではなく、リスク削減に伴う、別の「こういうリスク」(例えば、国内畜産業が壊滅的な打撃を受ける)があるから、輸入再開すべきではないと説明すべきである。
その二つは、分けて考えるべきなので、この場合なら、輸入再開すべきでないという考えが、リスク評価に影響を与えていないということの証明が、明示的か暗示的かは別として、必要なことなのである。にも拘わらず、その原則をわざわざ崩すような、疑わせるようなPRをしてしまうのは、・・・多分外の世界が見えないからだろう。
ここまで書いてきて、私はこのPRの目的が、国民へのPRではないと思うようになった。PRの規模も小さいことを考えると、これは、吉川さんと農水省の存在証明、いや、帰属証明かなと思うようになった。他の方のご意見も聞いてみたい。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):ご支援多謝
私にとっての2005年は、やはり、松井三郎さんに名誉毀損で訴えられた年ということとして記憶に残ることになるのだろうか。それは避けたいのだが。
救いは多くの方が支援のために動いてくれたことである。天羽優子さん、山本洋三さん、濱田弘さんが「応援団」を組織してくれた。天羽さんと山本さんは、このことが持ち上がるまでは、お名前も知らなかった。ネットの活用術に長けていて、これまで私が経験してきた市民運動や、学生運動、住民運動とは、ひと味も二味も違う。そこが、新鮮で勉強になる。
その3人の呼びかけに応じて、多くの方が、横浜地裁に傍聴に来てくれて、また、ネットや文筆を通して応援してくれた。多くは、これまでは知らなかった方である。心から感謝したい。提訴されたことの打撃より、この喜びの方が、今や大きくなりつつある。来年の秋頃になって、「2005年は多くの人の親切に恵まれた良い年だった」と言えるようにしたいと思う。2005年最後の雑感。
雑感327-2005.12.19「環境省も変わりましたね」
A. 環境省も変わりましたね
環境省環境保健部環境安全課の協力で作られた「チビコト」という小冊子が送られてきた。「特集:ロハス的環境ホルモン学」となっている。これを読んでいささか驚いた。そして、「環境省も変わりましたね」と。もちろん、悪い意味で言っているのではない。変わってくれて良かったと思っている。
30頁ほどの小冊子である。ソトコト1月号(12月5日発売)の付録として作られたと書かれているが、環境省に申し込めば付録(「チビコト」)だけでも買えるらしい。
チビコトの目次
目次は以下のようになっている。
1. ジョンサンプター教授のインタビュー(「メス化した魚の発見」)
2. 自然現象としての「魚の性転換」(桑村哲生)
3. 環境ホルモン問題から何を学ぶか(安井至×小出重幸<読売新聞編集委員>)
など。
サンプター教授のインタビュー
ジョン・サンプター教授は「奪われし未来」(1996)にも登場する。ローチという魚のメス化の原因を追究し、当初、ノニルフェノールとの関連を主張した学者である。
チビコトのインタビューで、サンプター教授は「ノニルフェノールの研究を続けたことで、ノニルフェノールが原因であるとする、短絡的で間違った答えに行き着いてしまった」と言っている(8頁)。ノニルフェノールが原因となっていた地域もあったが、一般的には人の尿に起因する女性ホルモンが原因物質であることを突き止める。
西川洋三さんの「環境ホルモン」(日本評論社)には、「ション・サンプター氏は、96年のサイエンスに寄稿した論文で、合成物質を「主犯」とみた初期の姿勢を反省し、こう述べている。結果はこうなるはずと思いこんではいけない。今回の件はその好例だ」と書かれている(70頁)。
それにしても、わが国で多摩川のコイのメス化(井口泰泉氏の調査)が見つかった、その原因がノニルフェノールであるかのような報道がなされるのは、この後の97年だし、わが国の騒動は98年に一挙に火がつくのだから驚く。多摩川のコイの調査とその報道は、確信犯としか思えない。それとも、これも「予防原則」なのだろうか?
魚の性転換の話
これも面白い。魚が容易に性転換すること、生き残りのためにそれが必要なことが書かれている(桑村哲生さんの文章)。こんなこともあるの? でも当時ヒラメだの、タニシだののメス化を報告した大学の先生方の専門は何だったのかなと考えてしまう。「野生生物の性になにか変化が見られたとき、それが社会条件などによる自然本来の性転換なのか、それとも化学物質などの人為的な影響によるものかを、慎重に見極める必要がある」と結ばれている。この当たり前のことが新鮮に聞こえる。
環境省の変身
このことを、どうしてあのとき言ってくれなかったの?と言いたくなるが、環境省が悟って、変わったことは良いことだ。知らん顔して皆の忘れるのを待つこともできるが、それをせずに、このような文書を出すというのは、役所としては珍しい。多くの研究者や、当時過激本を書いた人たちがほおかむりしている中で、このような行動をとることは高く評価したい。ただ、環境ホルモンは反省するが、また、新しい何かでは大騒ぎするということのないようにしてほしい。
環境ホルモン問題とのロハス的つきあい方として、4項目あがっている。 (1)
慌てず、騒がず、冷静に情報を探る、(2) 自分のなかに判断基準をもつ、(3)
行動することで積極的に関わる、(4) ほんとうの心地よさにこだわる(ロハスの意味はよく知らないが)。
B. 横浜市立図書館 録音図書
横浜市立図書館では、視覚障害者のために録音図書を用意しているとのこと。この度、中西の「環境リスク学」の録音図書が出来上がったという連絡を受けた。1セット送って頂いたが、90分テープが6本あった。
ボランティアが音読し、それを録音することで出来上がるのだそうだ。大変なものですね。録音図書の貸し出しは、登録された、障害により読書が困難な方に限られている。
この図書館では、本文中に含まれる写真・図・表をどのように読むかの、朗読者のための講習会を、2月と3月に行うのだが、そのきっかけが「環境リスク学」だったというご連絡を頂いた。図や表が多い本で、録音図書となるものが少なかったのでしょう。朗読者の方のご努力に感謝。
C. 毎日出版文化賞授賞式
やや旧聞となってしまったが、11月25日に赤坂プリンスホテルで、毎日出版文化賞の授賞式と記念パーティーが開かれた。受賞作品5点の内1点(「形の科学百科事典」)を除く4点にある共通点があった。
選者(代表者:辻井喬さん)の指摘にも、受賞者自身の言葉にも度々出てきた。それは、単純な「二極対立を超えて」とか、「左右対立を超えて」という言葉だった。村上龍さん、松本健一さん、佐藤優さん、それに中西。そういう時代になってきた、そして、これから書かれる物の方向性も、これだなという確信のようなものを得た。今年の毎日出版文化賞は、問題作、話題作が多いと言った人もいたが、確実に時代の変化を示したものとなっていた。
記念パーティーは、中曽根元首相や鈴木宗男議員の出席もあり、とても賑やかであった。
D. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):
内山充さんのご意見
次回口頭弁論 1月27日(金)午前10:30〜
中西応援団の掲示板を読んでいて教えられることが多い。この掲示板は書き込みのレベルが高い。12月06日に書き込まれた「内山先生のコメント」というのがあり、そこで、第11回 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会議事録(厚生労働省 医薬局 審査管理課 化学物質安全対策室)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/0107/s0731-3.html)が引用されている。
ここに内山充さんの意見が載っていて、この書き手はそれに興奮すると書いている。この議事録は見たことがなかったが、今回初めて読んで、私も興奮し、脱帽の感を強くした。内山充さんが言っていることは、私が環境省のシンポジウムで言ったことと同じ趣旨である。平成13年にこういうことを言われてしまっているのだ。内山充さんは、元医薬品食品衛生研究所の所長。
こう言っている(議事録からの引用)。
「コミュニケーションというものを、誰かほかの人がやればいいと思っていただかないように、先生方がずっとこれまでお話になったデータをどう解釈するかというのは、自分たちではないのだと思わないようにしていただきたい。そのデータから何を、明日すればいいかということを指示するのは、それは行政でもなければ一般の消費者でもないのです。それは実験を担当した先生方に言っていただかなければ結論は出ないのです。
ところが今までのお話の中で、もちろん結論が出ているものもありますけれども、わからないことがたくさんあるわけです。わからないことがたくさんある場合に、科学者というのは結論を言わない。「例外がある」あるいは「不明である」、「これはデータがない」、「これは何も言えない」。それは科学的には正しいことなんですけれども、コミュニケーションということが絶対必要だという立場からすれば、コミュニケートする内容をつくるという意味では全く何もやってないということと同じことなんです。」
「科学的に結論が出ていなくても、何らかのことを言っていただかなければならない。判断をしていただかなければならないのです。その判断はすべて予測であります。これは実証ではないです。実証ではないことは科学ではないと思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思いますが、この場合のコミュニケートというものがもしこの世の中で必要であって、それがなかったら、一般の人が明日の行動がとれないということであれば、それは科学者が結論を出すべき予測的な結論なんです。」
内山充さんには、随分お世話になった。私がリスク評価の勉強を始めた時に、内山さんが集めていた貴重な論文の綴りを貸してもらった。その論文には、ご自分の印鑑が捺してあった。その綴りには当時のリスク研究の論争部分に関するエッセンスの論文が入っていて、私は勉強を始めたその時点で、世界で何が議論されているかという核心を知ることができた。今も、そのコピーはあるのだが、私の宝物である。
雑感326-2005.12.5「光化学スモッグはなぜ増えたのか?−排出量削減は進んでいるのに−」
中西は、今、米国Washington DCに向けて移動中です。「工業生産されたナノ材料の安全性に関するOECDワークショップ」に出席のためです。今回は、中西が不在なのと、光化学オキシダント問題に関する検討会報告(東京都)が大気環境学会誌に掲載され、私の所属する研究センターのチーム長の吉門洋さんが、その検討会の委員だったこともあって、吉門さんに書いて頂きました。
今、VOCs(揮発性有機化合物)の排出削減が進められていますが、その根拠がオキシダント濃度増大です。しかし、どうも、VOCsとオキシダントとの関係がはっきりしない、いや、排出量が減っているのに、オキシダントが増えているという状況が腑に落ちないのです。今回の検討会の報告は、それに対して現時点で分かることを示していて、興味深いです。帰国は11日になりますので、次回更新は、12月20日(火)になります。(中西)
光化学スモッグはなぜ増えたのか?
---排出量削減は進んでいるのに---
吉門 洋(化学物質リスク管理研究センター・大気圏環境評価チーム長)
光化学オキシダント問題に関する東京都検討会の報告
1980年代に解決したかのように考えられていた光化学オキシダントの被害が近年また目立つようになり、再び問題となっている。改めて研究に取りかかるのもおかしな話で、さっさと対策をとるべきだと考えられる向きもあろう。行政も手をこまねいているわけではなく、大気中でのオキシダント(以下、光化学は略す)生成の一要素であるVOC(多種類の揮発性有機化合物)の排出削減をさらに促進するよう、力を入れている。
ところが、実際のところは、どれだけVOCの排出を減らせば被害が減るのか、よくわかっていないのである。それどころか、なぜ近年また被害が増えたのかもはっきりしない。1990年代にもVOCの排出対策が進められたし、VOCと同時に存在してオキシダント生成の原因となるNOx(窒素酸化物)の排出も減っているからである。NOxの主要排出源である自動車の台数は増えても、それを上回る排ガス対策により、NOx総排出量が減ったことは確からしい。それにもかかわらずオキシダントが増えたことについて、いろいろな要因が可能性として指摘され、それらが複合的に関与しているのであろう、とは言われていたが、はっきりしなかった。
この2月(2005年)、東京都が設置した検討会がその原因の究明を行い、今後のオキシダント改善施策の方向を示した報告書を提出した。その解説が大気環境学会誌11月号に掲載された。行政によって設置される検討会は往々にして「結論先にありき」で、そのつじつま合わせの作文をすることを仕事にしている場合もあるが、このオキシダント対策検討会は結論を急がず、原因解明に本腰を入れて取り組んだことは確かで、報告書もその謎解きが中心になっている。
オキシダントが漸増---気象要因がなくとも上昇
報告書解説の最初に載っているグラフ(図1)が、東京都のNOxやVOC(測定方式から、ここでは非メタン炭化水素NMHCで表現されている)の大気中濃度が近年、現実に低下してきている一方、オキシダントがじりじりと盛り返している事実を示す。しかし、オキシダント被害は必ずしもこの平均濃度の上昇に比例して増えるわけではない。図2には年々の被害状況が示されていて、一年ごとの変動が激しいことがわかる。これは、春から夏にかけての日射が強い日にオキシダントが高濃度になりやすいため、猛暑・冷夏とか梅雨の活動状況など、年々のこの季節の天候が大きく影響するためである。しかも近年は気候変動が身近に感じられ、梅雨期も高温少雨の年が多い傾向にある。このことだけによってもオキシダント被害は増加し得る。
そこで検討会は、オキシダント濃度と、それに大きく影響する気象要素である日射量や風速との関係を年ごとに求め、同じ気象条件を仮定した場合のオキシダント濃度がどう変化してきたかを算定した。もしオキシダント濃度がやはり年々上昇していれば、それは気象以外の要因によることになる。(実はここに若干の論理ギャップがあるが、ここでは重大視しないことにする。)この結果、気象要因を除外しても、地域内オキシダント平均濃度は統計的に有意な経年的上昇傾向にあることが確認された。
では、何が原因?
では何がオキシダント高濃度化に重要な役割を果たしているのか。最も注目すべきはやはりオキシダント生成の原因となるNOxとNMHCの濃度であろう。これらは最近ともに低下傾向にあるとはいえ、実際にオキシダントの高濃度が発生した日の朝のこれらの濃度はどうだったのか。この点を、気象条件が一定の範囲の日に限って調べてみると、やはり双方とも濃度が高い日ほどオキシダント高濃度の発生率も高い傾向があったのと同時に、濃度比NMHC/NOxがある程度高い一定の水準にある場合(つまり、NOxが低い、またはNMHCが高い場合)にオキシダント高濃度の発生率が最も高くなることも確認された。つまり、NOx濃度を低下させても、合わせてNMHC(VOCと言ってもよい)の濃度を低下させないとオキシダント生成がかえって増加する、ということが起こり得るのである。実際、この濃度比は過去順調に低下してきたのが、最近は再び上昇傾向にあり、そのことがオキシダント問題再燃の一要因とも言える。
今後の予測---両方減らせば一番いいが、NOxだけ減らすとかえってオキシダントは増える
従って、朝のNOxおよびNMHC濃度と午後のオキシダント高濃度発生率の関係に関する近年の統計データに基づき、今後のオキシダント対策として、NOxおよびNMHCの排出をそれぞれどの程度削減すればどの程度改善が進むかを見積もることとなった。算定の結果、例えばNOx濃度を20%、NMHC濃度を30%低下させれば、注意報レベル(120ppb)以上のオキシダントの発生日数は現状の半分以下になるが、NOxをもっと減らすとそれに応じてNMHCも大幅に減らすことが必要になる。この解析結果は、最初に述べた現在のVOC排出削減施策のねらいに一致する。
CRMの研究
都の検討会による対策効果の見積りは、現況モニタリングデータを基礎とした統計的な推測であり、十分な確からしさを備えているとはいえ、光化学汚染のメカニズムを踏まえた予測ではない。産総研の化学物質リスク管理研究センターでは気象・拡散・化学反応モデルを用いて空間分布も含めた長期的な汚染レベルの数値予測を行えるシステムを構築し、オゾンやアルデヒド類など二次生成有害化学物質のリスク評価に活用する計画を進めている。
なお、都の検討会で検討されたオキシダント濃度と原因物質の関係はあくまでも関東平野の領域内で起きるローカルな排出と生成に限られているが、現実には北半球の広い範囲でこれらの濃度上昇傾向が知られている。また、最後に検討会報告書の結論からそれるが、上記の見積りは気象条件が変化しないと仮定した結果であり、もし気候変動によって春から夏の天候が大きく変化していくようなことがあれば、排出削減の実効性をうち消すような効果が起きる可能性もあることを指摘しておきたい。
トップページに戻る