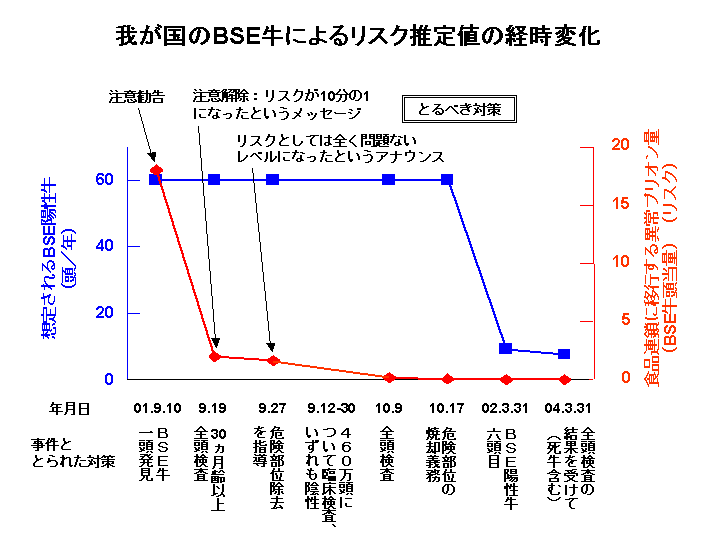雑感280-2004.11.4「リスクコミュニケーション」
内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム
−リスクコミュニケーション-
第6セッション「リスクコミュニケーション」
先週、読者の方からのご質問に答えるかたちでアナウンスしたが、環境省主催「第7回 内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」(12月15〜17日、於:名古屋)に、私は専門家向けセッション、第6セッション「リスクコミュニケーション」で座長を務めることになった。
私は、リスクコミュニケーションという言葉や、テーマが好きでない。したがって、このテーマの会議やシンポジウムには基本的に出席しない方針できた。しかし、その方針に反するにも拘わらず、今回は出席することにした(その理由は末尾)。
よくある、三つの場面
リスクコミュニケーションは、主に三つの場面で語られるような気がする。
第一は、企業が、自分のところは危険なものは出していないと説明する場面。
第二は、学者が、リスクコミュニケーションはこうすべきだ、というような報告の場面。
第三は、NGOや報道機関が、予見できたリスクが知らされなかった、または、それに対する対策がとられなかったとして、行政や関係した学者の責任を問う場面。
<企業による説明の場面>
第一のことに関しては、「リスクがあります」というリスクコミュニケーションの話がなく、いつも「リスクがありません」という話なので、どう考えても真剣に聞く気がしない。やはり、リスクコミュニケーションの基本は、リスクありの情報を出すことだと思うのだけれども。Aはリスクがある、Bは小さいというなら分かるが、いつも「リスクありません」では、リスクコミュニケーションとは言えないのではないかと思う。
<学者のリスクコミュニケーション研究>
学者の話はたびたび聞いた。しかし、私が聞く範囲では、米国などではこうしてるという手順の話が多く、リスクコミュニケーションという非常に難しい問題に“自分が”取り組むという切実さがない。一度でもいい、自分で市民の中に入って、リスクについて説明した、それはどうだったという話を聞きたいものだと思う。
遺伝子組み換えの場合でも、学者は常に第三者で、自分は全く傷つかない立場で議論している。例外は、原子力を扱っている学者のみという感じがする。原子力の場合は、学者が企業と同じような立場になっているきらいがある。
<NPOや報道や評論家の話>
従来の責任を問う反動で、何でもリスクあり、明日にも地球が壊れ人類が滅ぶというような話がほとんどになる。
リスクコミュニケーションで最も大切だと私が考えること
リスクコミュニケーションを考える場合に最も大切なことは、「リスクあり」の情報をどのように伝えるか、そのとき起きるかも知れない反応(パニック)や経済的な被害の責任を誰がどのようにとるかということを、皆できちんと考えて整理しておくことだと思う。
「リスクあり」の情報を予め出さなかった、あるいは対策をとらなかったという批判が、たびたび過去の事件について出される。確かに、それは問題だが、その問題も、「リスクあり」情報が出たときの経済的な損失の問題をどうすべきかということにふれないとすれば、単に、過去のことだから言える批判にとどまり、将来の対策につながらない。
もし、「リスクあり」の情報伝達に成功すれば、「リスクなし」の情報もまた、適切に伝わるのである。リスクありの情報を伝達した場合に、起きる反応を怖れると「リスクあり」の時には黙ることになる。そういう人や企業が「リスクなし」の発言をしても、誰も耳を傾けない。「リスクなし」を伝える人は、「リスクあり」も伝える人でなければならない。「リスクなし」を予測する同じ科学と方法論で「リスクあり」も予測されなければならないのである。
どういうことが起きるか、問題を表に示す。
| リスク評価の状況 |
伝達されたリスクの大きさ |
リスク情報で引き起こされる問題 |
とるべき措置(中西の考え) |
| (1) 嘘のリスク |
過大 |
経済的な損害 |
損害賠償すべき |
| 過小 |
人に被害 |
損害賠償すべき
(本当に償えるかの問題が残る) |
| (2) リスク評価の間違い |
過大 |
明らかな経済的な損害 |
補償すべき、または、責任をとる |
| 風評被害 |
補償しない |
| 過小 |
人に被害 |
補償すべき、または、責任をとる |
| (3) 適切な評価 |
A. 実態にあったリスク評価 |
経済的な損害 |
補償しない |
| B. 情報が少ないために過大に評価された(*) |
経済的な損害 |
補償しない |
| C. リスク不安 |
風評被害。経済的な損害 |
補償しない |
根拠もなく大げさに言うことは論外
表で(1)の第一段目に書いた「過大なリスク」は、ダイオキシンや環境ホルモンで「危ない」「危ない」と言って世論を煽った場合である。
(1)の二番目に書いた「過小なリスク」は、かつての公害問題で、企業や行政、多くの学者達がとった態度である。
こういうことがあってはならないことは論をまたず、損害賠償はすべきだし、責任も問われるべきである。この問題はこれ以上ここでは論じない。
難しいのは、(2)と(3)、特に(3)である
誠実にリスク予測をしたと思っていても、以下の二つのことは起こりうる。
リスク評価が間違いであった場合
<(2)について>
リスクは予測だから、精一杯予測しても間違うことはある。過大な方向に間違えば経済的な損失を引き起こし、過小予測になれば、例えば人的被害を引き起こすことになる。間違うことを怖れると、何も発信しないことになる。或いは、その人の所属セクターの思想傾向や利害を反映し、何でも「リスクあり」か、何でも「リスクなし」になる。
リスク情報を発信し、間違った場合に起きた損失は、どうすべきか?
このリスク情報の発信主体が行政なら(カイワレ事件とか、AIDSみたいに)、明らかな損害に対しては行政は補償しなければならないと私は思う。そして、社会全体がその間違いを、次のリスク評価に生かすようにしなければならないと思う。つまり、ただ、損害賠償するだけでなく、次回はリスク評価を間違えないようにする、そういう科学とか方法論を発展させるべきだと思う。
では、報道機関なら?これも、責任と結果がはっきりしているなら、補償すべきだと思う(テレ朝事件:テレ朝が間違いか、意図的なものかはここでは論じない)。
研究者はどうするか?行政の場合とは程度が違うとしても、何らかの責任はとるべきだ。謝罪、研究費申請の辞退、大学教授を辞めるとか、そういうことはすべきだ。
では、情報発信しない方が得ではないかと思われるかもしれないが、情報発信しないことは、間違った情報発信と同じである。
リスクを過大に評価してしまった時に、損害賠償すべきだと言ったが、表に書いた通り、風評被害的なものに対しては、損害賠償はしない方がいい。社会全体で、如何に風評被害をなくすべきかというレッスンをすべきだと思う。
リスク評価は適切だったが、経済的な損失が出た<(3)について>
この場合、リスク不安で私が書いたことが当てはまる。(雑感242-2004.1.13 ここをクリック)
A. 真のリスク(実は、この表現はよくない、何が真であるかは、そう簡単にはわからないから。しかし、一応しばらくして分かるとしよう)、
B. 当初情報が少ないために大きめに予測しなければならないリスク、
C. 過剰な反応
の三つとその影響を考えなくてならない。
この場合、リスクを過小に評価して実害を引き起こさないことを目標に評価しているので、Bのようなことが起きる。ただし、過小評価のための被害は防ぐことが出来る。
これらの場合、表に書いた通り、私は「損害賠償の責任なし」とした。ここが、重要だと思う。これが、保証されない限り、どうしても「リスクあり」情報は世に出ない。世に出ない状況下で、リスクコミュニケーションの技術論を論じていても無駄だというのが私の考えなのである。
(3)の問題の説明を補足すると
その時点で情報が少ないために、リスクが大きいと言わなければならないし、それを前提にしたリスク回避策をとらねばならないという問題は、リスク伝達、リスク管理で避けることのできない問題である。
そして、この初期にとられる措置は、多くの場合、後で考えれば過剰対策である。それは、間違うならば、「リスクなし」と言って人的被害を出すより、「リスクあり」と言って経済的損害を出す方が良いと考えてリスク管理を行うからである。
限度はあるが、一定の経済的損失を覚悟で、リスク評価の結果を出さねばならない。さらに複雑なのは、この時に、より過剰な反応が起きることである。
用心のために過大にリスクを評価しなければならない、そのための経済的損失を覚悟しなければならないということの他に、いわゆる風評被害的なことが起きる。それを怖れると、どうしてもリスク情報が出ないことになり、それが、次々と悪循環を起こす。
BSEの例で説明しよう
これを、我が国で1頭目のBSE牛が発見された場合に遡って考えてみよう。
図には、それぞれの時点でどの程度のリスク(ここでは人へのリスクではなく、食品連鎖に入る異常プリオン量になっているが、人へのリスクはこの値に比例する)と推定されたかを、グラフに示した。
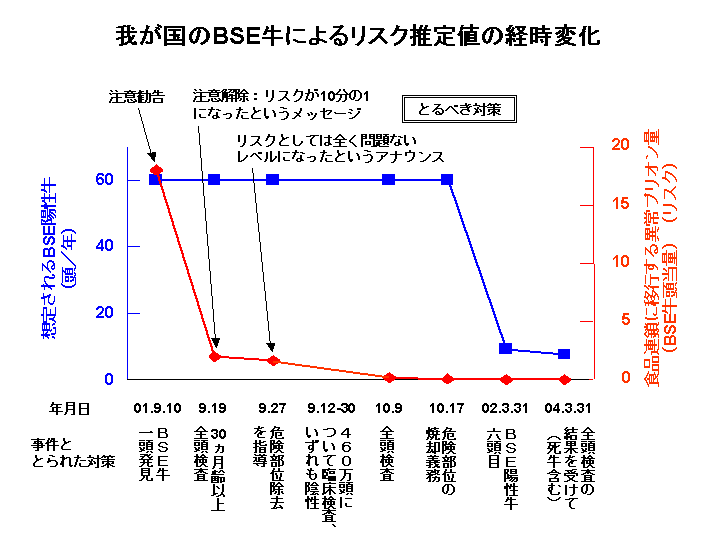
青いグラフは、その時点で得られる情報で推定した年間屠殺される牛の中でのBSE牛の頭数(95%信頼上限値)である。BSE牛の頭数は、今では100万頭中3頭程度であることが分かっている。その数字は01年9月でも同じだが、情報がないから、60頭位という推定をしなければならない。
赤いグラフは、それぞれの時点で、食品連鎖に入ってくる異常プリオンの量の推定値である。青が一定値でも、赤が9月中旬に極端に下がるのは、30ヶ月齢以上の全頭検査と危険部位の除去による。
危険部位の除去が進んだので、全頭検査の意味はなくなっている。グラフの上に、そのリスクの推定値の時に、とるべき対策を書いた(食品連鎖に入った異常プリオン量と人のリスクとの関係は、拙著「環境リスク学」187頁参照)。
01年9月10日、つまり、発見の日に出すべきは、「注意勧告」(内臓を食べるのはやめよう!)である。安全宣言ではない。
01年9月19日は、「注意解除」を出すことができる。リスクが1/10に減ったというアナウンスが必要である。
さらに、01年9月27日で「安全宣言」である。
難しい9.10
大事なことは、何故リスクが小さくなったのか、小さく推定出来るようになったかを知らせ、その都度とるべき対策を変えることである。そして、市民にリスクとは何かを知ってもらう必要がある。
ここで、難しいのは、9月10日である。ここでは、利用部位によっては、リスクはやはり問題かもしれぬという数値が出る。そこで、そのことを発表しなければならない。当然、食肉にも不買行動が起きるので、経済的な損害が出る。後で考えると、必要なかった措置である。しかし、その時点で得られる情報だけで判断すれば、注意が必要なのである。これを伝えなければ、リスクコミュニケーションではなくなってしまう。
ただし、相当大きな経済的な損害が出る。これを避けようとすれば嘘(「安全宣言」)を言うことになる。そこで安全宣言をすると、信用を失う。信用を失った人が、つぎに安全だから「全頭検査を止めます」と言っても駄目である。
もちろん、最初の「注意勧告」が、冷静に受け止められるべく行政官は努力するのであるが(報道機関も協力すべきだが)、パニックも起き、必要以上の経済的損害も起こりうる。それも、含めてやむを得ない。ただ、それが長く続かないようにすることは、適宜情報を出すことで避けられる。
リスク発信に伴う問題をきちんと見据えよう!
リスク発信にはこういう問題がある。その起きるかもしれない損害を認めること、しかし、それが過度にならないように、また、長引かないようにすること。そういう努力をすることで、はじめて、正直なリスク発信ができるようになる。
適切にリスク評価をしても、その情報を出せばかなりの経済的な損失が出る。そういう場合に、どうするかを皆で考えておかなければ、リスクあり情報は出せないだろう。リスクあり情報が出せない状況で、リスクコミュニケーションを論じても意味がないと私は思うのである。
そこで
私が、リスクコミュニケーションについて最も関心のあることは上に書いたようなことだが、べつに、今度の国際シンポジウムでこのことを議論したいと思っているわけではない。むしろ、参加者のご意見をよく聞きたいと思っている。
今回、国際シンポジウムに参加することにした理由を一言だけ書いておきたい(多くの方が聞きたがっているから)。
国際シンポシウムは今年で7回目ということだが、私は一度も出席したことがないし、関心もなかった。また、環境省と付き合うのも気が重いし、リスクコミュニケーションというテーマも好きでなかった。だから、いきなり環境省が話をしに来たら、当然断っていたと思う。環境省から、この依頼が私に来たのは、7月5日である。
ところが、それより2ヶ月も前から、「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」改訂ワーキンググループか、「内分泌攪乱化学物質検討会」かどちらかよくわからないが、公開の委員会で、リスクコミュニケーションのセッションを作り(これまでこういうセッションはなかった)、中西を座長にするという案が事務局から出されているという話が、傍聴者から伝わってきた。
私は何も知らなかった。皆は、私は承諾したものと思っていたという。「出ない」という話を聞くと、「是非出て」という。最後に、「環境省内部が変わろうとしている。その現れだから出てくれ。」と言ってきた人がいた。私はそれに賭けた。環境省は変わる!
○「環境リスク学」書評
書評(8) 10月26日、日経サイエンス12月号、評者森山和道さん。
書評(9と10) インターネットで非常にすごい書評に出会った。ここまで読みとるかなと、いささか驚いた。前者についてはリンクの許可を頂いたが、後者については連絡先が分からず、許可を頂いていない。しかし、これは本屋さんのHPで、全体として“リンク歓迎”とあったので、リンク了と解釈した。
書評(9) http://tftf-sawaki.cocolog-nifty.com/blog/2004/10/post_10.html
書評(10) http://www.bk1.co.jp/cgi-bin/srch/srch_rev.cgi/40480a73db4e70103aed?aid=&bibid=02478247&volno=0000&revid=0000377244
次回の更新は、11月16日(火)の予定です。
雑感279追記3と訂正-2004.10.28
10月26日 環境ホルモンのパンフレットが公開されたことは、既に読者の方からのご指摘でお知らせしました。
続いて、27日、今度は検討会の6回と7回の資料と議事録が公開されたとのご連絡を読者の方から頂きました(私はまだ見ていませんが)。
また、8回と9回は、会議そのものが開かれていないそうです。私の早とちりです。
どうも、私は環境省の広報担当になってしまった。
雑感279追記-2004.10.26
追記2
えっ?どうして?中西さんが環境省の内分泌攪乱物質シンポジウムの座長をするの?
案内は以下のサイトです。専門家向けプログラムのところをご覧ください。
http://www.congre.co.jp/eed04/index.html
詳しくは、次週です。
追記1
環境省の環境ホルモンのパンフレットは以下で公開されているとのことです。読者の方からご連絡頂きました。
http://www.env.go.jp/chemi/end/speed98/pamph.pdf
会議資料は公開されていませんが。
雑感279-2004.10.26「ああ、やっぱり! じゅげむじゅげむの閾に達した、環境ホルモンのパンフレット」
SPEED’98のパンフレット(前回の案)
環境省が“環境ホルモン戦略計画 SPEED’98 取り組みの成果(パンフレット)”を出そうと準備している、その文案を事務局が策定し、その中に19物質の調査結果が表に掲載されていたことを雑感269(2004.08.02)(ここをクリック)で、書いた。
メダカのライフサイクル試験とラットの一世代試験の二つに分かれていた。メダカの試験では、ノニルフェノールと4-t-オクチルフェノールについて、「所見あり」となっていたが、その他の17物質について「所見なし」となっていた。また、ラットの一世代試験での結果では、19物質すべてについて、「所見なし」となっていた。
その際も書いたが、委員からは、何もなかったということになると困るということを背景にした意見が出ていたので、かなり変わるだろうと思っていたが、案の定、ひどく変わったものになるらしい。
変わり果てた姿:“明らかな内分泌攪乱作用とは言えないが、内分泌かく乱作用に関連する所見が認められた”って何?
それは、10月5日に開かれた円卓会議に資料として出されたという。
(以下、伝聞)
そこで、表1は変わり果てた姿になっていた。試験結果は12の分類に分かれているが、この違いが何を意味するかが、分からない(私には、何度説明を聞いても分からない)。
メダカの試験結果では、「所見は認められなかった」というのとは別に、「内分泌攪乱作用とは関連のない所見が認められた」という分類がある。また、「明らかな内分泌攪乱作用とは言えないが、内分泌かく乱作用に関連する所見が認められた」という分類もある。一番目と二番目の違いもよく分からないが、三番目はもっと分からない。まさに、じゅげむじゅげむの世界。
ラットの方はもっと分からない
「影響が既に認められている用量未満で有意な反応が認められたが、生理的変動の範囲内であると考えられた」とある。影響が認められている用量未満って何だろう?普通の人は、どのレベルが影響の認められている用量かわからない、しかも、その用量未満と言う、これは何だろう?
用量未満で反応があるというのは、つまり、従来の研究結果でいわれていた閾値がより低い値だということが分かったということか、とも思うが、ここでは「影響」ではなく「反応」となっている。とすれば、影響とは別の反応が出たということか?そして、最後に、生理的変動の範囲内と言っている。これが、影響なの?これが、反応なの?
用量未満云々というが、それは、気をつけるべき用量なのか、それとも、通常はありえない用量なのか?もし、そのことを国民にどうしても伝えたいならば、数字を示してもらった方がいい。用量未満って、全く分からない。
ラットの一世代試験結果のまとめでは、“「環境中濃度を考慮して試験をしたところ」、環境中濃度より高い用量で精巣などになんらの「現象」が見られるが、「ラットの一世代試験では」「内分泌かく乱作用は」確認できない”と書かれている。ここも影響ではなく、「現象」となっている。この意味は何だろう?
この部分は、当初の事務局文書では、「19物質について環境中濃度を考慮した濃度レベルで試験を実施したところ、いずれの物質でもラットの1世代試験で見る限り明らかな内分泌かく乱作用は確認されていません」となっていたのである。
変更の意図は見え見え
変更の意図は見え見えである。この研究をしてきた、或いは、多額の研究費を使い、何もなかったでは困るという関係研究者の保身のためだろう。しかし、このパンフレットは、リスクコミュニケーションのための「円卓会議」で出されていることに注意してほしい。円卓会議では、国民に如何にリスクについて知ってもらうかを議論している。こういうことをしないことが、リスクコミュニケーションの第一歩ではないのか?
一体、誰がこういう案を出したのか、誰が検討会で発言しているのか知りたいと思い、「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」改訂ワーキンググループの議事録と資料をインターネットで探したが、第5回(今年の6月)までの資料は、すべて公表されているが(議事録は4回まで)、第6回、7回、8回、9回の資料と議事録は一切見ることができない。つまり、私が8月2日の雑感で、この問題について書いて以後の会議資料はインターネットで見ることができない。
雑感278-2004.10.19「ナノテクノロジーとリスク」
ナノテクノロジーが脚光を浴びている。その一方で、ナノによるリスクについても、問題が提起されている。新しい技術が世に出て行く時、同時に一定のリスク評価が行われることが大切だと思う。先日、産総研が音頭をとって開いている「ナノと社会研究会」で私見を述べた。その一部を、今回は書いてみたい。
ナノテクノロジーとは?
ナノメーター(nm)は、10億分の1m。1〜100 nmの範囲の微小粒子を活用した技術を、ナノテクノロジー(ナノテク)という。水素原子は0.1nm程度の大きさで、アミノ酸などになると1nmに近くなるものもある。ディーゼル排ガス粒子は、100nm程度の大きさと言われている。 |
ナノのリスク評価のための基礎知識(中西のプレゼンテーション)
こういうタイトルで25分ほど話した。
1.二つの異種のリスクに真剣に取り組み、その扱いを間違えないこと
二つの異種のリスクとは、微粒子という特性に由来する実態的なリスクと、ナノテクが切りひらく新しい医療分野におけるリスク問題、特に倫理に関連したリスクである。
1)微粒子であるが故のリスク
これは、通常のリスク評価でいい。ただし、化学的特性ではなく、サイズが小さいという物理的特性が問題になるリスク評価という点では新しい点もあるので注意が必要。
2)ナノを使った医療にからむ行為に伴うリスク(或る場合には目的そのものがリスク)
倫理や差別問題が出やすく、扇情的な問題になりやすいので、リスク不安対策が重要。
ナノを使った医療行為には、以下のようなものがある。
DDS:ドラッグデリバリーシステム。ナノ粒子を、ある患部の細胞の特定部位と結合力のある部分で修飾し、さらに薬剤を入れて体内に送り込む。特定部位に届くと、そのナノ粒子を壊すことによって、効率的に患部に薬を届けることができるシステム。
再生医療:機能が失われた組織に、ナノに幹細胞を入れて送り込む。幹細胞が新しい組織細胞を作り出す。
ナノマイクロマシン:体内で手術などを行う。
この二種のリスクに対して考えるべきことを表にした。
表 ナノテクとリスク管理
| |
リスク |
リスク評価の留意点 |
どうするか? |
| 第一のリスク(微粒子としてのリスク) |
人の健康へのリスク |
暴露経路 環境(一般環境と労働環境)経由と商品経由(化粧品など)に注意が必要 |
●(研究計画で、または既往の研究結果の解釈で)ナノ粒子が問題か、ナノ粒子に付着している他の物質(重金属など)が問題かの見極めが必要
●どこが、大きな粒子と異なるか、どこが溶解性の物質と異なるかを冷静に見る
●自然の物質の中に、必ず類似の性質の物(ナノ粒子)があるので、それについてまずよく調べる |
| 生態リスク |
ほとんど問題にならない |
|
| 第二のリスク(医療的利用) |
リスク問題がでやすい応用分野 |
安全性検査 |
倫理的考慮 |
どうする? |
| DNAチップ製造 |
不要 |
不要(DNA読みとりの問題がなければ) |
●それぞれの物質や系の安全性検査、労働現場、環境リスクへの注意は当然必要(これは通常の商品の機能検査と変わらない)
●倫理問題には特別の配慮が必要 |
| 人工血球 |
製品として必要 |
不要 |
| 人工緑素 |
製品として必要 |
不要 |
| DDS |
系として必要 |
多分不要(モノクロナール抗体と同種の問題) |
| 再生医療 |
系として必要 |
あり |
| ナノマシン |
系として必要 |
あり |
リスク不安
新しいことは、リスク不安を大きくしがちである。実態的なリスクの大きさを調べることは当然必要なことであるが、何か摩訶不思議なことが起こるかもしれないということがリスク不安を大きくし、実態的なリスクの大きさではなく、リスク不安の方で行政的な措置が決まる傾向が、最近見られる。遺伝子組み換え食品などもその一つであろう。
リスク不安は、技術が新しい、内容がよく分からない、人の生命や能力の操作などの場合に大きくなる。ナノテクでこんなに素晴らしい事ができますという宣伝がしばしば聞かれるが、それが不安を大きくするという面もある。
多くの人が、持って生まれた能力を改造したいという願望を持っている。しかし、それができますとなると、人が生命の限界の中で生きてきた秩序が壊れるという恐怖が出てきて、それがリスクになり、また、リスク不安にもなる。リスク不安は、技術や化学物質に対する願望や信頼の裏返しという面もある。
環境ホルモンがあれだけ大きな不安を引き起こしたのは、性の転換があったからであろう。ダイオキシンも子どもの奇形という問題が大きい。免疫力の低下や、発がん率の増加では、あれだけの問題にならない。
化学物質の力を皆が“すごい”と思っているから、心配するような事が起きるのではないかと思うのである(現実にも、量を間違えれば忌避すべき問題が起きるのだし)。
化学物質や新しい技術が、そういう領域に踏み込む場合には、技術としても当然気を付けなければならないが、また、踏み込むかもしれないということで不安が大きくなることにも十分な注意が必要である。
特に、倫理的な配慮が必要である。(リスク不安については、雑感242 ここをクリック )
否定しても駄目
倫理にもとる様な事が行われるのではないか?という危惧に対しては、否定しても無駄である。ナノ技術を医療との関係で、夢の技術として喧伝したのは、K.エリック.ドレクスラー氏だと言われている。(以下は、榊 裕之著 全図解「ナノテクノロジ−」に書いてあることからの受け売り)。
ドレスクラー氏は、MITの学生の時に「創造する機械・ナノテクノロジー」というタイトルの本を著し、生体内を動き、結合を作り、結合を切ることができるナノアセンブラーで、生体内の改造が自由にできると書いた。
「人間の身体は分子で作られているのだから、健康促進に分子テクノロジーを活用できるはずである。病気、老化、怪我はすべてウイルスの侵入、時の経過、車による事故などが原因であっても、もとをただせば、原子の配列の乱れにいきつく。原子を再配列するデバイスが実現すれば、配列を乱した原子を正しい位置に戻すことができ、医療の根本的なブレイクスルーとなると期待される」と書いているそうである(上記書、61頁)。
これに対し、フラーレンC60(ナノカーボンの代表的物質、日本でも製造が始まった)を発見したR.E.スモーリー氏は、それはあり得ないと主張している。
スモーリー氏の言うことの方が本当かもしれない。ただ、こういう問題が持ち上がって来たとき、単に否定してもほとんど効果はないと思う。熱力学的に不可能ということを言っても、システムとして別のところからエネルギーを得ることは不可能ではないので、否定は難しい。まして、ドレクスラー氏の発想は、生体内で起きていることの模倣なので、全否定は難しいように思う。
こういう場合には、むしろ、最悪のシナリオを描き、それに対する対策を早く提示するのがいい。例えば、遺伝子組み換え体の実験の際に、P2〜P4などの区別をして管理したように、このような場合は、国の倫理委員会で議論するとか、こういう法律で監視するなどの社会的な枠組みを作ることが先決だと思う。
その上で第一のリスク研究に立ち向かう
その上で、第一のリスク問題に着実に取り組むことが大切である。もし、リスク不安という問題に真剣に取り組まないとすれば、いくら第一のリスクの問題がクリアされても無駄である。
第一のリスクに対して
先にも書いたが、必ず自然物、既存物にナノ粒子が存在する、そのことをまず調べることが重要である。そして、何が起きているかを知ることが肝要。
ディーゼル粒子の大きさも100nmくらいで、やや大きめのナノ粒子であるし、その健康被害はよく知られている。しかし、ディーゼル粒子を、ナノ粒子の代表のように扱うことはやめた方がいい。何故なら、ディーゼル粒子には不完全燃焼生成物が付着している可能性は高いからである。
不完全燃焼生成物は、古くからその有害性が知られている。煙突掃除人の病気もそうだし、吉田博士が最初に動物がんの発生を確かめたのも、タールであった。安易に、ディーゼル粒子をモデルにしてはいけない。
発ガン性物質に我々がどのように対処したか、内分泌攪乱物質に対してどのように対処したかをよく勉強すると、新しいリスクに対する対処法が見えてくる。ここでは詳しくは述べないが、やはり早めに、何らかの定量性を獲得することである。
発ガン性物質の場合には、最初は用量反応関係をすべて直線関係と仮定した。これは、リスクの過大評価ではあったが、それによって何が大きなリスクか、大き目に評価したとして、どの程度かの比較ができた。これが、大切。
他と比べることなくして、リスク問題に対処できない。用量反応関係の仮定が気に入らなくとも、仮定をおいてみて、早く、リスクの全体像が見えるようにすることである。危険だ危険だという人の頭になって、用量反応関係を作ってみる勇気が必要である。
もう一つ注意したいことがある。リスク評価を始める時に、ナノ技術に愛着があると、安全を証明したいという気持ちに駆られやすい。つまり、安全領域を求めることが研究の目的になりやすい。しかし、これは陥穽だと思った方がいい。
安全はないという気持ちで取り組むことが大切である。特に、ナノの場合はそうである。
何故なら、微粒子が害になるなら、すでに存在する微粒子にナノ粒子が加わるのだから、当然その和がどういう影響を与えるかということになる。つまり、excess
riskが問題になる。(これから加わる)ナノ粒子単独で、用量反応関係に閾値あり(つまり、安全領域あり)と言っても意味がない。
ここをわきまえないと、最初に「安全領域あり」で説明し、途中から、excess
riskがこの程度だから我慢してください、みたいな説明に変わらざるをえなくなる。それは、ほとんど受け入れられないだろう。
原子力やその他の技術が、この悲惨な道を歩んでいる。
最初に安全と言い、何かが起きると、この程度は起きるのだみたいな説明が出てくる。ある程度はリスクはあるという前提で、研究も説明も始めるのがいいと思う。
内分泌攪乱物質の場合は、自然界にその作用を持つ多くの物質があり、その比較が可能であった。個別物質の問題はあるとしても、少なくとも、女性ホルモンと同じ作用があるから危険という問題提起に対しては、ホルモン類似活性や、体内動態を調べ、自然の物質と比べることによって、どの程度の問題であるかを示すことができた。環境ホルモン問題が、あれだけ騒がれたにも関わらず、少なくとも熱病みたいなものが数年で収束していった背景には、こういうことがある。
ナノが出てくると、何かそういう医学の専門家、気管支炎、粉塵などによる呼吸器障害の専門家が出てくる。それでは駄目だと思う。BSE問題で、BSE研究者が問題を混乱させているように、彼らは役に立たない。発がん物質でどのように対処したか、内分泌攪乱物質でどのように対処したか、それを学ぶことが一番大切なことである。
●10月15日、水俣病関西訴訟団についての最高裁判決がでた。このことに関連して、拙著「環境リスク学−不安の海の羅針盤−」の116頁を読んでほしい。
●「環境リスク学」書評3:10月17日、日本経済新聞。
●「環境リスク学」書評(4〜7):Amazon (http://www.amazon.co.jp/)にアクセスし、和書、環境問題で検索するとtopに「環境リスク学」がでてきます。ここに、4人の方がreviewを書いてくれています。人様々な感想とtoneの違いが面白いです。
雑感追記-2004.10.13 「環境リスク学」書評
1.毎日新聞 10月10日 藤森照信氏評 「原理より地道な調査貫いた研究者」
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/dokusho/archive/news/2004/10/10/20041010ddm015070125000c.html
2.エコノミスト 10月19日号(12日発売) 松田裕之氏評 「ファクトと信念で発信し続けた環境リスクの実態」
雑感277-2004.10.12「ビルと風」
汐留のビルでヒートアイランド?
今年の夏、汐留のビル建設で東京はヒートアイランドみたいな話がひろがった。いくつかの専門家の会議でも話題になった。本当だろうか?
私の勤務する産総研化学物質リスク管理研究センター(AIST, CRM)の主任研究員で、大気圏環境評価チームのチーム長で、METI-LISの開発責任者でもある吉門洋さんに聞いてみた。どうも少し話が違う。
そこで、本当のところはどうかという文章を書いてもらった。
以下は、吉門さんの文章。
ビルが海風をストップ?
(吉門 洋)
風のある日でも、物陰にいると風が弱い。大きなビルが立ちはだかると、その陰になった場所では風通しが悪くなる。これは、特に科学的知識を動員しなくても、誰でも経験から想像できることである。
だからこの夏、新聞・TVが報じたこの話題は「なるほどね、やっぱりそうか」と反響を呼んだ。朝日(6月22日)の見出しを借りると、「海風、ビルが通せんぼ、東京・汐留再開発で1〜2度暑く」という話である。
ところが、私の周辺の気象や大気汚染の研究者は「そんなことは起こり得ないでしょう」と皆一様に首を傾げた。問題は報道の中に「海風」という用語が不用意に使われている点にある。
海岸に立ったとき、海の方から風が吹いていたら単純にそれを海風と呼ぶこともあるが、通常、海風という用語はそれの吹くメカニズムを意識した使い方がされる。
日射の強い季節の昼間は陸上の気温が大きく上昇し、陸上が低気圧になるため、相対的に涼しい海上の空気が陸上に吹き込む、それが海風である。だからこそ、真夏日が続く首都圏の大都市域に吹き込む海風はありがたい自然の恵みであり、実際、夏の東京の日最高気温が熊谷、前橋、甲府等よりむしろ低いのは海風のおかげである。
その海風が、壁のように並び立つビルにせき止められ、吹かなくなるという。この表現が誤解を生むのだ。
陸上の加熱が及ぶ大気層の高さは数百メートル、午後には1キロを超すこともある。陸上の低気圧の高さもそれに対応し、海風層の厚さもほぼそれに従う。
高さ200メートル程度のビルが、それも途切れ途切れに、いくつかの地区に集中して建っても、海風がそのためにストップすることはあり得ない。それどころか、海風はそのメカニズムから推測されるように、陸上が暑くなればなるほど強く吹く。都市のヒートアイランドが激化すれば、それは海風を強く引き込むように働く。
従って、「ビルが海風を通せんぼ」の実態は、あくまでも最初に書いたように「大きなビルが立ちはだかると、その陰では風通しが悪い」という事実に過ぎないのであり、その影響はビルの風下に当たるごく限られた地区にとどまることを銘記すべきだ。
報道記事を注意深く読めば、確かにそうとしか書かれていないのだが、海風がストップするかのような見出しは誤解を生むし、また誤解をあおるような報道もあった。例えばこういうタイトルの記事も出たらしい(見てないが)。
「湾岸高層ビルが東京を『熱地獄』にする」(週刊朝日8月23日号)
さて、ビルの物陰の限られた地区ではあっても、風がさえぎられて高温化するのが現実であるなら、むやみに高層ビルを建てることには慎重でなければならない。今後もどんどん高層ビルが建つのであれば、その物陰に当たる地区も「限られた地区」ではなくなっていく。
しかし、今のところ、汐留地区のビル群が都心部にそれほど広く影響を及ぼしているとは思えない。朝方の吹き始めの海風は海岸線に対して直角方向に入る性質があるので、港区付近では朝は東寄りの場合も少なくないが、午後に向けて強まるとともにほぼ大抵は南風に変わる。
汐留地区の真北3キロメートルに東京アメダス(気象庁)がある。これとその北西24キロメートルの浦和アメダス(さいたま市)のデータによって、1990年前後と2000年前後の各3年間の夏季の海風発生状況を調べた研究(吉門、大気環境学会誌、2004年7月)によると、東京の夏季の海風発達日数はこの10年間に約20%増加し、また、海風が東京から浦和まで進むのに要する時間が短縮した。
つまり海風が内陸に進入し易くなった。2000年前後といえば汐留の高層ビル群は未完成だったかも知れないが、ともかく10年程度の気候変動によって海風の吹き方はこれほど変わるということである。そこに都市構造の変化も影響を及ぼすであろうが、その結果を明確に把握するにはもう少し時間をかけて解析する必要があるだろう。
|
雑感276-2004.10.5「児童のぜん息」
環境省報告 児童のぜん息有症率と大気汚染関係なし
環境省が、児童の呼吸器症状有症率と大気中NO2(二酸化窒素)、NOx(窒素酸化物)、SO2(二酸化硫黄)、SPM(浮遊粒子状物質)の濃度との間に関係がないという報告書を出した。
かなり、大がかりな疫学調査である。その報告のまとめ(9頁)は、下記URLで見ることができる。
http://www.env.go.jp/chemi/survey/index.html
私もまだ、この要旨しか見ていないが、考えさせられる。
こういう結果を予測させる様々な事柄があり、しかし、やはり大気汚染だろうみたいな気持ちがあった。本当に、この結論でいいのか、ゆっくり検討したい。
今週は、異常に忙しく、書くことができないので、詳しくはまたの機会にしたい。
トップページに戻る