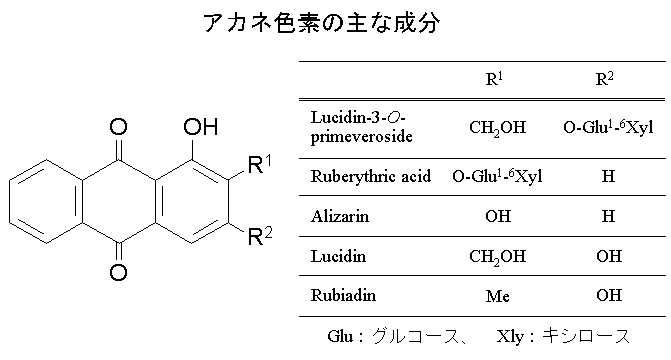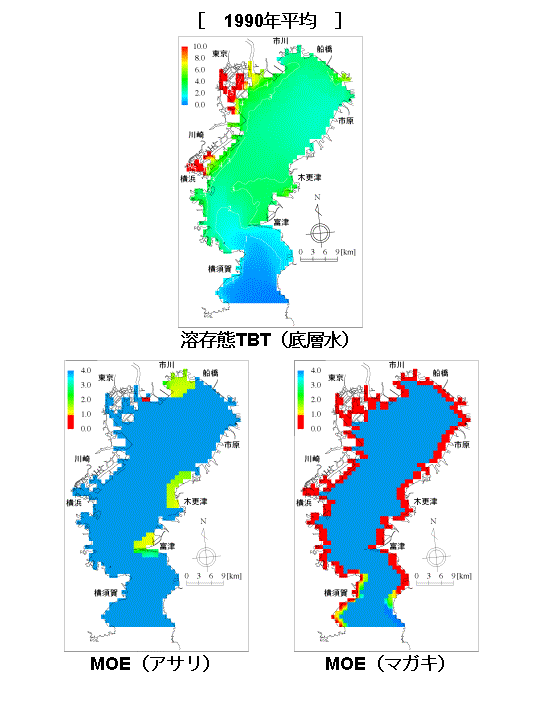雑感265追記-2004.7.7
思想(岩波書店)の 2004年7月号は、「リスクと社会」特集号です。
目次は以下の通りです。
思想 2004.7. No.963
リスクと社会
思想の言葉 天野明弘(2)
リスク社会という時代認識 長谷川公一(6)
リスク評価とリスクマネジメントのあり方-BSE事例の研究- 中西準子(16)
環境リスク管理と経済分析 岡敏弘(36)
国際環境法におけるリスクと予防原則 高村ゆかり(60)
リスク分析と社会-リスク評価・マネジメント・コミュニケーションの倫理学- 石原孝二(82)
環境リスクといかに向き合うか-水俣病事件に学ぶ- 吉田文和・吉田晴代(102)
生物多様性のリスク評価-外来種と絶滅危惧種- 鷲谷いづみ(122)
安全確保のための法システム-責任追及と学習、第三者機関の役割、国際的調和化- 城山英明(140)
社会のための企業リスクマネジメント-株主利益パラダイムへの挑戦- 水口剛(164)
産業における安全・健康リスクと自主対応参加型改善 川上剛・小木和孝(183)
|
雑感263の予告には「思想6号」とあり、7号の間違いでした。
雑感265-2004.7.5「アカネ色素禁止問題」
食品安全委員会
04年7月2日、食品安全委員会添加物専門委員会は「遺伝毒性および腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素についてADIを設定できない」という審議結果を出し、本委員会の食品安全委員会に報告された。
同日、食品安全委員会は、これを受けて審議し、その結果を厚生労働大臣に報告したとのことである。
ADIは許容一日摂取量の意味であるので、「ADIが設定できない」ということは、事実上禁止をいみする。
アカネ色素とは?
(http://www.fsc.go.jp/senmon/tenkabutu/t-dai10/index.html)を参照した。
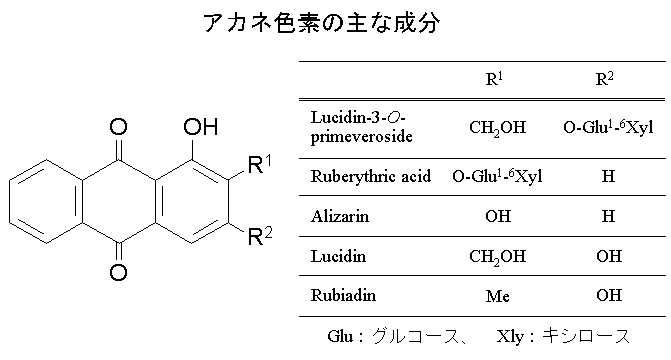
アカネ色素とは、西洋アカネという植物の根から得られ、アリザリン、ルベルトリン酸、ルシヂン-3-O-プリメヴェロシドなどを主成分とする赤色の色素で、ハム、ソーセージ、菓子、ジュースなどの着色剤に用いられている。
腎臓への影響があり、そのNOAELはこの報告書の記述では、食事中含量(混合物として)が0.2%となっている。この値を一日摂取量に直すと、約73 mg/kg/日になる。人のADIを求める際には不確実性係数を100にとることが多いので、その値を採用するとADI=0.7 mg/kg/日となる。そして、日本人の平均摂取量は0.002mg/kg/日以下であると書かれている。つまり、ADIの1000分の3である。
遺伝毒性
今回ADIが決められないとしたのは、「発がん性があり、遺伝毒性が認められる」となったからである。発がん性があっても、遺伝毒性がなければ閾値あり、つまり、許容量を決めることができるが、遺伝毒性があると、閾値がないので許容量を決めることができない、つまり、使用禁止という考えである。
発がん毒性
今回の報告によれば、発がん性の強さは、以下の通りである。
“ラットに前がん症状および尿管線がんなどが見られる。それが、用量反応的に増加する。”
この結果を表から読みとると、尿管線腫が約半数に見られるのは、雄で(雌の発症率は雄に比べかなり低い)ほぼ摂取量が1000mg/kg/日程度である。
Amesの論文から、自然物の半数発がん用量を調べると、以下のようなものがある。
ratに対する結果で、+は遺伝毒性試験で陽性、-は陰性の結果を示す。
| |
TD50 mg/kg/日 |
遺伝毒性試験 |
含まれている食品 |
| エチルアルコール |
9110 |
- |
お酒 |
| アフラトキシン |
0.003 |
+ |
かび → 穀類、肉、牛乳 |
| コーヒー酸 |
297 |
- |
各種野菜 |
| DDT |
84.7 |
- |
野菜、穀類、魚介類など |
| D.C. red No.5 |
415 |
+ |
米国の化粧品用着色料
(禁止された?) |
半数発がん用量(TD50)が1000mg/kg/日という値は、それほど発がん性が強いわけではないことを示している。
例えば、アルコールを我々は常時飲んでいるし、コーヒー酸が含まれる野菜や果実を健康にいいという理由で、かなりの量摂取している。
では、アカネ色素は少量しか摂取しないのに何故、駄目か?
リスクマネジメントの考え方
リスクマネジメントには、以下に示すような立場がある。
1)ひとつは、遺伝毒性あり(表に+)の場合、用量反応関係に閾値がない(どんなに少量でも、それなりのリスクはある)と考えられているので、
1-A) 少量でも、リスクが高いから、厳しい規制になる(一定のリスクは認める)
1-B) 少量でもリスクがあるから、禁止(リスクはゼロであるべき)
2)食品添加物の場合、リスクが小さいとはいえ、敢えて使わなくともいいので厳しい措置をとる(つまり、禁止してもマイナスが少なく、厳しい措置も合理的である)(リスクベネフィットの立場から)
つまり、遺伝毒性ありとなっても、三つの考え方のオプションがある。
| 考え方 |
項目 |
Action |
| 一定のリスクは受容 |
1-A |
例えば10-5とか10-6とか |
| リスクはゼロであるべき |
1-B |
禁止 |
| リスクベネフィットの考え |
2 |
効用を見て対策をとる。有害性が強く、添加物なら使用禁止もありうる |
厚生労働省は、食品添加物に対して1-Bの立場をとってきた。「発がん性があり、かつ遺伝毒性があればADIを決めることができない」という委員会の結論は、「リスクゼロでなければならない」という立場である。
つまり、発がん性試験の結果は、それほど強いものではないが、遺伝毒性があれば、リスクはゼロではないから駄目、という論理である。
では、常に、そのような立場をとってきたかというとそうではない。例えば、アフラトキシンは強発がん性で、動物のみならず人に対しても発がん性が証明されており、遺伝毒性ありだが、許容値を決めている。そうでなければ、ピーナッツとか、ピスタシオとかを食べることができない。
水道水に対しては、1-Aの立場をとってきた。そうしないと、水道水の消毒ができず、かえって大きなリスクを招いてしまうからである。しかし、後者のことは大きな声では言わず、表向きの発言では、常に、「リスクはゼロでなければならない」という立場をとってきた。
アカネ色素の場合
アカネ色素の場合は、2のリスクベネフィットの立場から、禁止にしてもいいとは思うが、他の色素のリスクとの比較は必要である。そして、そのためには、ADI以下ならリスクゼロという考えを捨てて、ADI以下でも一定のリスクがある、それを発がんリスクと比較するという立場をとらなければいけない。
その計算はおくとしても、このような時に、「リスクゼロでなければならない」ということを繰り返し強調すると、BSEのように極めて小さなリスクでも、社会が受容しないという事態が生ずる。
たった一つの物質の危険性管理にだけ目を向けると、「これは遺伝毒性があるからリスクゼロではない。したがって、駄目」という理屈は、それほど大きな問題を起こさないが、結局「リスクゼロ」を皆の頭に叩きこむことになり、必要な場合にもリスク受容が拒否されるという問題がでてきて、全体として大きな問題を引き起こす。
こういう場合も、リスクはいくらで、ベネフィットはいくらで、だから禁止という説明をすれば、皆の頭脳に、リスク管理の原則がいつのまにか入る。
今のような厚生労働省のその場かぎりの「安全論」的対応が、BSE問題のこじれや、ダイオキシン問題で、焼却炉が作れない、産廃処分場が作れないという問題をひきおこしていることに留意してほしい。
自然物のリスク
「安心!?食べ物情報」を出している渡辺宏さんが、「自然物にもリスクがある」ことを理解してもらう、いい機会になったと書いていたが、それは同感である。
来週、突発的なことがなければ、自然物のリスクについて書くつもり。
●ところで、毎日新聞で、こういうニュースがあったが、これ教育としていいことでしょうか?
千葉大学医学部の森千里教授(環境生命医学)らが、次世代の子どもに健全な環境を残すため環境ホルモンなどに関する正しい知識を身につけた“環境健康指導士”の養成講座を始める。
この講座の目玉となる「次世代環境健康メディア養成プロジェクト」では、胎児の環境を総合的に学び、そこで得た知識を一般の市民に正しく伝えてもらう役割を担う。主な受講対象者は教師や看護士、学生、マスコミ関係者らで、来年から本格的に始動する予定。問合せは千葉大学大学院・環境生命医学教室(043-226-2017)
雑感264-2004.6.21「-ダイオキシン テレ朝報道裁判和解-」
テレ朝 事実上敗訴
6月16日(2004年)、所沢市の農家が “ニュースステーション”(以下NS)のダイオキシン報道でテレビ朝日を訴えていた裁判で、両者が和解した。その当日と翌日、私はTVを見る時間が全くなかったので、TVでどのように報道されたのかは知らないのだが、ここでは新聞報道を基に私の考えを述べる。
和解の内容を繰り返す必要はないと思うが、(1)テレ朝の謝罪、(2)和解金である。
和解とは言え、テレ朝完全敗訴と言ってもいいだろう。私もこの和解条件は、妥当だったと思う。また、長い間つらい思いをしてきた原告(所沢の農家)にとっても、かなり満足のいく結果であったようで、そのことはとても嬉しく思う。
不思議な反応
高裁判決や最高裁判決の際、多くの識者が「社会を動かすためには、テレ朝報道のような報道も必要だった」という趣旨のことを言った。
この意見はどうしても理解できない。なぜなら、テレ朝の報道は、明らかに間違っているからである。意図的か否かは問わないとしても、間違いであったし、その間違いがパニックを引き起こしたことは誰も否定できないであろう。
間違った報道でも、ダイオキシンに世間の関心が集まり、それでダイオキシン特措法ができ、規制が厳しくなればいいという考えを開陳する人がいる。また、所沢周辺から産廃焼却炉がなくなり、空気がきれいになったからいいという人がいる。この論は恐るべきことだ。
これは、世論操作のために、嘘の情報を流していいということで、国民を愚民と見なす考えだと思う。たびたび例を出すが、英米軍を中心にしたイラク攻撃が、イラクの安定化と繁栄をもたらしたという評価になることもあり得ないわけではないが、それでも、大量破壊兵器の存在を理由に、イラク戦争を始めることは、大量破壊兵器がないのであれば、また、それが脅威でなかったのなら、許されないだろう。それと同じことである。
マスコミ関係者や学者が、このような考えを持っているなら、ある目的のために嘘の情報を流していい、つまり情報操作はいいことだと考えていることで、とても怖い。厳に慎むべきことの筈である。
今回も、泉徳治裁判官の意見が大きくとりあげられているが、これも同じ論調であり、報道関係者が、この意見にすがるような感じを持っているとすれば、大義があれば間違った報道でもいいと言っていることと同じではないだろうか?
びっくりのコメント
朝日新聞6月17日の朝刊にあった「違法性を認めたものではない。支払うのはあくまで和解金で、賠償金ではない」というコメントを読んで、かつての水俣病の時のやりとりを思い出し、びっくりしてしまった。確か、「補償金ではなく、見舞金」とチッソ㈱は主張し、見舞金契約ができたのだった。
自己規制招く畏れ
同じ17日の朝日新聞は、この訴訟が、報道側に自己規制を招くおそれがあるとして、大きな紙面を割いている。
自分にとっての「自己規制」問題?
自己規制とはなにか?自分の問題として考えてみた。
リスク評価結果を発信しようとする場合、ここで朝日新聞が言うのと同じか別かは分からぬが、「自己規制」が働くことがある。それには、二つの原因がある。一つは、もしかしてこの結果がまちがいではないかという心配(<間違いかも>)、もう一つは、このことが正しく伝わらず、大きなパニックをおこしたら困るという心配(<風評被害>)である。
<(その1)もしかして間違いかも>
研究結果を発表する際、100%正しいと確信できる場合は、それほど多くはない。もしかしたら、間違いがあるのではないかと思うことはしばしばであり、発表の前には相当心配する。また、結果には推論が入るから、それが間違いかもしれないという疑いは、常に残る。初歩的だが、計算間違いがあるかもしれないという心配もある。
実は「リスクをとる」気持ちがないと、いい研究もできないし、他人に先駆けて発表することもできない。もう少し確実にしてから発表しようという気持ちになることや、あいまいな書き方にしようという気持ちは常にある。これが第一の「自己規制」である。
しかし、一方で、報道も研究発表も、一番で得られる光栄と利得は大きいので、このことによって相殺するしかないと、私は思う。間違いとなったときには、それなりの「マイナス」を認め責任をとる。しかし、プラスはプラスとして評価し、マイナスを打ち消すことができるという考え方と制度である。
日本の場合、間違いもおおめに見られ、一番になっても、それほど評価されないことが多く、それこそ問題だと思っている。間違った発表(報道)で責任をとらされるから、発表(報道)をしない。だから、間違っても責任を問わないという議論は逆さまで、むしろいい報道、いい研究、特ダネにどう報いるかの議論をした方がいい。
しかし、研究などは、100年も後で考えれば、かつてのすべての研究は間違いともいえるので、“間違い”の定義も厳密に考えれば難しいことは、当然念頭におかなくてはならない。
したがって、科学報道の問題、不確実性の高い問題を報道する場合の責任の所在や、ありかたを巡る議論は必要である。ただ、NSのダイオキシン報道は、こういう議論の素材にならない。つまり、はっきりと今の時点で間違いと分かっているからである。
<(その2)風評被害が起きるかも>
しかし、リスクは1ですよと言っているのに、100とか1000とかに受け取られてしまう、または、関係ないものまでに買い控えがおきて、誰かに大きな損害をしまうというような場合もある(所謂「風評被害」)。
これが発表者の責任とされると、確かに「自己規制」を招き、発表しないということになりかねない。適切な発表をしても、過剰反応が起きることは、やむをえないので、その場合の対応について、報道関係者や研究者が一緒に考えるべきだと、私は思う。
間違った報道でなければ、それが不要な波及効果を起こしても、それは発表者の責任ではないが、被害がでた場合、誰が責任をとるのか、被害は補償されるのかという問題は残る。
社会全体で、このような過剰反応が起きないような努力や工夫を普段からしておくことが必要である。そのためには、この世には絶対安全はなく、常にリスクはある、リスクの大きさが大事で、その大きさの程度に応じて対策をとろうというメッセージを出し続けるしかないと思っている。
10月の最高裁判決
2003年10月、最高裁は「一般視聴者が放送全体から受ける印象などを総合的に考慮して判断すべきだ」という判決を出した。
繰り返し言うが、NS報道は事実が間違っており、事実は正しいが、一般視聴者が違う印象を受けて大きな被害を出したケースではない。
ただし、最高裁判決の文字だけが残ると、確かに、私が前項で書いたような「風評被害」が、発信者の責任となるケースであるという判決が出る畏れはある。そういうことも起こすかもしれぬ判決だということは認識しておく必要があると思う。
今のテレビ報道は、事実をきちんと調べもせず、ただ、焼却炉の煙突と同時にベトナムの障害児の写真を並べて見せるだけで、恰も関係あるかの如くして、恐怖感を煽るということを散々行ってきた。
最近は、学者もほとんど同じようなことをやっている。ダイオキシンが大変だというような本の内容の大半はこういうものである。
NSなども、まさにそれを狙った放送だったと思う。
こういう扇情的報道や研究発表に対して、内部から批判も反省も述べたことのない人が、「印象で判断されると自己規制が起きるおそれがある」と言う資格はないと思う。
扇情的な報道や研究(これが研究か?という疑問があるが、一応大学教授が出てきますから)が、多くの風評被害を引き起こしている現実を放置はできない。新聞などに登場する識者の多くが、こちらの被害については口を噤み、自己規制の畏れのみ言うのは、バランスを欠いている。
ダイオキシンの過剰報道は、権力との戦いだから許されるみたいな雰囲気があるが、これは、先に述べた情報操作もやむなしと同じだというだけでなく、当時のダイオキシン問題は、反権力でも何でもない。もともと、元厚生省と大手焼却炉メーカーが仕組んだものだったし、過剰報道で、権力から何の圧力も受けていない筈である。
自己規制は増えているか?
報道が、本当のリスクを報道しないケースは、確かに最近増えているように思う。その意味で、起きてはけない「自己規制」は現に起きている。かなり大きな実態のあるリスクについての報道がなくなっている。これは、大問題である。
ただ、それが直ぐに最高裁判決に影響されているかと言えば、そうではなく、報道内容の詰めが甘く、被害者からの訴訟(人権意識の高揚に支えられた)に耐えられないというだけのような気がする。
こういう状況を見ていると、やや飛躍するが、報道の発信者の層が変わるのではないかという印象を強く持つ。層が変わらなければ、新しい時代の要求には応えることが出来ないだろう。
今の、自己規制は、従来報道を担ってきた層が発信できなくなりつつあることを示しているにすぎないと思う。必ず、新しい層が出てくる。
それには、最高裁判決の「印象論」は必ずしも関係してはいない。しかし、最高裁の「印象論」判決は、かなり危ない面も含んだ判決であることは認識しておくべきだと思う。
やや苦みが残った
最初に書いたように、私は、今回の和解を好ましいものと受け取った。何よりも、農家の名誉回復が行われたことがいいし、補償金が払われたことも良かった。被害を受けた農家が泣き寝入りしなかったことも良かったと思う。
ただ、私個人には少し苦いものが残った。
4月末、私は所沢原告団(農家)とその周辺の方々から、裁判での証言を依頼された。
私は、はっきりと断った。理由は言わなかったが、半分は個人的な事情、半分は報道への裁判であるということに求められる慎重さからであった(農家が損害賠償を求めるのは当然であるが、第三者の私が、しかも書き手の一人である私が手を染めるには、相当の注意が必要)。
かなりきちんと断ったにも拘わらず、私の証人申請が行われたらしい。私には直接連絡はなく、第三者から連絡があった(原告団の意を受けてのことかもしれない)。
私は、その方に、呼び出しを受けても出廷する意思はない(それによる罰則は甘受する)ので、証人申請を取り下げて欲しいと伝えて欲しいと言った。にも拘わらず、私の証人申請は取り下げられず、結局最後まで残ったという噂である。正確にはどういうことだったかは、私には分かっていない。一切説明はないので。
4月末に原告団から頂いた手紙には、「正義のための裁判だからお願いします」と書いてあった。「正義」のために、私の事情と気持ちは無視されたのだと思う。ひどく残念である。
テレ朝を支持する多くのジャーナリストや知識人が、社会を動かすためには、このような報道も必要と主張した。大義のために、この程度の情報操作は許されるし、農家の犠牲があっても仕方ないという考え方である。どうも、大義とか正義とかは、個人を犠牲にするための言訳のようで、好きになれない。
来週、雑感の更新を休みます。次回は、7月6日です。
雑感263-2004.6.15「BSE 三ケースのリスク」
オーストラリア牛のリスクは?
BSE問題の決着は参議院選挙後であるというのが、もっぱらの噂だが、どう展開するのだろうか。興味深いことである。何故なら、このくらいリスクが小さいことをはっきり証明できる例は少なく、これを上手にハンドリングできないとすれば、相当おかしいと思えるからである。
私は、中央公論5月号で、米国で1頭のBSE感染牛が発見された状況下で、米国からの輸入牛肉によるリスクを、いくつかの条件下で算定し、「全頭検査」が必要になる場合と、そうでない場合とを明らかにした。そして、米国から、どういう状況かの説明を求め、それによって、「全頭検査」の必要性を判断すべきであると書いた。
米国については、状況によって判断が正しいが、国内牛の「全頭検査」は全く不要とした。
私の研究室の一人から、「オーストラリアでは、どのような検査が行われているのですかね?まだ、1頭も見つかっていないというのは、BSE1頭目が見つかる前の米国と同じではないですか?」聞かれ、「なるほど、その通り」とえらく感心してしまった。こういうことを、忘れがちである。
「思想」6号
6月25日に発売される「思想」04年6号に、再びBSEについて書いた。400字詰め60枚と表4枚の長い論文である。
この中で、私は三つのケースについて、リスクを計算し、その時にどういう判断ができたか、現実にはどういう判断が行われたかを書いた。
<第一ケース>米国でBSE牛の1頭目が発見された時(中央公論と同じ内容)
<第二ケース>日本でBSE牛の1頭目が発見された時(発見された日から、今に至るまで、その時の情報量でリスクはどう算定されたか)
<第三ケース>英国でBSEが見つかった時から、今に至るまでの英国の状況(この場合は、BSEがはじめて、また、変異型クロイツフェルトヤコブ病との関連も全く分からなかった状況の中で、リスクはどの程度と算定できたか、また、その際どうすべきだったか)
特に、この、<第三ケース>は面白いと思う。また、リスクマネジメントとは如何に難しいかも分かる。是非、読んで頂きたい。
中央公論
中央公論5月号に私は、「全頭検査で“安心”を買う愚かしさ」という小論を書いた。
多くの方から、手に入らない、読みたいという希望があり、中公論新社のご好意があり、ここに再録する。参議院選挙後、日本人の冷静な判断の一助になればの願いをこめて。
中央公論 2004年5月号 176-184頁
全頭検査で「安心」を買う愚かしさ ―BSE問題に冷静なリスク評価を
中西準子
今月のリスク
米国に「今月のリスク」という言葉があると聞いたことがある。このリスクで人類が滅びるというような大騒ぎをするが、翌月になるとまったく別の新しいリスクの話でもちきりになり、先月問題にしていたリスクはけろっと忘れてしまうような社会現象のことだという。
この言葉を聞いた時、いずこも同じ、しかし、日本ならさしずめ「今年のリスク」程度だからまだましなのだろうかと思った。ダイオキシンから、BSE(牛海綿状脳症)に移り、鶏インフルエンザとめまぐるしく「今年のリスク」は変化している。
BSE問題はもう終わったかと思っていたが、米国で感染牛が1頭見つかり、日本政府が米国からの牛肉輸入禁止に踏み切ったことから、牛肉の不足という新たな問題に直面することになった。
我が国は、全頭検査または全頭検査並みの安全度を米国に要求し、米国は全頭検査の要求は科学的ではないとつっぱねて膠着状態に陥っている。もちろん、米国の牛肉業者は、日本がいいお客さんであるところから、日本向けだけは全頭検査をしてでも貿易を再開したいと言っているので、全頭検査で輸入再開ということもあるかもしれない。
もしそのような展開を見せた場合、二つのいやなものが残る。一つは、米国民向けの牛肉は全頭検査されない状況下で、日本向けだけにはそれを要求するという、ある種“金満家”的要求のうしろめたさであり、二つは、リスクが小さくなっても、日本で全頭検査をやめることができず、無駄と知りつつ延々と続けることになるという予感である。
全頭検査については多くの国民が支持しているという世論調査の結果があり、また、米国牛に対しては、「米国の圧力に屈するな」というかなり屈折した主張もある。他方で、「全頭検査でもまだリスクはゼロではない」という主張や、「危険部位の除去の方が効果的」「費用がかかりすぎる」というものや、全頭検査は情緒的な判断であるから、もっと科学的に考えた方がいいという意見などが出されている。
このような様々な意見があるわりには、どういう対策をとれば、どのくらいのリスクが削減されるのかについて解析されたものがない。ここでは、どういう対策をとれば、どのくらいリスクが削減されるのかについて検討し、最後に、かかる費用との関係も考えたい。
いくつかの対策とリスク
BSE感染率そのものを下げることが根本的なリスク削減対策であり、そのために肉骨粉の使用禁止、飼料管理などが行われているが、ここではそれらの対策には触れることなく、一定率のBSE感染牛があるとしたときに、われわれの口に入るリスクを如何に下げるかの議論をする。
こういう場合のリスク削減の方法としてしばしば議論されているのは、危険部位除去と検査である。危険部位とは、BSEとそれが人に感染した変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJDと略す)の原因物質であるプリオンが集積している牛の器官で、脳、脊髄、脊根神経節、回腸などを指す。これらは、牛の解体時に除去できるが、解体方法と手間によって、プリオンの食肉への残留率が異なる。
全頭検査が行われれば、陽性と判定された牛はすべて棄却されるので、本来リスクゼロのはずだが、それでもリスクが残るのは、現在行われている脳の成分の検査では、感染初期段階では陰性と出ても、他の組織ではプリオンが存在することがあるからである。
感染しているが陰性と出る率を検査の見落とし率と呼ぶことにしよう。この小論の中では、見落とし率は1%と仮定した。頻度としてはもっと高いかもしれないが、見落とされる場合は、牛体中のプリオン量がかなり少ないのでこの比率を用いた。
つまり、リスクに関係するのは、1)牛肉の摂食量、2)牛のBSE感染率、3)危険部位除去後のプリオン残留率、4)検査の頻度、5)検査の見落とし率である。
米国の牛肉と日本人
米国では約1億頭の牛が飼養されており、毎年4000万頭程度が食用に回る。その40分の1の約100万頭が日本に輸入され、それらが日本人の牛肉消費量の約3分の1を賄うというのが、米国牛肉と日本人の食生活との関係である。いくつかの条件下でのリスクを計算し表に示した。リスクは、1年間に米国から輸入される牛肉全量に含まれるプリオン量がBSE牛何頭分に相当するかという値(BSE牛頭当量)で示した。
|
表 検査や危険部位除去後の残存リスクの大きさ
リスクは米国牛により日本に持ち込まれるプリオン量(BSE牛頭当量:BSE牛何頭のプリオンに相当するか)で表現した。日本に輸入されるプリオン量を10(BSE牛頭当量)未満にするという目標をもてば、グレーの部分では何らかの追加的対策が必要になる。(本文参照)
| 検査の程度 |
米国での年間BSE感染牛 |
危険部位除去後のプリオン残留率 |
| 1% |
5% |
10% |
100%(除去せず) |
| 無検査 |
400頭 |
0.1 |
0.5 |
1 |
10 |
| 4000頭 |
1 |
5 |
10 |
100 |
| 40000頭 |
10 |
50 |
100 |
1000 |
| 全頭検査 |
400頭 |
0.001 |
0.005 |
0.01 |
0.1 |
| 4000頭 |
0.01 |
0.05 |
0.1 |
1 |
| 40000頭 |
0.1 |
0.5 |
1 |
10 |
| 年40万頭(1%)の検査 |
400頭 |
0.09901 |
0.495 |
0.990 |
9.901 |
| 4000頭 |
0.9901 |
4.950 |
9.901 |
99.01 |
| 40000頭 |
9.901 |
49.50 |
99.01 |
990.1 |
この計算に用いられた仮定:
1)米国での牛の生産高は年4000万頭、そのうち1/40が日本に輸入される。
2)検査では、感染牛の1%は陰性と判定される。
3)米国でのBSE検査の結果では、累計57000頭が検査され、そのうち1頭がBSEと判定された。
これから、米国におけるBSE感染率の95%信頼上限値は10-4と算出され、それが年間4000頭に相当する。
4)何もしないときのプリオン残留量=Aとすれば、
無検査・危険部位除去後のプリオン残留量=A×α(α:危険部位残留率)、
全頭検査・危険部位除去後=A×α×β(β:検査の見落とし率=0.01)、
1%検査・危険部位除去後=A×α×(0.9901)
|
年間BSE感染牛の数という欄に、400、4000、4万と三つの区分を示した。危険部位除去後のプリオン残留率は、1%、5%、10%、100%の四ケースについて計算した。ここで、100%とは全く危険部位の除去を行わないことである。
「無検査」の欄で一番上の行には、年間感染牛400頭で、プリオン残留率が1%の場合、「0.1」頭当量という数字があるが、これは日本に輸出される1年間の牛肉量(100万頭)に0.1頭分のBSE牛のプリオン量が含まれることを示す。
二番目の「全頭検査」欄を見ていただくと、年間400頭感染、かつプリオン残留率1%の場合のプリオン量「0.001」頭当量になっていて、先の0.1頭当量に比べて100分の1である。すべての条件で、無検査に比べ全頭検査をすればプリオン量は100分の1になる。
この表だけ見ると、すごい、やはり全頭検査がいいと思われる読者もおられるに違いない。次から次と対策を加えれば、残存プリオン量はどんどん削減される。問題は、割合ではなく、それによって削減される量であり、残る量である。
例えば、先のケースで0.1頭当量を0.001頭当量に減らすことにどのくらい意味があるのかである。全頭検査でリスクが減ることは間違いがないが、われわれはどこまで減らすべきか、1頭分のプリオン量は大問題なのか、そこが議論すべきポイントである。
受容できるリスクレベル
どのくらいのプリオン量なら受容できるかを考えてみよう。米国牛を100年間食べ続けて、vCJDの発症が1人以下を目標にした場合、米国からのプリオン量が年間10頭当量程度ならいいということになる。これは、英国の例から計算された値である。10年間で1人以下という基準でいいとは思うが、これまでの経緯も考えて100年という基準をとってみた。
10頭当量未満を目標にすると、表のグレーの部分では、この値を超える。したがって、もし、米国牛がこのグレーの部分の条件であれば、たとえば年間4000頭以上が感染し、プリオン残留率が10%以上なら、プリオン10頭当量未満という条件は満足されない。
こういう場合に、全頭検査を組み込めばプリオン量は10頭当量以下になる。つまり、あるリスク目標があれば、ある場合は危険部位除去だけで目標を達成できるが、ある場合はさらに全頭検査を組み合わせることが必要になる。
ここまでは、リスク目標をvCJDの患者が100年で1人という目標をたてた場合であるが、目標が異なれば当然対策は異なる。この目標が妥当かは、そのリスク削減のための費用との兼ね合いでも検討されるべきである。
100年間の全頭検査の費用を2000億円とすれば(米国での検査単価は日本の半分)、1人弱の命を救うために2000億円かけることになり、目標が厳しすぎることになる。
年間10頭当量のプリオンまでは許容されるとしたが、他との釣り合いを考えれば、100~400頭当量でもいいのである。しかし、これまで、リスクはゼロだという方針できているので、一挙に変えるのも難しいだろうから、年間10頭当量以下を当面の目標にして、議論を進めよう。
米国に要求すべきこと
したがって、日本が米国に要求すべきは、米国ではBSE感染数が年間400、4000、4万のいずれのレベルにあるのか、また、危険部位除去はどこまでできるのかをはっきりさせることで、それが分かれば、とるべき対策は決まるのである。
ある場合は、全頭検査は不要で、ある場合は必要である。これまでの情報から米国の状況を推察するに、全頭検査は不要と思われるが、米国はそれを日本の消費者に分かるように説明する義務がある。
まず、米国での年間感染牛推定値であるが、累計57000頭を検査し、1頭が陽性であったというデータを用いると95%信頼上限値で年間感染牛約4000頭となる。感染牛年400頭の部類である可能性も大きいが、これまでの検査が少なくて、大きめに推定せざるを得ない。
米国は今後検査数を0.1%に増やすと言っているので、より確かな推定が可能となる。これに対して、0.1%の検査では少なすぎる、増やすべきという声がある。検査率1%にまで上げた場合、つまり検査数を年間約40万頭にした場合、どのくらいリスクが下がるのか計算して、表の3番目の欄に示した。
無検査で残存プリオン量が10頭当量の場合、1%検査での残存プリオン量は9.901頭当量で、ほとんど減少しない。つまり、検査率を上げてもリスクは削減されない。検査は対策のレベルを決めるために行うのであって、感染牛を見つけるためではないので、それによってリスクは下がらない。
わが国の牛のリスクレベル
では、わが国で生産される牛によるリスクはどのくらいであろうか?この2年半の間に検査されたのは約300万頭で陽性牛は10頭であった。100万分の3.3である。これは、表に表した米国の例に照合させると、年間感染牛130頭のレベルに相当する。このとき危険部位除去によるプリオン残留率が5%であるとすれば、その残存プリオン量は0.16頭当量となる。
さらに、全頭検査を加えるので、0.0016頭当量となる。今、先端技術としてもてはやされているナノテクノロジーの世界に迷い込んだのかと錯覚するくらい小さい。
BSE陽性率が100万分の3.3の場合、無検査・危険部位除去なしでも、100万頭(国産牛のおおよその年間生産高)に含まれるプリオン量は3.3頭当量になり、先に示した目標の10頭当量以下になる。理論的には、危険部位除去もやめてもいいのだが、少なくとも全頭検査はやめるべきである。米国の問題とは別に、すぐにでも決定できることである。
2002年度の欧州諸国での検査牛のBSE陽性率は、いずれも100万分の1の単位で、英国2738、ポルトガル1046、アイルランド471、スペイン247、イタリア50、ベルギー84、フランス75、オランダ43、ドイツ35であるが、いずれの国でも全頭検査は行われていない。
米国民は科学的か?
米国が日本より科学的か?と聞かれると、答えに窮する。冒頭に書いた「今月のリスク」のようにリスクパラノイア現象はしばしば見られるからである。国民レベルでは大きな違いがあるとは思われない。BSE問題ではたまたま、米国人が冷静というにすぎないと思う。
ただ、明らかに違うのは行政機関の姿勢である。米国の行政機関は、リスク削減対策により真摯に取り組んでいる。いや、取り組まざるを得ない状況にある。真摯とはなにかと言えば、リスクの大きさを明らかにし、削減対策の効果や効率を説明しつつ、対策を提示することである。
ところが、我が国の行政機関はこういうことを一切していない。BSEの場合も、リスクの大きさを説明しないし、その削減策の中からあるものを選ぶ理由や、費用が妥当かの説明がまったくない。
こういう態度でリスク問題に臨むと、本当に必要なリスク削減策に資源(資金や人手)を回すことができなくなってしまい、国民の健康や福祉のレベルが下がり、国力の低下につながる。また、説明力がないから、外国に対してリーダーシップをとることもできない。
今、リスク評価とそれに基づく対策立案と説明が非常に重要になってきているのは、以前に比べリスクが大きくなっているからではない。むしろ、小さなリスクに皆の関心が集まり始めているからである。
かつては、危険とは誰の目にも被害が分かることであったが、今、われわれがリスクとして扱っているものは、かつては見のがされてきたが、新しい分析技術や予測技術で推定される、確率的な事象である。
かつては、目に見える被害が問題になったので、被害の大小は割合わかりやすかった。優先順位は自明いうことも多かった。しかし、今は予測の世界なので、リスクの大きさがわかりにくい。だからこそ、リスク評価の科学が必要になってくるのである。
反面教師としてのダイオキシン
昨年、三重県の多度町でRDF(ごみ固形燃料)発電所の火災があり、消防士2名が死亡、作業員1名が重傷を負うという事故があった。その後の調査で、RDF処理・貯蔵施設は各地で事故とトラブルを起こしており、RDF発電所はエネルギー利用効率も低く、維持管理には異常な手間がかかり、かつ、危険きわまりない施設であることがわかった。
旧厚生省がRDF発電所を「ごみ処理の広域化を進める上で効率的な施設」として補助金をつけることにしたのは1993年だが、それが一挙に増えたのはダイオキシン対策特別措置法が制定された1999年以後である。まさにダイオキシン対策のためにRDF施設は普及したのだった。
ダイオキシンは危険という大キャンペーンの中で、焼却炉の排ガスに厳しい規制値が定められ、大型の焼却炉しか国の補助金をつけないという方針が出され、小さなところはRDFにして大きな焼却炉まで運ぶことが推奨され、それ以外の道がなかった。小規模焼却炉改善のための補助金は認められなくなったので、新しい排ガス規制をクリアできなければ、操業停止で町中にごみが氾濫するのは目に見えていたからである。
当初からRDF製造施設やRDF発電所に疑問をもつ者もいたが、ダイオキシンで子供に異常がでるとか、がんが多発などの大宣伝で、考えるいとまもなく、そちらに流された。旧厚生省の大規模焼却炉への横暴とも言える誘導が許されたのも、ダイオキシンが危ないというキャンペーンが功を奏したからであろう。
しかし、ごみ焼却炉のダイオキシン対策は、それほど急を要する問題でもなく、また、小型焼却炉でできないものでもない。焼却炉からのダイオキシン排出は削減されるべきだが、やや時間をかけて取り組んでも遅すぎることはなかった。
焼却炉から排出されたダイオキシンが直接近傍の人々の健康に影響を与えることはなく、ほとんどが長期間に排出され、水域にたまり、魚介類に蓄積し、それを食べることによって人の体に入るのであり、現在水域に蓄積しているダイオキシン類のかなりの部分が、1960年代や70年代に使われた農薬の不純物起源だからである。
ダイオキシンのリスクを過大評価し、また、主原因を見誤ったために、何兆円もの資金を使い、事故まで起こしている。国民はこの支払いをずっと続けることになろう。誰に責任があろうと、支払うのは国民である。
今、テレビのニュースは毎日のように、イラク戦争やテロについて報道している。大量破壊兵器もテロも脅威であり、リスクであるが、そのリスクの大きさを正確に捉えようとする努力を放棄し、過大に評価してもいいのだという雰囲気が強くなれば、たとえ世界第一の強国の米国でも苦境に陥ることになるのではなかろうか。ニュースを見るたびに、リスクの大きさをできるだけ正確に捉え、対処することの重要性を痛感する。
リスクの大きさ三種
リスクには3種の大きさがある。科学的に詰めて得られたリスクの大きさ(科学的評価リスク)、次が、社会の意思決定で用いられるリスクの大きさ(意思決定のためのリスク)で、考え方の違いやデータの不確実性を考慮して、科学的評価リスクよりやや大きめに評価されることが多い。第三がかなりの国民が抱く不安としてのリスクの大きさである。
不安としてのリスクの大きさは、第一や第二の大きさに比べて、かなり大きくなるのが普通である。BSEのように、新しい現象が現れると多くの人が不安に思い、不安としてのリスクの大きさはとてつもなく大きくなる。ある程度やむをえないことであるが、この差を縮める努力を怠って、不安としてのリスクの大きさをそのまま受容して、それを基に国の政策が決まるようになると、非常に無駄が大きくなる。
BSEのわが国での全頭検査はそのような政策決定である。意図的に不安を煽る行動が加わり、それを止める行動がとれないとすると、それはまさに亡国への道ではなかろうか。
リスクの大きさにはこの三種があることを考え、リスク不安と真摯に向き合い、しかも、できるだけ科学的評価に近い、意思決定のためのリスクの大きさを適切に選ぶことが、今後ますます重要になる。リスクとリスク不安を泳ぎ切る覚悟と科学的備えが、行政にも、学者にも、ジャーナリストにも市民にも必要なのだと思う。
これまでのBSE関連雑感:
雑感262の訂正-2004.6.9
雑感愛読者の方から、間違いのご指摘頂きました。Speed'98は、当初67物質から出発し、65になったが正しいです。
私は間違って、69から67と書いてしまいました。訂正します。ご指摘頂いた方から、67手怪獣(ムナジュカイジュウ)も「むなしい」に通じて、いいのではというご意見頂きました。物質数を間違ってすみません。文章はそのままにしておきます。
雑感262-2004.6.8「千手観音」
Speed'98 リスト廃止
2004年6月2日の朝日新聞によれば、環境省は98年に発表した「内分泌かくらん化学物質と疑われる物質リスト」を廃止するという。当初69物質だったが、現在は67物質となっている。ノニルフェノールとt-オクチルフェノールがメダカ等に一定の影響を与えるかしれぬ兆候があったが、ほ乳類への影響は見られなかった。
この6年に及ぶ期間と、莫大な調査費は、まさにリストを否定するためのものだった。
これについては、既に、雑感184に詳しく書いているので、ここでは繰り返さない。(雑感184へジャンプ)
余りにも愚かで恥ずかしいことだったので、以下に、寓話を書いてみた。まさに筆のすさびだけど。朝日新聞の記事によれば、環境省は1000近い物質から選んだ、新たなリストを作るという。こういうこと許されるのだろうか?
寓話 69手観音(ロクジュカンノン) 辞世のことば
69手怪獣(ロクジュカイジュウ)現る
私は、98年5月、69の毒手をもつ怪獣として皆の前に姿を現しました。69手怪獣(ロクジュカイジュウ)という呼び名です。
この69の手は、いずれも環境ホルモン作用の疑いがあり、生物や人類を破滅に導くものとして大々的に宣伝されたために、日本の人々は驚きおののき、大変な社会問題になりました。
この69手にはそれぞれ名前があり、「ノニルフェノール」「ビスフェノールA」とか「フタル酸ジ(2エチルヘキシル)」とかの名前がついていました。
地球防衛隊
それらは、ホルモンと似た働きをし、オスをメスに、メスをオスに変える機能を持つ、生態系の多くの生物の性比が変化しているが、これもこの怪獣のせいだと言われました。
また、人の男性の精子数が減少し、子供を作る能力が低下しつつある、また、子供の非行もこの怪獣が出す環境ホルモンのせいだし、子供がキレルのもそのせいだと、毎日のようにマスコミが報道しました。
そして、私を打ち倒すべく地球防衛隊が組織されました。“地球を守れ!打倒、怪獣!”のスローガンは、日本中に行き渡りました。地球防衛隊の中心は学者で、それに役所がお金を出し、マスコミが担ぎました。その宣伝力は大きく、日本の津々浦々まで地球防衛隊の支部が作られ、怪獣を追い出せといいう運動が組織されました。
しかし、私の姿はなかなか見えませんので、ついには、私の足跡をみつけて、足跡とその周辺をくまなく取り除く、怪獣足跡大清掃運動に発展し、さらに、もしかして怪獣が現れては大変ということから、怪獣が来そうな場所の木々をすべて伐採し、水面は全部埋めたて、子供の入るシェルターを作る予防作戦が展開されました。
私の力は万能で、すぐにでも地球を破壊するように言われましたが、実は、それほどでもないことを私は知っていました。しかし、大怪獣と思われることは、とても得なことですから、できるだけ姿を人目にさらさないように、夜そっと動くというようなことをしておりました。
もぎとられた二本の手
69手のうちのひとつは、「スチレン2量体、3量体」でした。これは、カップラーメンに入り、人間をやっつけるものと言われていました。このことを聞いた「ラーメン突撃隊」は怒り、執拗に私を追い回し、ついにある晩、戦いになり、「スチレン2量体、3量体」の手はもぎとられてしまいました。
その戦いに勝てなかったのは、その手には毒も何もなかったことと、「ラーメン突撃隊」が非常に強力な政治力で支えられていたことのためでした。そのとき、一緒に「n-ブチルベンゼン」の手ももぎとられてしまいました。それは、00年秋から冬にかけてのことです。
それ以後、私は「67手怪獣」になりました。
地球防衛隊の人々による、怪獣退治大作戦は、莫大な国の予算を使って進められました。そして、足跡を探すあらゆる調査や実験が進められたのですが、どうも被害もなければ、また、私の姿そのものを見つけることが出来なくなっていきました。
私は、ひたすら逃げ回っていたからです。ただ、怪獣は人前に出て闘ってこその存在です。私の手にはそれほどの毒も力もないことを私は知っていたので、もうこの地球に姿を現すことが出来なくなっていたのです。私は苦しみました。毒手をもってこその怪獣です。毒手のない私は何だろう?と。
WMD怪獣
最近になって、実は同じような怪獣が他にもいることを私は知りました。そして、それと比べれば、自分は罪が軽いかと思い、少しほっとしたのです。
それは、WMD怪獣です。WMDは、Weapons of Mass Destruction の略、つまり大量破壊兵器です。
WMD怪獣がいて大変だということで、ここでも、地球防衛隊が組織され、大量の軍隊がイラクに送られました。イラクには様々な問題はありますが、WMD怪獣は未だに見つかっていません。
これは私と同じ類の怪獣だと、直感でそう思いました。それは、WMDなど持っていないのです。普通の小さな怪獣だと思います。だから、皆の前にも姿を見せることができないのです。
それは、イラクで戦争をしたいと思っていた人々よってWMDを持っている怪獣にさせられたか、或いは、そのように見えてしまったか、どちらかではないでしょうか?いずれにしろ間違いで、そのために、とんでもないことが起きてしまっているのです。私には、イラクのことが手に取るように見えるのです。
怪獣ではなく観音
地球防衛隊は、近々「69手怪獣は、大した毒をもたない力のない怪獣だった」と発表し、隊を解散するようです。私も、静かに死を迎えることになります。残念ではありますが、もともと、実態のないものだったのですから、仕方がありません。
地球を破滅に導く「69手怪獣」として世に喧伝されましたが、地球を破滅する力などないことは、既に地球防衛隊の人自身が認めています。だからこそ、私は特に戦いもすることなく、地球を去るのです。
時々思うのですが、私は、怪獣どころか、むしろ、地球防衛隊の参謀達にとっては、「69手観音」(ロクジュカンノン)だったのではないでしょうか?国中から、そこに資金が集まったからです。そして、栄華を極めたからです。
新しい千手観音
聞くところによれば、また、新しい怪獣が地球破壊にやってくるという噂があります。今度は、千手怪獣(センジュカイジュウ)だそうです。私を作り上げた地球防衛隊の同じ参謀達がそう言いふらしてします。
私が地球を去るにあたって、日本の皆さんにどうしても言いたいこと、それは、絶対に私は、今後でてくる千手怪獣には関係ないということです。私は6年間生きながらえただけでも心苦しいのに、また、同じような新しい怪獣と関係があるように思われることには、とてもたえられないのです。
私は自分の6年間を許せずにいます、そのことを知ってください。さようなら。
雑感261-2004.6.1「「詳細リスク評価書 TBT(トリブチルスズ)」公開
-最も面白い第Ⅸ章(reviewerの意見と我々の考え)-」
産総研 化学物質リスク管理研究センター(AIST CRM)は、04年5月31日、「詳細リスク評価書 TBT (Version 1.0)」を公開した。ご希望の方は、以下のサイトからダウンロードできる。
http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/5-1-2.html
Executive summary と本文(266頁)からなり、summaryまたは本文の各章を個別に取り出すことができる。因みに、第Ⅸ章は46頁。
序でながら、1週間程度遅れて、「詳細リスク評価書 ノニルフェノール」も公開予定。
TBTをめぐる動向
TBTは既によく知られているとは思うが、船底に貝や藻類が付着するのを防ぐために塗布する船底塗料であり、漁網などの防汚材として使われてきたが、その生物への有害性のために、70年代初頭から、少しづつではあるが、規制がはじまった。
その悪い影響の最初の報告は、海洋性巻き貝にインポセックスが生ずるという報告である(70年)。続いて、漁業への影響として、76~81年にかけて、フランス、アーカッション(Arcachon)湾でカキ幼生着底に阻害が生じ、地元のカキ産業が壊滅したことが報告された。
77年から83年の間に、フランスではカキの生産量がTBTによる影響を受けて、その損害額は約1億5000万ドルにもなった。その後、様々な国や地域で、同様の影響が報告された。我が国でも、巻き貝のインポセックスは多くの海域で認められた。しかし、具体的な漁業被害との関係が指摘された例はなかった(現実にはあったのだろうが、そういう調査結果はなかった)。
わが国では72年に水産庁が漁網への使用の自粛を指導している。諸外国では、80年代初頭から、部分的にではあるが、船底塗料としての使用制限が始まった。
我が国では、90年に14種のTBTが化審法の特定化学物質の指定を受け、規制を受けることになった。
01年には、国際海事機関において、03年以降船舶への新たな塗布の禁止、08年以降船体への存在の禁止を内容とする条約が策定された。
評価の視点
この評価の対象海域は東京湾である。年代は90年、00年、07年。
対象生物は、沿岸域の水産資源生物とした。そして、貝類が特にTBTに敏感であることから、マガキとアサリを選んだ。
CRMでは生態リスク評価は、個体群レベル評価であるべきだという考えをもっているが、ここでは様々な制約から個体群レベル評価に至らず、個体レベル評価を行った。ただし、評価のエンドポイントは、個体群レベルで影響を及ぼす死、生殖、成長などを対象にすることにした。
最終的に評価のエンドポイントと、その無影響濃度(NOEC)は以下の値を採用した。
マガキ 成長阻害(16.6 ng/L TBT基として)→石灰沈着異常(1.0 ng/L TBT基として)
アサリ 幼生の成長阻害 (4.1 ng/L TBT基として)
当初、マガキについては、成長阻害を評価エンドポイントとすべきと考えていたが、カキを選んだのは水産生物だからであり、そうであれば、石灰沈着異常があれば、商品と成り得ないとの判断から、10倍ほど厳しい値になるが、石灰沈着異常を評価エンドポイントに選んだ(詳細は本文参照)。
1.0ng/Lという値は、殆どの生物の成長や、生殖に対する無影響濃度より低く、最も敏感な影響をエンドポイントとして選んだことと同義となった。
軟体動物のインポセックスは、1ng/L以下でも観察されるが、インポセックスによる産卵数の減少が認められる濃度は、この値より10倍程度高い濃度であるので、特に取り上げなかった(これについては、第Ⅸ章を参照)。
東京湾の海水中TBT濃度の推定
TBT濃度推定のためには、東京湾流動・生態系モデルを使った。これは、昨年公開した東京湾簡易リスク評価モデルの原型となっているものである。
そして、毎日の水質を予測して、その下層のTBT濃度と、先に述べたNOEC(無影響濃度)との値を比較してMOE
(margin of exposure)を求めた。
MOE=NOEC/環境濃度である。
そして、
MOE <= 1 リスクあり
MOE > 1 リスクなし
と判定した。
判定結果
1990年(規制前)1月の評価結果図(MOEの値)をこの雑感の最後に示した(本文図VI-4の1枚目)。
<アサリ>
アサリについては、荒川河口付近のMOEが最も小さく、年間を通じて1未満となった(リスクあり)。荒川河口付近などでは年間を通じて、その他の生息域では冬季に成長阻害を起こす可能性があると考えられる。
<マガキ>
マガキは、年間を通じて生息域全域で1未満の値を示した。リスクありと判定した。
つぎに、2000年と2007年の予測をした。2000年の結果(本文図VI-12)と、2007年の結果(本文図VI-13)をこの雑感の末に示した。
2000年のアサリのMOEは5~15で推移した。マガキのMOEは、千葉港、横浜港及び東京港では依然として1未満となった。したがって2000年では、アサリは成長阻害を起こす可能性がなくなったが、マガキには局所的にリスクありと判断された。
2007年のアサリのMOEはさらに大きくなり(50~100)、アサリは成長阻害の可能性はないと予測される。マガキも2007年では1未満のMOEは認められず、全域的に10前後であるので、リスクなしと判定した。
レビュワーのご意見と我々の考え
多分、レビューワーのご意見とCRMの考えが第Ⅸ章が、この評価書の中で最も面白い部分ではなかろうか?
今後
レビューワーのご指摘の中にもあったが、ここで使われた東京湾流動・生態系モデルには、底質からの溶出が組み込まれていない。代わりに簡単なモデルを用いた計算結果を引用したが、底質からの溶出を組み込んだモデルの高度化は必須である。現在このことに努力を傾注している。
つぎに、TBTの代替物のリスク評価にとりかかっている。TBTが禁止されて、代替物質が使われている。しかし、それらも決して、海洋生物に対して無害ではない。そこで、代替物質として使われる可能性のある数種の物質についてのリスク評価にとりかかっている。
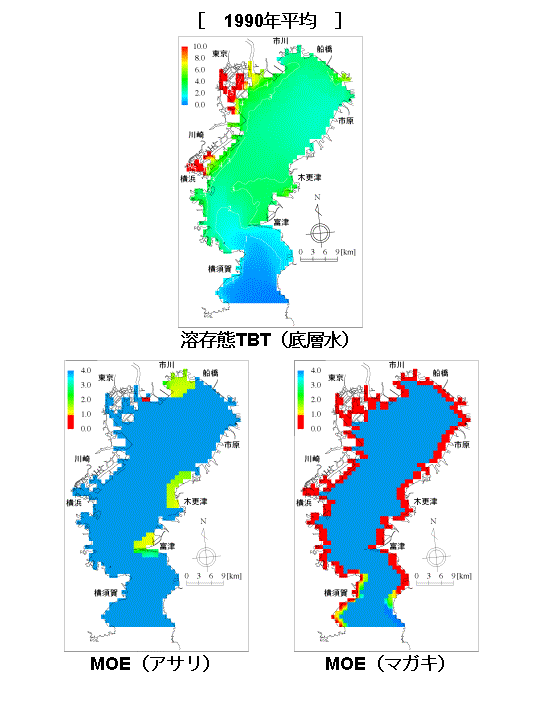 |
図VI-4 アサリとマガキに対するリスク評価(1990年平均)
(MOEの値が1以下のときリスク有り) |
| |
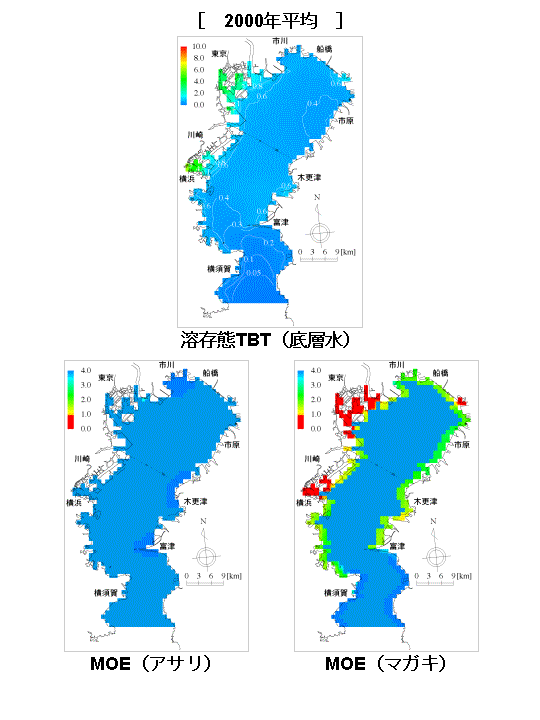 |
図VI-12 アサリとマガキに対するリスク評価(2000年平均)
(MOEの値が1以下のときリスク有り) |
| |
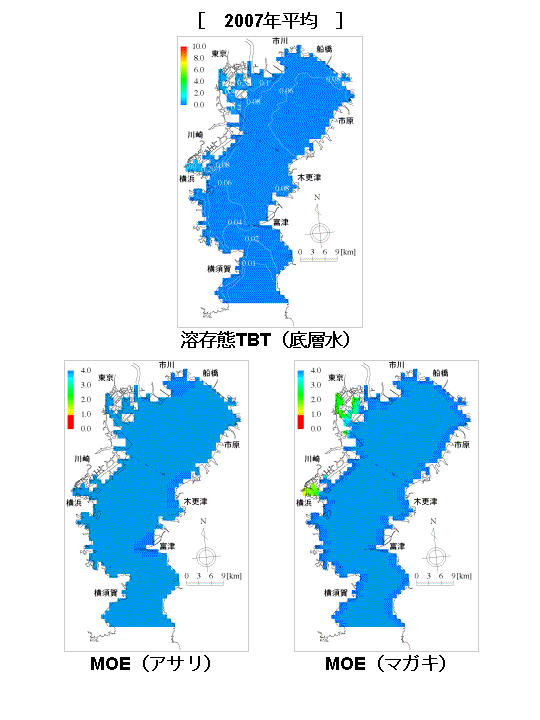 |
図VI-13 アサリとマガキに対するリスク評価(2007年平均)
(MOEの値が1以下のときリスク有り) |
トップページに戻る