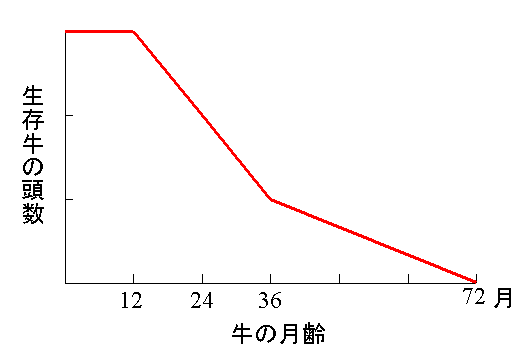雑感260-2004.5.25「Risk Learning(リスクを学ぶ)というソフト」
このソフトに含まれている重要な概念
AIST-CRM(化学物質リスク管理研究センター)の吉田喜久雄主任研究員が、Risk
Learningというソフトを開発した。すでに、昨年(03年)12月15日に朝日新聞で大きく報道されたので、知っている方も多いとは思うが、もう一度ここで、その特徴を紹介しておきたい。
一言で言えば、気になる化学物質を選び、その濃度のデータを入れ、暴露シナリオ(飲料水として飲む、野菜を食べる、魚を食べる、空気を吸う)を選び、その人の条件を入れるとリスクが計算できる、そういうソフトである。
この雑感の最後のところにdemo softを入れてあり、それを開くと、自然と、操作が進行する。それを開いてみて頂ければ分かるが、操作は極めて簡単である。
操作は簡単だが、このソフトには他にはない、重要な概念が含まれている。
クロスメディアという概念を、複雑な計算を自分ですることなく、自然に学ぶことができるように作られていることである。
クロスメディアとは?
demo fileには、水道水中のクロロホルムを1)飲料水として飲用することによる経口リスクと、2)洗濯や炊事、フロ等で使う水道水中のクロロホルムが揮発して室内空気中に含まれ、それを吸入することによる吸入リスクの二つを計算する場合が示されている。
この後者の部分が、クロスメディアによるリスクである。
メディアとは、環境媒体の意味で、大気、水、土壌、野菜、肉など化学物質が存在する場のことである。当初「水」に存在したクロロホルムは、大気中に揮発して、「大気」に移動し、人が呼吸することで体内に入った。水から大気への移動、これがクロスメデイア移動である。
ダイオキシンの例
ダイオキシンの例を思い出そう。
焼却炉からもくもくと煙が出ていて、そこにダイオキシンが含まれていれば、大気から吸入すると考えるのは自然である。しかし、ことは、そう単純ではない。ダイオキシンの主要な摂取ルートは、大気ルートではなく、魚介類であったことが分かった。つまり、ダイオキシンは、大気→水→魚と、または、水→魚と、媒体を移動して、人の体内に入った。これがクロスメディア移動である。
所沢でホーレン草が汚染されたかのような報道があり、大騒ぎになり、農家には多大な被害を与えたが、これが本当だったなら、大気→野菜というクロスメディア移動である。
このように、あらゆるところで、クロスメディア移動は重要な役割をしている。しかし、そのことを忘れてしまうことも多いし、定量的な評価も難しい。このソフトは、クロスメディア移動の重要性を教えてくれるし、簡単にどのルートが問題かを教えてくれる。
ヒドラジン
PRTR対象物質のひとつにヒドラジンがある。
PRTRの報告によると、多くは、廃棄物としての搬出なので、大気や水域への排出量は多いわけではない。ただ、有害性が強いので注意はしている。
このヒドラジンが、大気中に1μg/m3存在した場合を仮定すると、その吸入リスクに比べ、野菜からの経口リスクは4桁も大きい(多くの仮定があることに注意)。
また、水道水中に含まれる場合を考えると、この場合は大気に揮発する比率は小さく、吸入リスクは、経口リスクの1000分の1である。
つまり、このソフトを使うと、どの経路に気を付けるべきかが分かる。
有害性データには注意
注意してほしいのは、この結果を、今のように相対的な評価に使うのではなく、絶対値を使いたい場合は、計算に用いられている仮定をきちんと理解すること。ここで用いられている有害性データは、基本的に米国環境保護局(EPA)のデータベースIRISに拠っていることである。
IRISでは発がん性の強さについては、人への影響があるかどうか確かめず、動物実験結果から簡単に推定している場合も多く、注意して使う必要がある。
クロロホルムの吸入発がん性データについても、現在見直しが進められている。
有害性データが変わったらどうするのか、とよく聞かれる。それは、その時点で修正し、基準値も変えるしかない。データが蓄積されて、より正しい数値になることは良いことである。先に決めた責任を問われるからと、いつまでも変えないケースが見られるが、そちらの方がおかしい。
データが少ない場合、不確実性係数に大きな値をとり、安全側で有害性評価をしている(予防的アプローチの一つ)。したがって、データが蓄積されれば、基準値が甘くなることはありうる。それを否定すると、実は、予防的アプローチはできなくなる。このことにも留意してほしい。
demo fileを開いてみよう
Risk Learningのホームページにあるダウンロードページから、デモンストレーションファイルをデスクトップ上にダウンロードし、ダブルクリックすると動き出す。トライしてみてほしい。クロロホルムのリスク評価の動作が、つぎつぎ現れて、嬉しくなる。
ファイル名が長いが、この名前で画面の制御等をしているので、変更しないで欲しいと注意書きがある。
download
つぎには、本物のRisk Learningのソフトをダウンロードし、使ってみよう。
Risk Learningのホームページ: http://www.riskcenter.jp/RL/
雑感259-2004.5.18「大井川農業用水水利権転用問題とTV朝日の報道(続き)」
(先週の続き)
5月2日のテレビ朝日の放送では、農業用水の転用について三つの例が紹介された。記憶がやや、不鮮明なので、もし間違いがあれば、教えて頂きたい。
一番目は、農業用水を工業用水に転用し、工業側が水利組合にいくばくかの費用を払っているケースである(年690万円とか1580万円とかの話がでていた)。この場合にもまた、二つのケースがあり、一つは水利組合がお金を受け取っている場合で、もう一つは町が受け取っている場合であった。
二番目が、農業用水を工業用水に転用したが、二本の水路が平行して走り、無駄この上ないという状況。
三番目は、広島県の目谷ダムの農業用水利権を上水(水道水)に転用する場合に、多額の清算金を求められており、新しいダムを造る方が安いという世羅町長の話である。
農水省の反論
これについて、農水省農村振興局は、5月2日“サンデープロジェクト「なぜ水は盗まれたのか」(5月2日)について”と題する反対論を展開している。
http://www.maff.go.jp/nouson/houdou/20040502.htm
この中で、農水省は大井川の水利転用はすでに解決した問題で、水利組合へのお金の支払いも今は行われていないと述べている。確かに、2004年2月末に、農業用水の一部を工業用水に転用することを認め、一応の整理がついたという報道(静岡新聞 2004年02月22日)があった(このことは、私は知らなかった)。
これに至るまでに、大井川の違法取水として何回も報道されており、それに対処するかたちで、委員会も設置され、工業用水への転用が認められた経緯がある。
また、農水省HPは、広島県目谷ダムについて、その農業用水水利権を都市用水に転換するために、世羅町など3町に4億6000万円の清算金を求めたことに対して、水道の費用として、それなりの補助や交付金があるので、町自体が払う金額はずっと少ないと述べている。
筆者自身は、事実を確かめていないが、農水省の述べている事実が正しいとすれば、水利組合や町がお金をとっているというTV朝日の報道は、すでに終わった問題を放送したことになる。或いは、終わったことになっていて、この事実が続いているのか、そこがよく分からない。もし、農水省の言っていることが事実なら、TV朝日の報道は、不誠実の印象を受ける。
水利組合がお金を徴収してもいいではないか
ただ、私自身は、水利組合がお金をとることは悪いと思っていない。当然だし、こういうのをどんどん認めればいいではないかという考えである。
もう一度、問題を整理する。
1)農業用水は余っている。農水省は、水田面積が減少しても、それで直ぐに農業用水の必要度が下がるわけではないと、先のHPでも強調している。確かに比例はしないが、余っていることは事実。
2)この水利権を都市用水に転用すれば、我が国に渇水問題はおきないし、新規利水ダムも不要である。
3)国土交通省(旧建設省)は、これを転用する場合、無償で国に返せ、それを国土交通省が再配分すると言っている。
4)この国土交通省の主張は無理である。なぜなら、権利を有する農業者に何のメリットもないからである。
5)農業者は、それくらいなら、いざという時のために権利を持っておきたいと思うのは当然である。
6)まず、自主的に売ることを認めるべきである。水利権は権利なのだから。
7)場合によっては、料金を取って貸すことも認めた方がいい。
8)これでは、異常に高くなるという主張がある。それなら、金額の上限を決めればいい。現実には、ダムを造る方が、また、農水省と国土交通省との調整ができて、ばかでかい水路を作る場合の方が高いのである。
農業水利権への敬意がほしい
かつて、「水の環境戦略」(中西、岩波新書)で「都市は水を使わない」という題目で、大都市が水を多量に使うと言われているが、実は、水田の方が単位面積あたりの使用量で言えば多い。水田をつぶして、都市が発達して日本では、水利転用がうまくいけば水不足はおきないと書いたことがある。
また、1994年9月1日の朝日新聞に、「農業水利権に敬意払い 都市用水への転換を図れ」という文章を書いたことがある。農業者が持ってきた権利を尊重し、水を維持するための長年の努力には敬意をもって対処してほしい。当事者主義で、水利権の貸与や売買を認めるべきである。そうすれば、安い費用で水利転用ができるし、渇水問題など起きない。
ここで報道されたケースについて、私には予備知識がなかったので、報道の記憶のみで書いている。
実は、大井川の水利転用問題は大きな問題で、それは、今年の2月に解決をみているのである。いい解決かどうかは別だが、大きな問題は解決している。この報道で取りあげられたケースは、そこから漏れたか、小さな問題かの筈であり、私も現地の状況は知らない。
雑感258-2004.5.11「農業用水の転用問題-テレ朝の報道-(来週の予告)」
5月2日のテレビ朝日、サンデープロジェクト(午前中の時間帯)で、大東町など大井川水系における農業用水から都市用水(水道)や工業用水への転用問題を扱っていた。
これは、我が国の水問題で最も重要な課題で、これが解決すれば、少なくとも水不足はなくなるし、利水のためのダム建設の必要性もなくなる。これは、私の年来の主張。
非常に重要な問題だが、この日の取りあげ方は一方的で、水を使うことを「盗水」として現場の町長などを責めていて、聞き苦しかった。また、原因は、農水省の既得権擁護のためだと決めつけていた。
確かに、農水省も悪いが、この主張が通ると、一方的に国土交通省(元建設省)の権益が大きくなってしまう。気をつけないといけない。放送は、少なくともフェアーでなかったし、結果が良くなるような内容ではなかった。
このことについて書こうと思っていたが、余りにも忙しくて駄目だった。来週書くことにする。
今週は、来週の予告のみです。
雑感257-2004.4.27「BSE:検査の見落とし率」
小澤OIE顧問の講演
4月15日に開かれた、第41回食品安全委員会に招待された小澤義博国際獣疫事務局(OIE)名誉顧問は、“全頭検査について「精度に限界があり、多くの感染牛が検査をすりぬける恐れがある」と指摘した。
牛肉の安全対策としては、「--(一部省略)危険部位の除去が最も重要な手段」とも述べ、全頭検査は必ずしも有効ではないとの認識を示した”と、4月16日の日経は報じている。また、講演資料を見ると、「検査で陽性とでるのは感染牛の約半分以下」と述べている(http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai41/dai41kai-siryou1-1-2.pdfの11枚目のスライド)。
このことは、二つの議論を呼びそうだ。ひとつは、すでに新聞などでも主張されていること(朝日新聞内山記者、毎日新聞小島記者)であるし、また、小澤さんの主張でもあるのだが、「だから、全頭検査で安全が保証されるものではない、基本的な対策は危険部位除去である」という主張である。
もう一つ、多分出るだろう議論は、「もっと精密な検査を行うべきだ」というものである。先般、20ヶ月齢の牛でBSE陽性(擬陽性か?)とでた結果を受けて、だから全頭検査をやって良かったというのは、この後者の流れの考え方である。
私は、この主張は両方間違いを招き易いと思う。
何故か?
前者の言いたいことは分かる。全頭検査で絶対安全は保証されない、だから、絶対安全を求めて全頭検査をしても意味がないということだろう。
ただ、この論調で欠落しているのは、我が国では全頭検査か、危険部位除去かの議論をしているのではなく、両方やっていて、それを続けるべきかどうかの議論をしているので、危険部位除去が最も重要な手段であるとしても、それはすでにやっている。
その上全頭検査をすべきかが争点であるから、どちらが重要ではなく、どこまで安全を求めるか、どのリスクは許容できるのかの議論をしなければ意味がない。
つまり、危険部位除去の上に、全頭検査が必要なほどリスクが大きいのかという問題提起をしなければならないのである。
見落とし率50%?
その議論を避けて、全頭検査では半数しか分からないということになれば、なぜ、もっと精密な検査をしないのかという議論に発展するだろう。
「陽性と出るのは、約半数以下」というメッセージは丁寧に説明しないと誤解を招く。むしろ、あやういメッセージだと思う。
中西は、中央公論(5月号)で、検査の見落とし率0.01と仮定して計算をした。その際、このように書いた。「この小論の中では、見落とし率は1%と仮定した。頻度としてはもっと高いかもしれないが、見落とされる場合は、牛体中のプリオン量がかなり少ないのでこの比率を用いた。」
この意味は、先の小澤さんの指摘と矛盾しない。つまり、半分くらいの見落とし率があっても、見落とされるプリオン量は1%程度であるという意味である。
感染牛がすべて陽性になるとは限らない
私が、なぜ見落とし率1%としたかを説明しよう。
小澤さんの講演slide(http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai41/dai41kai-siryou1-1-2.pdf)の6枚目に、「BSE感染と潜伏期間」というタイトルのスライドがある。そこには、BSEの潜伏期間が2〜8年で、その間は感染していても陰性となる、そして、発症の直前6ヶ月くらいにしか陽性にならないと書いてある。現実には、我が国での検出技術を使えば、より早く検出できるようであるが、検出の原理はこの図に近いであろう。
年齢を重ねるとBSE陽性牛の率が増えることは、今や常識である。だから、24ヶ月齢超の検査とか、36ヶ月超の検査が行われる。しかし、だからと言って、24ヶ月超または36ヶ月超で感染するわけではない。大体が、6ヶ月から24ヶ月齢で感染している(雑感145の図参照)。
ということは、5-6年齢での発症牛は少なくとも24ヶ月齢までに感染している。もし、途中の屠殺や死亡を考えなければ、5-6年齢で発症牛の数だけ若年齢でも感染牛が居るはずである。それは、脳幹部分のプリオン量が少ないから、検出されないだけである。
現在の検出法は、脳幹でのプリオン検査である。ところが、感染初期は脳にはプリオンは存在しない。ただ、他の部位には少量だが存在する。
小澤さんが言うのは、こういう状態の感染牛は検出できないと言っているのである。それは、その通りである。
見落とし率1%の意味
では、この半分は検出できないことと、中西が仮定した1%との関係はどうか?
私は、以下のような仮定をおいて計算し、約1%でいいと考えた。
この図の縦軸は生存牛の数である。
横軸は牛の月齢である。
牛は, 0〜24ヶ月齢までに1/3、24〜36ヶ月齢の間に1/3、さらに36〜72ヶ月齢の間に1/3が屠殺されると仮定した(米国では、高齢の牛は少ないが、ここは日本の状況を図にした)。
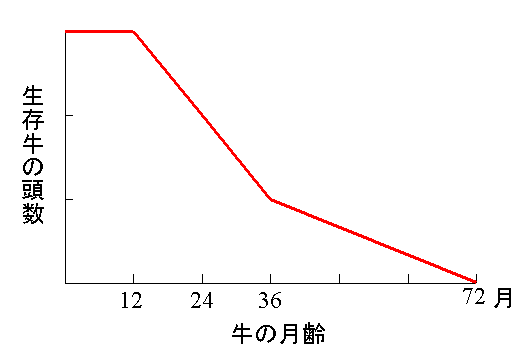
つまり、その年屠殺される牛の1/3が0〜24ヶ月齢、1/3が24〜36ヶ月齢、1/3が36〜72ヶ月齢である。もう少し詳しく書いたのが、下の表である。
ポイントは、三つの月齢群において、感染牛の比率は皆同じだということである(厳密に言えば、0〜24ヶ月齢については、24ヶ月の時点で)。
表 牛の月齢と見落とし率
| |
月齢による群 |
全体 |
| 0〜24 |
24〜36 |
36〜72 |
| 年屠殺数中の割合 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1 |
| 検出率(頭数の割合) |
全く検出できない(月齢群内) |
5割(月齢群内) |
10割(月齢群内) |
5割(全月齢) |
| 見落とし率(頭数の割合) |
10割 |
5割 |
なし |
5割(全月齢) |
| プリオン存在量(牛頭当量) |
0.1% |
5% |
100% |
|
| 見落とし率(プリオン量の割合) |
0.001×(1)=0.001 |
0.05×0.5=0.025 |
1×0=0 |
(0.001+0.025)×(1/3)=0.0087 |
0〜24ヶ月齢での検出率は0、つまり、すべて見落としである。ただし、20ヶ月齢で陽性が出たと騒がれているが、このような例外はあって当然なのである(尤も、このケースは特別な検査をしたらしい)。
この月齢では、見落としと言っても、プリオン存在量は低いので問題にならない(この表の計算では、成牛の陽性牛と比較した場合、1/1000のプリオンしかないとしている)。
24〜36ヶ月齢では、見落とし率5割、プリオン存在量5%としている。
36〜72ヶ月齢では、見落としはないとした。
この場合、最後の列、全体のところをみてもらえば、全体で見落とし率の頻度は5割だが、プリオン量で見れば、約1%なのである。
どちらが安全かという議論は意味がない。リスクレベルを議論することが肝要
どちらが安全かという議論になると、どれだけ徹底的に危険部位除去をしても、さらに全頭検査をした方がいいということになるし、さらに、全頭検査の精度をあげよという議論もでてくるに違いない。20ヶ月齢も検査すべしという議論がすでに出ているが、より安全なのは?という立場に立てば、そのようになる。
大事なことは、発想を変えることである。つまり、どの位のリスク、どのくらいの安全を保つために、いくら費用をかけるかという議論をすることである。
これまでのBSE関連雑感:
小川英行著 ”ディーゼルこそが日本を救う”(ダイアモンド社)という本が出ている。それなりに面白い。機会があればとりあげる。
来週は連休のため、次回の雑感更新は、5/11(火)の予定です。
雑感256-2004.4.20「理科嫌いは誰が作ったか?」
日亜化学の投資
4月20日の日経によれば、日亜化学工業の今年の投資額は300億円を超えるという。そこに、発光ダイオード大手の日亜化学工業(本社徳島県阿南市)と書いてあって、ああ、阿南市にあるこの企業が大手になったのかと、嬉しくなった。
そこで、以前から書こうと思っていた中村修二さんの特許訴訟について書くことにする。
理科嫌いをなくすために
私の周囲には、今の若者の理科嫌いを心配し、様々な努力をしている教授達がいる。ある人は、いい教科書を作る努力をしているし、また、ある人は実験室が汚くて、安全度が低いことが問題だから、安全教育をきちんとした方がいいと言って努力しているし、またある人はもっと必修科目を増やせと主張している。
それはそれで分かるが、何かピントがずれているように思ってきた。
そして、中村修二さんの青色LED(発光ダイオード)の裁判での勝訴判決を聞いた時、「これだ」「これだ」「これからは、理科嫌いはなくなる」と思った。理科系の人の努力は今まで報われてこなかったのである。
そして、この判決の後、企業の経営者が「こういう判決が認められると、企業はやっていけない」と口々に言うのを聞いて、理科嫌いを作っているのはむしろ日本の経営者ではないかとさえ思った。
給与差
吉川弘之さん(現在、産総研理事長)が東大工学部長の時に、やはり同じようなことを書いていた。東大工学部卒業生の理系職就職者が、どんどん減っていき、ついに5割を切った年だった。
当時、私は工学部都市工学科の助手をしており、都市工学科でそれより以前から、損保、金融にいく卒業生が多く、文系への就職には慣れてはいたが、やはり工学部全体の半数が技術的な仕事につかないというのは、一つの時代の流れを感じた。
そのとき、吉川さんが書いたのは、文系出身者に比べ、技術者の給与が低すぎる、これでは就職しない、もっと技術者の給与を高くすべきという内容だった。
「理系白書」(毎日新聞科学環境部著、講談社刊、2003)によれば、ある国立大学出身者で、理系の場合の生涯賃金は3億8400万円、文系が4億3600万円で、5200万円の差があるという。多分、この差は東京大学卒業生だともっと大きい。
「負けてたまるか!」
中村修二さんの著「負けてたまるか!」(朝日新聞社、2004)を読むと、中村さんはこの裁判を若い人のためにやったと書いている。
「現在の日本では、理系離れや理系出身者の文系企業への就職、理系科目の学力低下などが問題になってなっているが、科学者や研究者に対して成果に見合った対価を払うようにしないと、才能ある若い人材を科学技術の分野に引きつけることはできない。」(203頁)と書いている。本当にそうだと思う。
以前、何故技術者の給与が、文系出身者(特に、金融や経営コンサルタント)に比べて低いか考えて、やはり理系は利益が少ないから仕方がないのかと思っていた。
ところが、今回の裁判の過程を見ていて、理系は儲からない、稼げないのではなく、会社にとられていることを知った。理科嫌いを作っているのは、こういう会社の経営のあり方ではないか。
噂の真相
最近休刊になったが、「噂の真相」という雑誌があった。その雑誌は、こういう言葉も古くなったが、左翼、反体制を標榜していた。アナーキーでもあった。
ところが、その3月号か、2月号かに、「中村修二、守銭奴」(正確な言葉は忘れた)と書いてあったのをみて私は驚いてしまった。どうして、守銭奴か?その成果をとってしまう企業の方が守銭奴ではないのか。旧左翼って、体制に都合のいい存在になってしまったのだなとつくづく思った。
冒頭に書いた日亜化学工業と、中村さんと間で、この発明を巡って裁判が行われている。金額について双方の主張に違いがあるのは当然で、それが裁判で争われるのは透明でいいことだと思う。
しかし、聞くところによると、日亜化学工業は、中村さんの発明に対して、かなり心ない主張をしているらしい。発明者に対する敬意を忘れないでほしい。そして、東京から遠く離れた小さな町から、光を放ち続ける企業であってほしい。
トップページに戻る