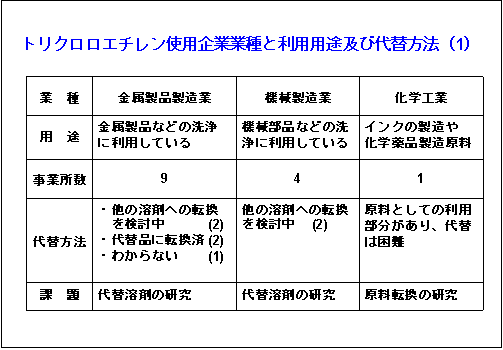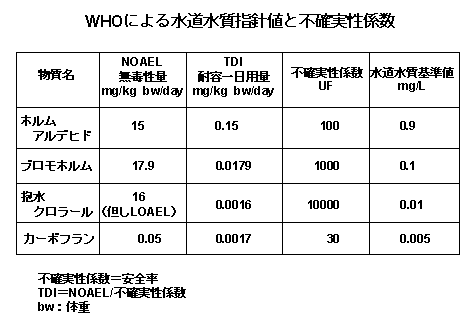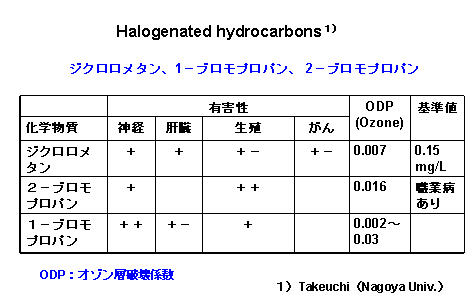雑感245-2004.2.5「神栖町井戸水ヒ素汚染−汚染源ほぼ確定か?
―もしこれが正しいなら、茨城県の責任は大きい−」
ヒ素中毒発生
2003年(昨年)3月、茨城県神栖町(かみすまち)で複数の中毒患者が発生し、それが砒素中毒であることが確認された。その砒素は、井戸水に起因し、住民が使用する井戸(数戸での共用井戸が複数掘られている)に含まれていた。
旧日本軍の毒ガス兵器に使用されたとされる有機ヒ素(ジフェニルシアノアルシンとジフェニルクロロアルシン)の分解生成物と思われるジフェニルアルシン酸が検出され、この化学物質が他のヒ素化合物から生成されるとは考えられなかったので、毒ガス兵器に起因するヒ素化合物が中毒の原因とされた。
ただちに、環境省は大がかりな汚染源調査に入ったが、昨年末(12月27日)、原因は特定できなかったという発表をして、2003年の調査を終了した。もちろん、2004年になっても調査は続いているが、それに関する報道はない。
他方、茨城大学広域水圏センター神栖町有機ヒ素地質汚染調査団を結成し、調査をしていた楡井(にれい)久氏らは、8月に中間報告をし、さらに12月に報告会を開き、ほぼ汚染源を確定したと発表した。
汚染源は砂利採取跡地に捨てられた廃棄物
楡井さんらの報告は、当初私が予想した結果と一致しており、詳細を知りたいと資料を頂いてきた。それによれば、汚染源は複数あり、いずれも砂利を採取した凹地に埋められた廃棄物の人工地層中に存在すると推定している。1970年代から1980年代に埋められた汚染残土石または汚染ゴミである可能性が高いとしている。
この地区は、昔の河川敷で地中に良好な砂利がある。その砂利が骨材として採取された。砂利の値段は、土地代の10〜100倍と言われている。その砂利が採掘されあとの凹地は、下の方は廃棄物で、やや上は残土で、表面は土で埋め戻され、宅地に造成された。
茨城大学報告書には、年代を追った航空写真があるが、それによるとA地区(A地区とB地区の井戸がヒ素で汚染されているが、その区別については後で述べる)では、1983年の写真では、1ヘクタールくらいの敷地の2/3ほどの大きな穴が見える。88年には完全に埋めも出されているのが分かる。
人工地層
2003年12月4日、「神栖町有機砒素地質汚染調査 第二次報告」(茨城大学広域水圏センター神栖町有機ヒ素地質汚染調査団)には、つぎのような記述がある。
「凹地に、ダンプ・カーなどで搬入され堆積した人工地層内には、ダンプ・カー1杯分の物質(時間的地層単元)が、下から上へと累々と重なっている。累重している地層(時間的地層単元)は、非汚染土石類や汚染土石層、又はゴミ層からなっている。」
まだ続く砂利採取
ここに、この問題が起きたばかりの4月に撮った写真を一枚掲載する(撮影者濱田弘さん)。

これは、最初に汚染が問題になったA地区の、その住居に隣接する場所の写真である。今でも、砂利の採取は続いており、汚染井戸のすぐ隣まできているが、茨城県は中止命令を出していない。
茨城県の責任
もし、砒素汚染が埋め戻しのための廃棄物に原因があるとすれば、責任はむしろ茨城県にあるのではないか?もちろん、そのもともとの原因は旧日本軍かもしれない(これも、もう一度疑ってみる必要がありそうだ)。しかし、この埋め戻しは茨城県が認めたことである。とすれば、茨城県の責任はかなり大きい。
にも拘わらず、最初から治療費の補助や補償金は、国(環境省)が全額支払うものというような雰囲気で話が進んでいる。どこかおかしい。汚染の原因によって支払い責任者は違う筈で、国の責任という前提で進めないでほしい。
すべては、原因が明らかになってからの筈である。確か、そういうことが最初の頃、環境省から出された文書に書いてあった。しかし、これほど時間が経つと、払ったことが既成事実になってしまうのではないか。
では、原因は(B地区の汚染)
汚染源は、人工地層(廃棄物)の中にある
まず、B地区の汚染原因からはじめよう。(茨城大学広域水圏センター神栖町有機ヒ素地質汚染調査団、「神栖町有機砒素地下水汚染(B地区)の汚染機構解明」 第1次報告、平成15年7月22日による。)
最初に身体異常を訴えた人々の居住区を、茨城県(環境省)はA地区とよび、そこから、西北西に1kmほどの地区にも井戸水のヒ素汚染があることがわかったが、この地区をB地区と呼んでいる。A地区の井戸水中ヒ素の最高濃度は4.5 mg/Lで、B地区のそれは0.43 mg/Lである。
茨城大学の調査は、B地区から始まった。そして、最終的な結果が、以下の図―1(報告書では図-5-2)と図−2(報告書では図-5-3)である。
ここで、B-4というような記号は井戸を表す。T.P.は東京湾標準高度である。
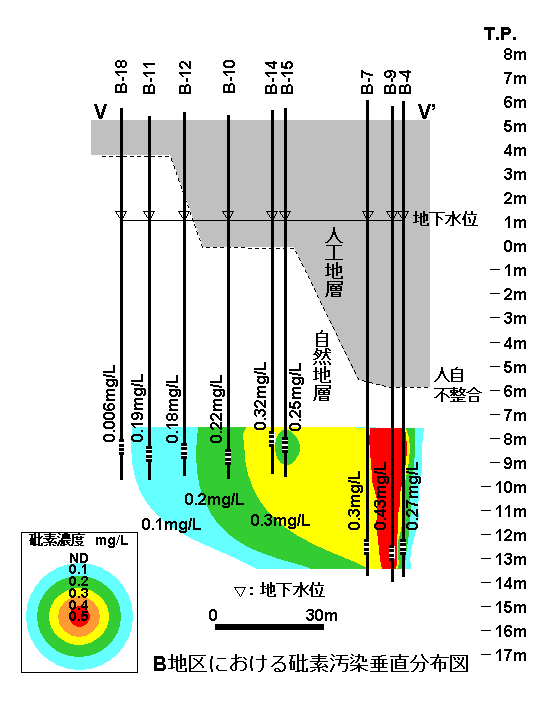
図−1
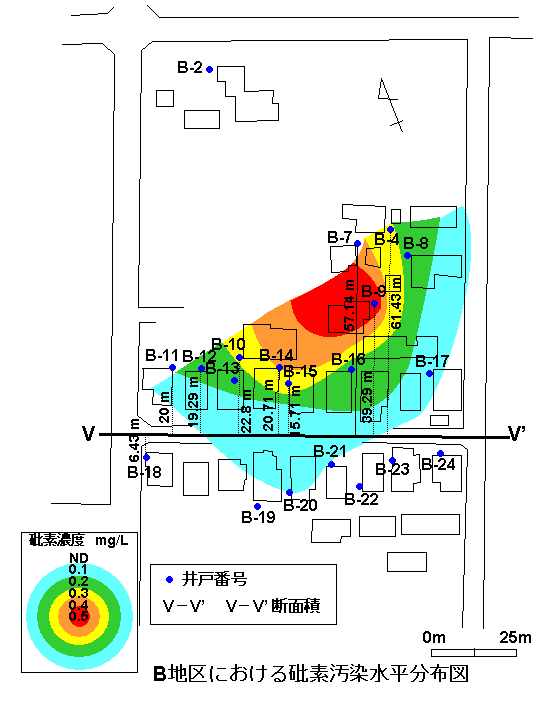
図−2
V−V’が地表面を表す。TPで -6m程度まで人工地層(ごみと表層の覆土)がのび、その下に自然地層がある。その境界を人自不整合(じんじふせいごう)とよぶ。汚染井戸のストレーナは−8mから−13mの間にある。最も汚染されているのがB-9で0.43 mg/L、最も西側のB-18の濃度は0.006 mg/Lと低い。
そして、茨城大学調査団は以下のように結論する。
1)B-9を中心に汚染がひろがっている様子が読める。このことは、B地区の汚染は、A地区の汚染源から汚染地下水が移動してきたものではなく、近傍に汚染源があることを示唆するものである。
2)汚染源は、人工地層内に遺棄された有機ヒ素が、下に引っ張られ、帯水層に漏出した。汚染源は砲弾とは限らない。
3)この地域の地下水流動は、B地区の周辺にある鹿島工業用水道のための地下水取水に支配されている。そのために、地下水は西方向に移動する(もっと複雑だが、簡単に書いておく。もし、鹿島工業用水による取水がなければ、地下水はちがった方向に移動する。この括弧内は、中西による追記)
4)ボーリング調査等で確認が必要
(人工地層中の汚染物が、水平方向に移動せず、垂直方向に落ちるのは、人工地層の透水性が悪いためである。中西追記)
A地区の汚染源
茨城大学広域水圏センター神栖町有機ヒ素地質汚染調査団、「神栖町有機砒素地質汚染調査」 第2次報告、平成15年12月4日による。)は、環境省の調査結果をもとに解析した。その結果は以下の通りである。
図-3(報告書では、図6)にA地区の汚染井戸(最高値4.5 mg/L)と、そのすぐ近傍に掘られたNo.26のボーリングした地層中の砒素の濃度を示す。この地点での人工地層は薄く、そこにも、その直ぐ下層にも汚染は存在しない。むしろ、深い部分に汚染がある。A地区井戸のストレーナは深度-13〜15mで、丁度この汚染地層にかかる。
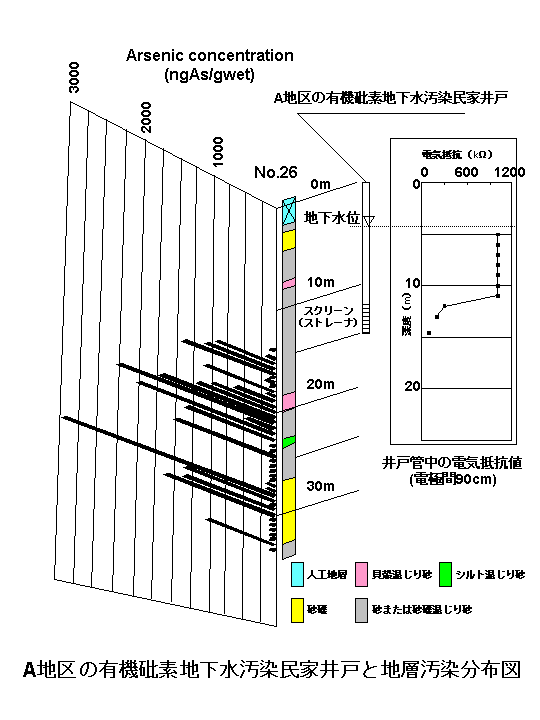
図−3
1)A地区の汚染源は、やはり人工地層中にあると思われるが、B地区と違い、その汚染源は東側のやや離れたところにある。
2)A地区の井戸のストレーナが、数m浅ければA地区の被害はなかったであろう。その代わり、広域汚染に発展した畏れがある。
3)工業用水の取水で、汚染物が下層の帯水層に絞り出され、広域にひろがっている。
4)15m以浅(TPで-10m程度か?中西追記)の井戸の汚染があれば、その汚染源は真上または周辺の人工地層内にあり、それより深い井戸の汚染の場合は、やや広域の汚染と考えていいだろう。
君津
楡井さんは、千葉県君津市での東芝コンポーネンツによるトリクロロエチレンによる汚染解明でも功績を挙げた。楡井さんらの研究で、ほぼ汚染源の推定ができた。これは、あの地域の事情を知る者には、実に理にかなった推定に思える。しかし、その推論を確かめるための調査が必要である。そのために、文科省の研究費を申請し、約2000万円が認められたという。これからが楽しみである。
環境省は何故?
環境省は、すでに調査費として20億円使ったという噂がある。あまりの大きな金額で、ちょっと信じられないが、多額の調査費を使ったことは確かである。A井戸の周辺だけでも、30カ所以上でボーリングをしている。それでも、原因を特定できずにいる。何故だろう?(暇ができたら書くことにしよう)
地元の人間はことのはじめから、砂利穴の埋め戻しによって原因物質が持ち込まれたものと見ているから、環境省のやり方を冷ややかに眺めていて「環境省はいつから建設省並みのトンカチ土建屋になったんだっぺ。あちこちむやみにボーリングしたって何にもめっかんめぇーよ。もっと智慧を絞れば的もしぼれっぺーのによ。」と醒めたものである。
(最近、茨城ネタが多い。生活時間の半分を茨城県つくば市で過ごしているためである。ただ、これらの問題が国レベルでの重要性をもっている。これだけ問題が発掘できるのなら、やはり、北九州市とか、東大阪市とかに住んでみる必要があるなと思ったりする。)
雑感244-2004.1.26「アメリカのBSE牛と全頭検査」
2004年1月19日朝日新聞夕刊「窓−論説委員室から」で論説委員の竹内敬二さんが、「風評被害」というタイトルの文章を書いているが、その中にかつて中西が書いた文章を紹介してくれている。(この元の文章を末尾に再録)
米国で聞いた講演
この文章を書いた2001年6月に、私は、米国でハーバード大学のリスク解析センターが行ったBSEのリスク評価に関する報告を聞いた。そこでは、米国でのBSE流行の危険性も、人間がクロイツェルヤコブ病に罹るリスクも極めて小さいとされていた。今回の米国でのBSE牛発見のこともあり、もう一度その時のメモを読み返してみた。
この報告書の全文は、農業省のHP*1)
からも入手出来るのだが、長文なので読まなかった。ただ、間違いがあるといけないので、数値の対照にExecutive
Summaryだけは参考にした。私が講演を聴いたのは6月だったが、農業省から正式に公開されたのは2001年11月だったらしい。
*1) Evaluation of the Potential for Bovine Spongiform Encephalopathy in the United States,
http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/risk_assessment/mainreporttext.pdf
牛への感染
ハーバード大学のレポートは、狂牛病(BSE)の牛が米国に入ってきた場合、どのくらい感染するかを推定することに重きがおかれたものだった。聞いた当時は、牛への感染と人への影響が区別されていることに気がつかず、漠然とリスクが小さいという報告だったと思っていたが、今回読み直すと、まず感染牛から他の牛への感染について大きく扱われ、人へのリスクはその結果として割合軽く扱われている。
ここが日本との違いである。もっぱら輸入に頼り、人への影響だけを論じているのと相当ちがう。
シナリオ
こういうシナリオでリスクを計算している。
10頭のBSE牛が輸入されたとしても、新たに平均して3頭、95%値で11頭が病気に罹るが、20年間で完全に病気はなくなるとしている。この感染は、違法な廃棄物処理(肉骨粉となり、飼料に入ることであろう)が大きく寄与しているという仮想のシナリオである。
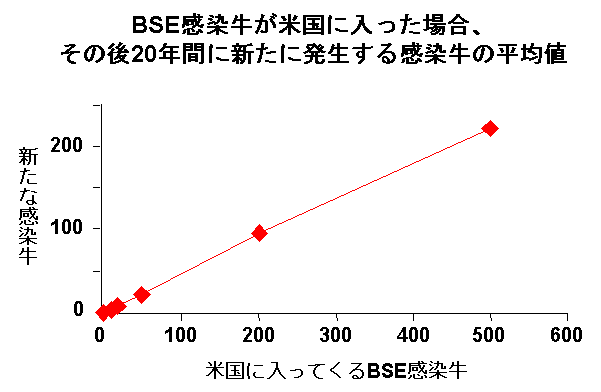
国内での羊のスクレイピーなどに起因する発生原因についても検討し、これもそれほど大きくはないとしている。
人への感染のリスクとして、95%タイル値で、20年間で牛がBSEに半数罹る用量(ID50)の170倍、平均値で34倍としていて、これはほとんどリスクゼロに近い。
そしてリスクを削減するための最も効果的な手段は、1) 英国などからの反芻動物やそれらの肉、骨のついた肉等の輸入禁止(1989年以降)、2)
国内での病牛組織のリサイクルの禁止(1997年以降)であったとしている。
今後感染に最も大きく寄与する要因は、1) 病牛の組織のリサイクル(前記「2)」についての違反)、2)
間違った飼料を与えること(豚の飼料を牛に与えるなど。因みに豚や鳥には牛の肉骨粉を与えることが許されている。)、3)
飼料のラベリングの間違い、4)
牧場で死んだ牛の処分、である。
人への感染に大きく寄与する要因は、1) 危険部位の処置、2)
とさつ場でのBSE牛の検出である(0.06%の検査)。
これらのモデルは、スイスの例で検証された(これは、ひどく強く印象に残っている)。
カナダでの発生後
2003年夏にカナダでBSEが発見され、George M. Grayらは報告書を少し訂正した。ただ、2001年の報告書では、カナダから75万頭の牛が入ってくるが、80%は直ぐにとさつされ、約2割が飼育されるとして、大きな問題なしとしていた。
この理由は、カナダでBSEが発生していないということだから、このルートでの前提は大きく変わったことになる。2003年の改訂された報告書では、計算はだいぶ違っているが、最終的なリスクが小さいという結論は変わっていない。
しかし、今回のBSE牛が、2001年の報告書で最も軽く扱われたカナダから入ってきたことは皮肉である。カナダとアメリカは、同一国と言ってもいいので、これは米国内で発見されても不思議でないことを示唆するものである。
また、2003年夏、カナダでBSE牛が発見された際、カナダ政府が最初に語ったことが、「米国から入った」とコメントし、大騒ぎになった。つまり、ここは同じ国とみた方がいい。ここがハーバード大学の報告書で弱い点だが、国内要因で米国が考えているほど、厳格な規制が守られていないというシナリオが必要だと考えた方がよさそうだ(既に、95%値などで評価されている)。
今回読み直して
今回読んでみて、ハーバード大学のリスク評価書が挙げた最悪ケースみたいな状況が、やや現実味を帯びてきたのかなという印象はある(つまり、不法にレンダリングが行われているなど)が、それがどの程度の比率かが、今後のポイントになりそうだ。
米国での死んだ牛の処理の管理や飼料の混入で、かなり改善しなければならない点があるとしても、ハーバード大学の評価枠組みの中にはこのことは既に考慮されている(あり得ないとは思うがみたいな書き方になっているが)。
全頭検査の要求はやめた方がいい
我が国は米国に全頭検査を求めているが、もし、全頭検査をしなかった時、どのくらいの大きさのリスクがあると考えているのだろうか?
もう少し科学的に、例えばハーバード大学の報告書にしたがって、このルートの危険性が高いから、これを検査すべし、リスクは1000万分の1以下にすべしというような要求はできないものだろうか?
国内でも、科学的な議論を無視し、経済性も無視して、いきなり心情的に「全頭検査」を決めたが、こういう費用のかかる方法をいつまで続けるつもりだろうか?
国内で科学的な議論を行わないから、その主張を外国に対して認めさせることも難しいのではなかろうか?もし、消費国の圧力で求めることができたとしたら、世界的な損失になる。貧しい人の食べる機会をとりあげることになることにも気をつけてほしい。
米国やカナダとの交渉も大事だが、それを円滑にかつ早急に終わらせるためには、まず、日本人に科学的な結論を納得させる努力と勇気が必要である。多分、米国との交渉でも裏では、全頭検査以外の方法につてい検討が行われているにちがいない。
そういう経過を明らかにしないと、「全頭検査をしないですます」となった時、また、米国に押し切られたみたいな印象を与える。
いずれにしろ、まず、日本国民に「全頭検査」の必要性がないことを説明すべきである。
最新情報
因みに、1月23日現在米国農業省の調査では、BSE陽性であった牛と同じ所から米国に入った81頭の牛の追跡調査では、27頭の居場所が確認された。
http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse_update01-23-04.htm
かつて中西が書いた文章(日経、あすへの話題、2001.10.23)
風評被害
狂牛病のことで風評被害という言葉が、とびかっているが、この用語は昔はなかったと思う。ここで言う風評被害とは、本当は危険ではないが、危険だという風評が広がり、消費者がその商品を忌避することによる被害のことを指す。
リスクマネジメントを専門にする私の立場から言えば、風評被害の頻発は、この専門が無用だという証明でもあるから、風評被害を防ぐためにどうすべきかについて、しばしば考える。
風評被害の原因として、行政機関の対応が悪い、情報を隠すから問題だ、そもそも消費者の安全を軽視しているという意見が出されており、それらは尤もだと思う。
しかし、そういう尤もな議論とは別に、風評被害を頻発させる新しい状況が出てきていると、最近つくづく感ずるのである。
リスク回避のためには必ずコストがかかる。無限のコストをかけることができる人はおらず、誰でもコストとの兼ね合いを考えて、コストが高すぎれば、そのリスクを我慢し、コストが低ければリスクを回避する。
日本のように商品があふれている社会では、消費者は危険かもしれぬという情報があれば、それを避けて、代替品を手に入れることが容易である。つまり、消費者は殆どコストを払わずにリスク回避ができる。
したがって、その情報があやしげでも、真偽を確かめるよりは、回避に走る。リスク評価を専門にする私でも、そうなりがちだ。しかし、このことによる社会全体のコストは莫大で、農業者、漁業者、商店などが廃業の危機に見舞われることもあり、徐々に食料安全保障もおびやかされる。
従来の議論も必要だが、もう一方で、消費者のリスク回避費用はゼロに近いが、その社会的な費用は莫大であるという新しい状況を十分認識した上で、対策について議論しなければ、風評被害の蔓延は防げないように思う。
雑感243-2004.1.20「コイヘルペス−病魚買い上げは妥当か?」
持続的養殖生産確保法
茨城県霞が浦で養殖のコイにコイヘルペスが蔓延していることが分かり、農水省は移動禁止(→廃棄→焼却)の措置をとった。同時に茨城県は、これらのコイを実勢価格の8割で買い取る方針を発表した。
私は、この「買い取り」という方針にどうも納得がいかない。
例えば、水田農家が防除を怠り、稲がいもち病で全滅したという場合に、それを県が買い取ってくれるであろうか?新しくおきた、山口県のトリインフルエンザの場合も、県が買い取るのだろうか?
BSEの場合に、国が補償金を支払った。これも納得できる話ではなかったが、まだ、国の対応が悪かったとか、そういう理由もあるので、補償に追い込まれてしまったのかなと考えていた。
ところで、この病気のコイを買い取る根拠法は何かと調べてみたら、持続的養殖生産確保法だという。この法律は、1999年に制定され、「伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずる」ことをその目的としている。そして、第9条には、損失の補償を行わねばならないとしている。つまり、買い取りの根拠はこの法律の第9条であった。
病気蔓延は事業者の責任ではないのか?
確かに、そういう法律がある。しかし、伝染病を見逃し、蔓延させたのはどう見ても事業者たる、養殖業者の責任である。このような補償を続けていいのだろうか?
もちろん、これだけの被害を受けたのであるから、生活援助とか或いは貸し付けとかがあるのは当然である。しかし、病気のコイを買い取るというのは納得できない。コイが病気に罹るのは、重大な経営リスクだから、もっともっと注意すべきことで、経営者の責任の筈である。
工業やサービス業での零細企業はつぶれても、県が売れ残りの商品を買い取ってはくれない。さらに、伝染病が蔓延するのを防ぐための措置は必要だが、それが、これだけの高額の補償となると、経営責任を問うという姿勢が欠けていて、とても納得できない。
BSE以後、農産物関係のこのような補償が度を超している。このようなことを続けると、いつまでも独立心が育たないのではないか。
怪しげな廃業の動き
最近の新聞を見ていると、さらに一部の養殖業者は、廃業するからとして廃業補償を要求している。霞ヶ浦町漁協の樽見軍司組合長が「処分補償と廃業補償をセットでお願いしたい」と要望した(朝日新聞茨城版2003年12月26日)。これに対し、橋本昌知事(茨城県)は、全業者の廃業を前提に「(補償を)霞ヶ浦の環境対策事業に盛り込めないか」としている(日経茨城版、2004年01月13日)。
つまり、こうだ。養殖は水質に悪い。だから、廃業補償を霞ヶ浦の環境対策事業費から出そうというのである。
霞ヶ浦の水質汚濁と養殖
養殖が霞ヶ浦の水質に悪い影響を与えていることは事実である。
日経新聞によれば、霞ヶ浦の水質(COD)に養殖が与える影響は7%であるとなっている。茨城県水質審議会霞ヶ浦専門部会中間報告(1981年)「霞ヶ浦の水質浄化の方策について」によれば、チッソについては養殖の寄与が12.6%、リンについては21.6%となっている。
水産や農業の寄与率は過小評価の傾向があるので、現実には、この数字よりもっと高いに違いない。しかも、この数字が発表されて以後、他の対策は進んでいるのだから、CODの比率で考えても養殖の比率は現状では20%を超えると考えていいのではなかろうか。
私も、霞ヶ浦の水質保全の点から考えると、コイの養殖をやめる、または、極度に規模を縮小することに賛成である。
しかし、今回の廃業には三つの点で疑問がある。
1)この廃業宣言は本当に実効性があるか?
2)これほどまでに、コイ養殖の規模を拡大させたのは誰でそれは、何故か?
3)廃業に対し、県が補償金を支払う根拠は何か?
現実の世界
1)いくら廃業宣言しても、養殖以外で生活できない人がでてくるから、補償金を使い切ってしまえば、また、養殖を始めるだろう。もちろん、法律的には免許がなければできないのだが、現実にはそれは問題にならず、既成事実が先行し、やがて本物の免許がおりてしまうというのが、今まで私が霞ヶ浦で見てきたことである。
2)コイの養殖廃止が水質汚濁解決の切り札になるのなら、何故、県は免許更新の際に、規模の縮小を指示しなかったのか?免許の更新は多分3年毎に行われるから、その度に許可量を少ずつ減らすことは可能だったのである。それをしなかった。
このような浅い湖で、かくも大量のコイの養殖をすることは非常識である。なぜ、こういうことになったか?それは、県がコイの養殖を奨励してきたからである。何のために?
霞ヶ浦の取水のための「水ガメ化」(湖の締め切り)で、自然漁業ができなくなる、それに対する反対をすこしでもやわらげるために、コイの養殖を奨励し、事業免許をだしてきたのである。
水質に悪影響を与えることは最初から分かっていた。今になってまた、水質問題解決のために廃業を促し、廃業資金を霞ヶ浦の環境対策事業費から出す?そんな!
3)橋本知事は、廃業資金を水質対策費として支払えないかという。あるラーメンやが汚水を流している。それを処理しない。だから、廃業を勧めた。そのために廃業資金を出した。こういう例は聞いたことがない。でも、知事はなぜ、これほどお金を払いたがるのか?
奇妙な残留塩素論争
コイヘルペスの出た霞ヶ浦の水を原水とする水道水の給水区域(私のいるつくばも含む)で、コイヘルペスの発生で、水道水の残留塩素を通常より高くしたか、しなかったかで、奇妙な論争がおきている。茶番劇としか言いようのない論争だが、ある種、市民運動とお役所の建前論の世界を、よく表現している論争でもある。暇なときにまた、触れるとしよう。
雑感242-2004.1.13「リスク不安と科学技術」
幸運な技術と不幸な技術
つらつらと考えて見るに、我々の周囲にはリスク不安が大きくて、その利用が極度に制限されている技術がある。もう一方で、リスク不安が囁かれながら、そのリスクに配慮することもなく、ただ新しい技術を売り込めばいいという姿勢で売り出され、受け入れられている技術がある。
前者の代表的なものは、原子力と遺伝子組み換え作物、もしかして、ナノテクノロジーもその仲間に入るかもしれない。後者の典型が、携帯電話やユビキタスコンピューティングと言ってもいい。
原子力が夢の技術とは思わないが、我が国のエネルギー状況と、今のような管理技術を考えれば、もう少し利用されてもいいと思うが、残念ながらリスク不安が大きく、原子力発電所の建設が市民に拒否される状況が続いている。
遺伝子組み換え技術は、さらに応用可能性の大きい技術であろう。そして、人への影響については、かなり調査が進んでいて、少なくともいくつか個々の作物について、当面大きなリスクなしという判断ができる程度になっている。しかし、個々の検討とは別に、遺伝子組み換え作物のすべてが十把一絡げにして、市場から閉め出されている(表示で認めるという形にはなっているが)。
最近、ナノテクノロジー(超微細技術)が脚光を浴びているが、すでに、市民団体などからナノハザードという言葉で、そのリスク問題が提起されているし、特に分子ナノエンジンは人間の細胞操作に使えることから、生命倫理との関連で問題が提起されている(2003年12月6日、朝日新聞)。
技術者や研究者は、新しい技術、良い技術を生み出せば、それが使われ、人々に福祉や喜びをもたらすと考えて、それにのみ邁進しがちだが、実は、このリスク問題を解決しなければその技術は利用されない。いくつかの新技術がおかれている状況からみて、このリスク問題は特別な技術だけの問題ではなく、すべての技術や物質にとって避けることのできない共通の問題であり、技術の行方を左右する決定的な課題である。
だから、技術の研究とそのリスク研究とは、常にセットで行われなければならないのに、そして、リスク評価結果と新しい技術はセットで世に出さなければならないのに、研究者や事業者は、いつもリスクの方は忘れ、ともかく新しい技術はいいですよと言って世に出してしまう。
そして、リスクが問題になると始めて、リスク評価の研究にとりかかるのだが、その時は大抵手遅れで、時間がかかればかかるほど皆のリスク不安が大きくなってしまう。そして、リスクよりもリスク不安という問題と格闘しなければならなくなるのである。
それでも、リスク問題を単なる不幸、巡り合わせが悪かったとしか考えず、なぜ原子力だけが攻撃されるのか(不幸な技術)、車のリスクがより大きいのにとか(幸運な技術)、何故塩ビだけ悪く言われるのとか(不幸な技術)、言って嘆いている。でも、それは違うということに、そろそろ気付くべきである。
要するに、リスク問題はすべての科学技術のなかで、その一部として常に対処しなければならない問題であるということを。もちろん、車は何故許されるの?携帯は何故いいの?ユビキタスコンピューティングなんて、いいの?という問題はある。
しかし、市民はずるいから、これらの商品の魅力が大きいために、リスクに今は言及しない、考えないことにしているだけであって、もう少し落ち着けば、問題は過去の分まで含めてでてくるのである。
むしろ、塩ビなどは昭和30年代に、リスクが問題にならず、どうしてあんなに売れたの?ということを考えた方がいい。今、そのつけが回ってきているのである。リスク評価とリスク管理はすべての技術や商品の問題である。まず、技術や科学、商品開発に携わる人は、このことを肝に銘じてほしい。
リスク不安
ここに一枚の絵を示そう。インターネットで不安という題で引いたらでてきた絵なのだが、これが丁度私の言いたいことをよく表している。この人の頭の中に三つの円がある。真ん中が赤、次が白、最後の一番大きな円が水色である。
実は、リスクにも三種あるように思う。
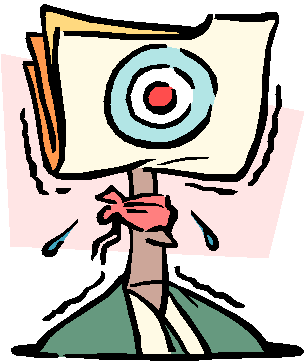 Microsoft® Office Online クリップアート
Microsoft® Office Online クリップアート
一つは実態としてのリスク(リスクの実像)、つぎが我々のような研究者や行政機関が安全率(不確実性係数)を考慮して想定するリスクの大きさ(規制リスクと名付ける)、最後が一般の人が抱く不安としてのリスクの大きさである(リスク不安)。
リスクの実像の半径をa、規制リスクの大きさをb、リスク不安の半径をcとする。
リスクの実像と言っても、リスク評価は予測が大部分を占めるので、誰にも本当の大きさは分からない。100年も経って見れば、実像(a)が「不安」(c)と同じだったということもありうるが、一応今の科学を使って予測できる大きさを、リスクの実像としておこう。
データが少ないとか、評価の枠組みが適切でないと、不確実性係数を大きくして規制値を厳しくするという方法をとっている。これが、(a)と(b)の違いである。一般の人は、それよりもさらに大きいリスク不安を持つことが多く、しかも、このリスク不安の大きさ(c)が国の政策決定に大きく影響する場合が増えている。
リスクに対応することの他に、リスク不安に対処するという考え方が必要になっている。それに対する処方箋は先手必勝しかないのではなかろうか。つまり、できるだけ早くリスク情報を出すことである。
新しいことがリスクにならないために
その技術開発に携わっている人を除けば、新しい技術は新しいというだけで「リスク不安」を大きくする。「新しい」というだけでリスクなのである。つまり、(a)と(c)の差が非常に大きくなる。だから、新しい技術を世に出す時には、必ずリスク評価の結果を一緒に出し、世に問うことが必要である。
新しい技術なので、そのリスク評価の枠組みや技術も新しくなければならないことが多いだろう。そういう事も含めて、リスク評価が必要なのである。我々は、今化学物質のリスク評価を行っている。しかし、よく考えてみると、他の技術や科学の分野でもリスク評価は必要な筈である。どうして、そういう研究部門を揃えないのだろうか?
たまたま、net上この図を見て、三つのリスクという着想を得た。これは、新年早々大きな収穫だった。
雑感241-2003.12.24「PRTRからの逃避」
最近工場を見学して帰ってきたCRM(産総研化学物質リスク管理研究センター)の研究員がそろって言うことがある。それは、PRTR対象物質をやめて、指定されていない物質に代替することが急激に進んでいるということである。つまりPRTR指定物質からの逃避である。
有害大気汚染物質規制でも同じことが見られる。
やや古いものだが、「有害大気汚染物質規制による関東圏の産業への影響調査報告書関東通商産業局 平成9年3月」という調査報告書があるが、その一部を抜き出してみよう。
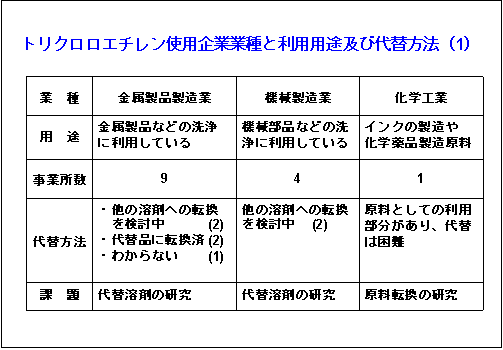
これは、トリクロロエチレンの例だが、代替溶剤の研究とか、検討を進めている事業所が多いという調査結果が出ている。問題は、規制物質から未規制物質への転換が本当にリスク削減に向かっているか、そのためのコストに見合うリスク削減効果を生んでいるかである。
自主管理で浮き彫りにされた問題
従前から、こういう問題点があるだろうとは想像されていたが、いつも結果のみ知らされるという状態であった。ところが、現在進められている「事業者による有害大気汚染物質自主管理」では、事業所が自主管理削減目標を作り、その削減過程を委員会で報告する(check&review)ので、進行過程で問題が明らかになってきた。
自主管理目標の対象物質のひとつに、ジクロロメタンがある。事業者の報告によれば、ジクロロメタン削減のために、代替洗浄系が使われている。それは大きく分けると三種あり、水系、石油系、塩素以外のハロゲン系(臭素かフッ素)になる。
それぞれ、代替物は本当にbetterかという吟味が必要だが、委員会で問題になったのは1−ブロモプロパンであった。ジクロロメタンより良いという研究報告書がある一方で、委員の中からは「それはやめた方がいいという意見」も出された。
この問題については、やがてまとまった意見を出そうと思っているが、ここではそのこととは別に、規制が始まる→代替物に替えるという場合に、本当にリスク削減につながるか否かについて、迅速に判断する方法について考えたい。
こういう場合のリスク比較には注意が必要
リスク評価をし、リスク比較をすればいいではないかと考えるかもしれない。しかし、一般的にはリスク評価には非常に時間がかかるし、また、このようにこれまで使い古された化学物質(この場合ジクロロメタン)と新規にでてきた化学物質(1−ブロモプロパン)を、通常のリスク評価の手法でリスク比較することは意外と難しい。
何故か?
1)通常のリスク評価では(遺伝子損傷性のある発がん性物質でなければ)、ハザード比(HQ)を尺度に用いる。つまり、
HQ=(一日用量)/(一日許容用量)
一日許容用量=(無毒性量)/(不確実性係数)
で、定義されたHQの値を計算し、HQが1以上であればリスクあり、1以下であればリスクなしと判断している。(ここで、許容用量とは、ADIまたはTDIである)。
HQを用いたリスク比較が難しいという一般的な問題がある。
2)蓄積されている有害性データの量や質に違いがあり、不確実性係数が大きく異なってしまうことが多い。こういう場合、TDIは(NOAEL)/(不確実性係数)であるので、NOAELよりも不確実性係数に大きく影響されてしまい、TDIにお対する比であるハザード比(HQ)で比較することで、進むか退くかの判断がとても難しい。
<水道水質基準値の例>
参考のために、以前、WHOが提案している水道水質に関するガイドライン値で、許容量値(TDI)、ひいては水道水質基準値が、不確実性係数の違いのために大きく異なってしまう事例を挙げたことがあるが、ここにそれを再掲する。
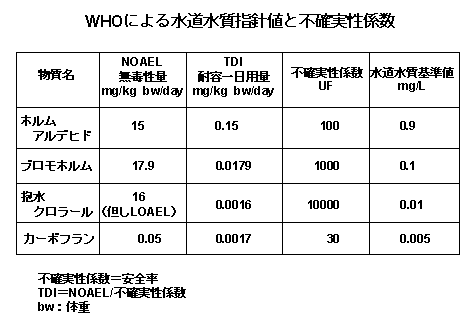
この表に示された上から三つの物質は、NOAEL(無毒性量)またはLOAEL(最小毒性量)はほとんど同じであるにも拘わらず、TDIは100倍も違っている。この差は、不確実性係数の取り方に影響されている。最後の行にカーボフランの値を示した。これは有害性が強いことが知られている農薬で、そのNOAELが0.05であることからも、そのことが伺える。ところが、UFが30と非常に小さいために、TDIは抱水クロラールとほぼ同じである。
カーボフランは、人への影響も調べられているためにUFが小さく、抱水クルラールは動物実験のデータも少ないために大きなUFをとっているからである。
<これと同じことがおきる>
古くから使われていて、有害性も分かっている物質(UFが小さい)と新しい物質でデータが少ない物質(UFが大きい)のリスクを、とりあえず手早く比較し、代替物を選択すべきか否かを知るためには、このようなTDIを用いてHQを尺度にリスク比較はできないのである。
3)新規物質の毒性が見えない場合もある。2)の問題は、新規物質のリスクが過大に評価される問題だが、逆に新規物質では問題が見えず、リスクを見落とすという問題がある。
こういう場合に、どのようにリスクを比較するかというのが、今日の主題である。
ジクロロメタンとブロモプロパン
もう一度、ジクロロメタンとジブロモプロパンの問題にもどろう。
2−ブロモプロパンも含めた有害性比較の表を示した。表の作成者は名古屋大学医学部教授竹内康浩さんである。健康開発1999:4(3)、20-25頁の表1の一部である。
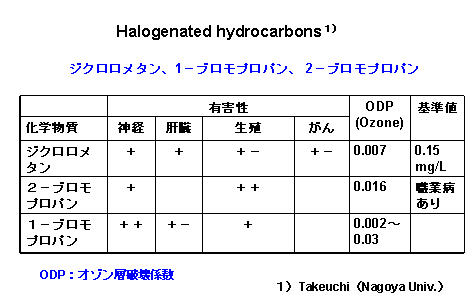
この表に示した2−ブロモプロパンは、フロンの代替物として使われて工場労働者に生殖障害が出て、使用禁止になっている。
こういう場合に、私が提案する方法は、まずこれまで人間への影響が分かっている物質と症状(生殖障害と神経影響)、或いは確定しているエンドポイント(発がん)を取り出し、それと関係するバイオマーカ(酵素レベルの反応)または、動物実験での反応を探しだし、それらのNOAELを比較するという方法である。
つまり、不確実性係数は使わない。もちろん、これは正式なリスク評価ではない。しかし、少なくとも上に挙げた1)2)3)の問題をクリアしつつ、代替物がいいか悪いかを比較できる方法である。この作業は進行中なので、具体的な報告は後日になる。
PRTR指定物質の場合―HQより、NOAEL比を使う方がいい
PRTR指定物質から、とりあえず逃避して、非指定物質に替えるというのも、法律の目的に反した行為である。もし、代替物質がいいという保証がないのなら。
そこで、どのように検討するかであるが、ジクロロメタンの場合よりさらに、データがなく、かつ急を要するであろう。こういう場合は、HQでの比較より、UFを使わずにNOAEL比を比較に用いた方がいい。
NOAEL比とは、中西の作った用語だが以下のように定義する。
NOAEL比=(用量)/(NOAEL)
HQでのTDIの代わりにNOAELを使うものであり、米国でしばしば使われるMOE(暴露マージン)の逆数である。
PRTR指定物質についても、代替物質を使う場合には、代替物の方がいいというこの種の根拠を求めるべきだと思う。それを業界団体でとりまとめ、また、どこかでcheckするシステムができるといい。その場合、HQでの比較は危ないということを知ってほしい。
次回upは、1月13日(火)の予定。
トップページに戻る

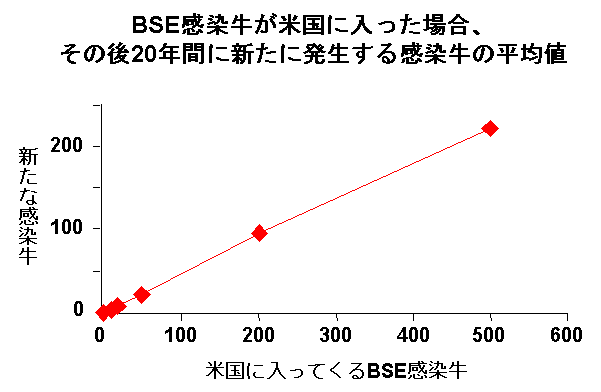
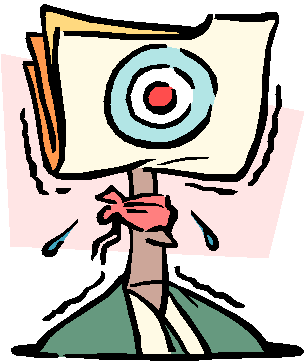 Microsoft® Office Online クリップアート
Microsoft® Office Online クリップアート