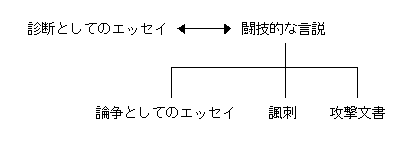�G��235-2003.10.14�u�_�C�I�L�V�����
�\RDF�Ə���ٔ��\�v
�N���[�Y�A�b�v����̕���������
9���͂��߁A���Ō`�R���iRDF�j���d���Ŕ������̂��N����l�����S�����B�l�X�Ȗ��������ɋ���ł����̂Łu�����A����ς�v�Ƃ��������ł����邪�A����ɂ��Ă��\�z��葁���A�\�z���傫�Ȗ�肪�o�Ă��Ă��邱�ƂɁA�������Â��������Ƃ����v��������B
���̌̕�A���ׂĂ݂�Ɗe�n�łЂǂ���肪�N���Ă���B�������Ȃ�RDF���u���ݏ����̍L�扻��i�߂��Ō����I�Ȏ{�݁v�Ƃ��ĕ⏕�������邱�Ƃɂ����̂�1993�N�����A�ꋓ�ɍL�����y���n�܂�̂̓_�C�I�L�V�����ʑ[�u�@����1999�N�Ȍ�ł���B
��T�ANHK�̃N���[�Y�A�b�v�����RDF���d�ɂ܂�鎖�̂ɂ��ĕ��Ă����B���̕����Ă��āA��̂��Ƃ������������B
�P�j�ЂƂ̓R�����e�[�^�Ƃ��ĂłĂ���A�����́u���Lj��S���ɂ��Ă��炩���ߌ������Ȃ������̂����v�Ƃ������C�y�ȃR�����g���Ă�����Ă��܂����B
�Q�jRDF�{�݂ō�ƈ������Ȃ���Ȃ�ʉߍ��ȍ�Ƃ����āA�u���݂��o���S�Ă̐l�����̎��Ԃ��v�����̐ӔC�Ǝv���Ă݂Ăق����Ǝv�����B
�Ȃ����C�y�Ȕ����Ǝv����
RDF�̓������Ȃ�����
RDF���������}���ɍ̗p���ꂽ�̂́A�܂��Ƀ_�C�I�L�V����̂��߂ł������B�_�C�I�L�V���͊댯�A������������邽�߂ɂ͑�K�͏ċp�F�������߁A���̂��߂ɂ͏����ȂƂ����RDF�ɂ��āA�傫�ȏċp�F�܂ʼn^�тȂ����B
RDF�Ȃ�A���ɗǂ��i�_�C�I�L�V�����o�Ȃ�����j�A���T�C�N���\�Łi���݂�R���ɗ��p�ł��邩��j�A�G�l���M�[������������i�������ǂ��A�d�͂邱�Ƃ��ł���j�Ƃ������ƂŁA�����̕⏕��������ꂽ�BRDF�͏z�^�Љ�̖͔͋Z�p�Ƃ��������Ő������ꂽ�B
�����Ȏs�����́A���K�͂̏ċp�F�ɂ͕⏕�������Ȃ����A���܂ł̏ċp�F�ł̓_�C�I�L�V���̌������K���l���ł��Ȃ�����A�ǂ����Ă���悤��RDF�ɑ������̂ł���B
�����̐l��RDF�̈��S���ɂ͋^��������Ă����Ǝv���B�s���^���̒��ɂ́ARDF���݂ɔ������Ƃ�����������B�������A���ǃ_�C�I�L�V���K���l�����Ȃ��A�܂��A������Ƃ��Ă��s�����ċp�F�̌��݂�F�߂Ȃ��Ƃ����ł́A�����Ȏs������RDF�̓������Ȃ������̂ł���B
���S���̌����͂����̂ł���i�_�C�I�L�V�����͂܂��Ǝv�킹��ꂽ�j
���ɂȂ��Ĉ��S���̌������Ȃ��������Ƃ����ƌ����Ă��A���̂Ƃ��́A�_�C�I�L�V���Ő��܂�Ă���q���Ɉُ킪���邩������Ȃ��A�݂����ȕƐ�`������A�N���������RDF���܂����Ǝv�����̂ł���B
�܂�A���S���̌��������Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ��B�����̂��B�F�A�S�̒��Ŕ�r���Ă���̂ł���B�����āA�_�C�I�L�V���̃��X�N�͂ƂĂ��Ȃ��傫���ƐM�����܂���Ă��邩��A���͏����댯�ł��d�����Ȃ��Ǝv�����̂ł���B
�����āA����ȊO�ɓ����Ȃ��悤�ȍ��̖@����K�����ł��Ă��܂�������ł���B�_�C�I�L�V�����[�@�Ə��^�ċp�F�ւ̕⏕���̔p�~�ł���B
���̓���������̂́A�_�C�I�L�V���̃��X�N�͐l�ނ̐������������悤�Ȍ��r�Ȃ��̂��Ƃ������_��������w�҂�W���[�i���X�g�A����𗘗p�������ċp�F���[�J�[�A������x�������ċp�F���[�J�[���r�C�X�g�̊w�ҒB�Ƌ������Ȃ̖�l���Ǝv���B
A�������A���̂Ƃ��̓_�C�I�L�V���̗L�Q���ɋC���Ƃ��Ă�������A�������������낻���ɂȂ������炢�̔��Ȃ͂��Ăق����B
�ł́A�ǂ����邩�H
�ł́A�������s�����͂ǂ�����������H�����ȂƂ���͏������Ȃ�ɏċp�����炢���Ǝv���B�ł��邾�����S�R�Ăɓw�͂���B���̂��߂ɂ́A�T3���A���^�]�ŁA�c���4���͋x�݁A�݂����ȉ^�]�������炢���B
�������ɁA����͏T7���A���^�]�������͈������A������x���������Ȃ��Ǝv���B�厖�Ȃ��Ƃ́A���̔�p�����������ŏo�����Ƃ��B��������A�����T�C�N���̒m�b���o�Ă���B
���������A���݂����������ɂ��Č����悭���d�����肷�邱�Ƃ́A���Ȃ��Ȃ����Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B�������グ�邽�߂́A���Ƀo�[�W���̌���������ł���ꍇ�͂��܂��������ǁA�����łȂ��Ɠ���B�v�����g�̉^�]�Ƃ��Ċ댯�ɂȂ�B
�̘̂b�ł���
��όÂ��b�ŋ��k�����A1970�N��̏I��荠�A���̓N���[�Y�h�V�X�e���Ƃ������@��Nj����Ă����B�r���������Ɏg������A�ė��p�����肵�Ĕr�����o���Ȃ����Y�H���ł���B
���̂��Ƃɂ���āA�H�Ɨp���̎g�p�ʂ������������A���ɏo��L�Q���̗ʂ����������B�������A100%�������܂��݂����Ȃ��Ƃ�錾���āA�����ڎw���ƃv�����g�Ƃ��ĂЂǂ���Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ��o�������B
����H��ł̑̌�
�����A���͐���d��@�J�Z�C�\�[�_�����H����ǂ������Ă����B������o���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�N���[�Y�h�V�X�e�����̗p����Ă����B����H���K�˂��ہA���̍H�ꂩ��ٗl�ɑ��ʂ̐����C�����o���Ă��邱�ƂɋC�������B
�H��ɓ���Ȃ�A���́u���́A�����C���ł����H�v�ƕ������B�l�X�Ȃ��Ƃ�̌㕪���������Ƃ́A�r�������ׂčė��p���邱�Ƃ������������i���Y�ʂ̕ϓ��ȂǂŁj�A��������ƁA�����ł͔r�������̎{�݂͂����Ȃ��Ȃ��Ă�������A���C�ŕ��U�����Ă����B�����āA���̏��C�ɂ��Ȃ�̐��₪�܂܂�Ă����B
���������\�肳��Ă��Ȃ��r�o�H��������ł���B�܂��A���ꂾ���łȂ��A�M���x���펞�ϓ����āA�����I�ȃG�l���M�[���p������A�M�o�����X���Ƃ�ɂ����̂Ŏ��ɂ͉��x���オ�肷�����肵�Ċ댯���Ƃ����b�����B
�Ⴂ���ɁA�N���[�Y�h�V�X�e���̓����@�����܂ꂽ���́A�p�����̍ė��p�Ƃ��M���p�Ƃ��́A�قǂقǂłȂ��Ɗ�Ȃ��Ƃ������o�������Ă���B���ɉ����āA������x�̂Ă�E�C�Ɗo�傪�K�v���Ǝv���B
�z�^�Љ�Ƃ��A�[���G�~�b�V�����Ƃ��A���O�Ƃ��ڕW�������ƁA�Z�p�̊댯���������Ƃ����ƂɂȂ肪�����B�����̋Z�p��������ƌ����Â����Ȃ��Ɨǂ����X�N�Ǘ��͂ł��Ȃ��B�ǂ����Ƃ̗��ɂ́A�K���������Ƃ�����B
����_�C�I�L�V���i��
�@�u���o�G�R���W�[�v2003�N11�����ɁA�u�e�����i�ׂōō��ق������٘_�J���A�_�C�I�L�V���Ŕ_�����t�]���i���v�Ƃ����L��������B
�@�����ŁA�ǂ����Ƃ���悤�ȃG�s�\�[�h���������B
�������W��
1999�N2��1���̃j���[�X�X�e�[�V�����ł́A�ȉ��̂悤�ȃt���b�v���o���Ƃ����B
|
�u��̃_�C�I�L�V���Z�x�v |
| �S���i�����Ȓ��ׁj |
0 �` 0.43 pg/g |
| ����i���������������ׁj |
0.64 �` 3.80 pg/g |
����3.80 pg/g�Ƃ����l���u�͂��ς��́v�Ɛ�������AVTR�Ȃǂ�ʂ��ăz�[�������Ƃ�����ۂ�^�����̂����A�{���͂����������B
������̋L����
������āA����ȉ��̂悤�ȋL��������B
�g�����̊W�҂�98�N�ɋ{�c�G���ۓ��w����������Y���̃_�C�I�L�V���Z�x�𑪒肵���ہA4pg
���o������������ł����B������A�u�ۓ��w�̒����� 4pg
���o�Ă���ȏ�A3.8pg
������Ǝ����҂��v���Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��傤�v�ƌ����B
�����āA�u�\�̏���̐��l�� 0.64�`4 pg/g �Ƃ��A�������������Ɛۓ��w���ׂƂ���Ă����p�[�t�F�N�g�������v�ƕٖ�����B�h
���̋L���͓�̂��Ƃ���������B
��́A���� 4pg �Ƃ�������������������A�ŏ����� 3.80pg
���Ǝv�킹��Ƃ����Ӑ}�ŕ��Ă������ƁB������́A�Ō�͋{�c����̐ӔC�œ������������Ƃ������ƁB�|���ˁB
�G��234-2003.10.6�u�G�b�Z�C�Ƃ͉����H�v
�_���Ƃ��ẴG�b�Z�C
�C���^�[�l�b�g��Řa�����p���ɁA�܂��p����a���ɂ��Ă����T�C�g������B����A�������������u�G���v�̕��͂����āu�p���ɖ|��v���N���b�N������A�����ǂ���ɉp�����o�Ă����B����ȕ֗��Ȃ��̂������Ŏg����̂��ƁA�Ђǂ����S���Ă��܂����B
�@
�����ł́u�G���v�̉p��́AMiscellaneous Impressions �ƂȂ��Ă����B�l�X�Ȉ�ۂƂ����悤�ȈӖ��ł���B���Ȃ�ǂ����Ȃƍl�����̂��AEssay as a controversy�ł���B����A����_���Ƃ��ẴG�b�Z�C�ƂȂ�B����ɁA�Ӗ���t��������A���Ȃ�������_���ɂ��U������A�m�I�S��I�����Ƃ����Ƃ���ł���B
�u�������v�Ɉʒu����
Essay as a controversy�Ƃ�����́A�������O�ɓǂu�G�b�Z�C�Ƃ͉����v�Ƃ����{�̉e���������Ă���B�s�G�[���E�O���[�h�A�W�����E�t�����\���E���G�b�g���A���V�a�`��u�G�b�Z�C�Ƃ͉����v�i�@����w�o�ŋǁA2003�j�ł���B
�@
���̖{�̒��ŁA���҂̓G�b�Z�C����ϓI�Ȃ��̂Ƌq�ϓI�Ȃ��̂Ƃ́u�������v�Ɉʒu������̂Əq�ׁA�T���g���̕\���Ƃ��āA�u�_�ؓI�ȖړI��������A�t�B�N�V�����ł͂Ȃ��U���v���A�G�b�Z�C���Ǝb��I�Ȓ�`�����A���̒�`���̘_���Ŋ�b�Â��邱�Ƃ��A���̖{�̖ړI�Ə����Ă���B
���`�}
�����āA�ނ�͈ȉ��̂悤�Ȏ��`�}���o���B
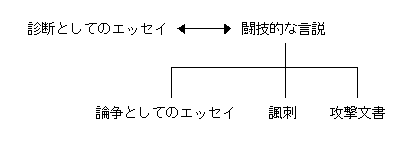
�����ŁA�G�b�Z�C�͓�ɕ������B�u�f�f�Ƃ��ẴG�b�Z�C�v�ƁA�u�_���Ƃ��ẴG�b�Z�C�v�ł���B��҂́A���Z�I�Ȍ����̒��̈�Ƃ��Ĉʒu�Â����A���h��U�������Ƌ�ʂ����B
�@
�u�f�f�Ƃ��ẴG�b�Z�C�v�́A�����m�F�Ƃ������g���b�N��W�J������̂ŁA�Љ�ɍL���F�߂��Ă���펯����{�ɂ�����̂ł���B
���̕������猾���A�f�f�Ƃ��ẴG�b�Z�C�͘_���Ƃ��ẴG�b�Z�C�Ƃ͑S���قȂ�A��҂����G�b�Z�C�̐_���ƌ�����̂�������Ȃ��B
���Ɉ��p���镶�͂͂ƂĂ����͓I�ł���i56�Łj�B
�u�m���ɁA���_�Ƃ��ẴG�b�Z�C�͍U���I�ȈӐ}��Ə�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A����͕��h��U�����������j���A���X�ɕx��ł���A���Z�I�Ȍ����̓��ꐫ�̂Ȃ��ɂ���ɃA�C���j�[�I�ȕs���a����[�����X�ȋ���������B
���̃G�b�Z�C�́A���e�s�ׂɂ�����s�����ɂ܂Ŏ��邱�Ƃ����肤��Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ɏ���̌��V�Ԃ�ɑ��Ă����A���Ț}�̈�˂��܂����邱�Ƃɂ���āA���̓{������炰��̂ł���B����͂悭���̋ߑ�I�ȏ����琶�܂�Ă���̂����A���̏��͂�����̌n�̗����������̂ł����āA�����ɂ̓G�b�Z�C�X�g���鎩�����g�̂��߂ɍ\�z�������Ǝv����������Ȃ��̌n���܂܂ꂤ�邾�낤�B�v
�z�[���y�[�W�̓ǎ҂́H
����A���ŊJ���ꂽ���w�V���|�W�E���̍ۂɁA���̃z�[���y�[�W�̓ǎ҂͂ǂ������N��w���Ƃ������₪�������̂����A�������̂��߂����ɗ��̂��p���������A�������ɏI������B
������m�ȔN��w��E�Ƃ������锤���Ȃ��B�������A���锽�����画�f���āA���������猤���ҁi��w�⌤�����j�A�s���@�ւ̐l�i���ɉ����ցj�A�W���[�i���X�g�i���炩�̔��M�ҁj�A��Ƃ̕��A�w���Ƃ����������ȂƎv���B
���ʂł͈��|�I�ɒj�ł���B�N����A���̂Ƃ���Ɋ���e-mail���画�f����ƁA30��㔼����40��̐l���ł������悤�Ɏv���i���m�ɔN�������킯�ł͂Ȃ����A�|�W�V�����Ȃǂ��画�f���āj�B
���́Ae-mail �A�h���X���z�[���y�[�W��Ɍ��J���Ă��Ȃ��̂ŁAe-mail���o���ɂ����Ǝv�����A����ł����낢��T����e-mail��͂��Ă����B���������l�̐��̏����Ō����ƁA�����ҁA�����ցA�w���̏��ł���B��Ƃ̕������e-mail�͔��ɏ��Ȃ��B
���̒��ŁA�����s�v�c�Ɏv���̂́A�O���ŕ����Ă�����{�l�����ҁi�@���APD���܂ށj�����e-mail�����Ȃ�̐��ɂ̂ڂ邱�Ƃł���B�䗦���l����ƕs�v�c�ȂقǑ����B��T�i���Ȋw�j�ɂ��Ă��h�C�c�̃V���c�b�g�K���g��w�ŏ�������Ă�������炲�ӌ������A���̑O�̏T�i�����f�j�ɂ́A�n�[�o�[�h��w���O�q���w���Ō�������Ă���������e-mail�Ō뎚���w�E���ꂽ�B
�����A�G���̉p��\�L�͉��ɂȂ邩�Ȃƍl�������������́A�O�������e-mail����������ł���B
�G��233-2003.9.29�u���Ȋw�̓y���z�����߂Ɂi���̂P�j�v
���Ȋw������ŋ߂̋t���ɂ���
9��10���ɁA���䎊�����Ấu���w�V���|�W�E���v���J���ꂽ���Ƃɂ��ẮA���łɏ������B���������ŏ������Ƃ��邱�Ƃ́A���w�ł͂Ȃ����Ȋw�ł���B�ǂ����Ⴄ���ƌ����A�Z�������ɂȂ炸�A����폃���Ɋ����ۂ�ǂ������镔��ƌ����Ă�������������Ȃ��B
�@
�䂪���ɁA���w���i�����w���Ƃ��A�l�Ԋ��w���Ƃ��j�͑������A���Ȋw��{�C�ł���Ă���w�ȂƂ������Z���^�[�Ƃ����͖̂{���ɏ��Ȃ����A���Ȋw�ł̋Ɛт����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@
1960�N��㔼����1970�N��ɂ����āA�����ɗ���݂Ȃ����r�Ȍ��Q��Q���o���������߂ɁA�܂��A���y�������Y�ƂƊ��ۑS�Ƃ̒��a��������������ɁA���Q�h�~�Z�p�̕���ł͂Ő��E��̃��x���ɂȂ����B
�������A1970�N��㔼����Ăъ����ւ̊S������A�����҂��������Ă������B�����āA�������Ȋw�Ȃǂ�߂悤�Ƒ�w�̋����������n�߂����A�I�]���w�̖���A���g�����i���O�Ƃ��Ă͐������l���������j�A����ɂ͒~�ϐ������̐����ւ̉e���┭�������̐l�̉e�����N���[�Y�A�b�v����āA�Ăъ���肪�傫�Ȓ��ڂ��W�߂�ƁA�܂����W�̌����҂��������B�܂��A���y�̋����������āA�p������肪�[���ŁA�p�����̌����҂͂��Ȃ葽���i���{�l�͔p������肪�D���݂����j�B
�����āA�ɂߕt���͊��z�������ƃ_�C�I�L�V���i������A���z�����������A����肪�������j�̑呛���ŁA���A���É������邪�A�����ɂ��̖��Ŋ��Ȋw�����ɂُ͈�Ȃقǂ̑��z�̌�������ꂽ�B���܂́A���̂��߂ɁA�傫���M�p�������A����픽����������悤�Ɏv���B
�u�����Ă��������ł͂Ȃ����H�v�u���ꂾ���̌�����g���ĉ������������̂��H�v�u���͂��ׂĂɊW���Ă���̂ŁA���ʂȂƂ��낪�����̂ł͂Ȃ��v�u���Ȋw�ł͂Ȃ��A���Y�Z�p�ɂ����A���������̂��߂̗\�Z���g����ׂ����v�Ƃ��������̎~�ߕ����L�������B
���z����������
���z�������A�_�C�I�L�V�����������flame up�͂Ђǂ����̂ŁA�ǂꂾ�����ʂ̉��w�����ł����Ă��A�~�W���R�̂Ђ����Ȃ����Ă��A�����͐l�ނ��łт�ƌ����̂����炠����Ă��܂����A�s�v�c�Ȃ��Ƃ����A����ȗ��R�ő��z�̌�����o�����Ƃ������ł���B
���������Ђǂ����痧�������āA�n���őn���I�Ȋ��Ȋw��i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�M�p�������Ă���̂ƁA�h��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ɗ����ł͂Ȃ��݂����ȕ��͋C���o�Ă���̂ŁA�n���Ȍ����Ɍ�������ꂸ�A�������肷��Ƃ��̑�w�Ɩ@���̗���̒��ŁA���Ȋw�͂��キ�Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
���Y�Z�p�̂��߂̊�����
�܂�A���̂��߂̌�����̑唼�́A�����Ƃ��Ẵo�C�I�}�X�̌����A�R���d�r�̌����A�O���[���P�~�X�g���ƌ�����V�������w�����̌����A���ۑS�ɗL���ȃi�m�e�N�A�r�K�X�����s�v�Ȏ����Ԃ̃G���W���̌����Ƃ����悤�ȁA����ΎY�ƋZ�p�̂��߂̊������ɗ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B
����́A����CP�icleaner production�j�ƌ����Ă�����̂ŁA���������̂��߂ɕs���ȋZ�p������A���̕��ʂɌ����J����������Ƃ͈������Ƃł͂Ȃ��B
�������A�����́g�����͊��̂��߂�ڎw���Ă����h�Z�p�J�����^�Ɋ��������̕��Ɍ������ۂ��́A���͖��m���ȂƂ��낪����B�ǂ����ŁA�����̋Z�p�̎g������������̖�肪�K���N���邵�A���e���͑��ʓI�ł��邩��A���A���łȂ��Ǝv���Ă��邱�Ƃ��傫�ȉۑ�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�����B
�����̕����������߂�l���A�������Ɉ����A�����ǂ����ɂ��āA���f�͂������Ă���Ƃ͌����Ȃ����珮�X�A��Ȃ��B�����̌Œ�ϔO�ŁA�������ɏ]�����A���헪���߂�̂��w�ǂȂ̂ŁA�{���ɑ��v�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B
�Ⴆ�A��R�܂́A�L�f���������g��Ȃ���Ί��ɂ₳�����ƌ��߂ĊJ�����Ă��邵�A�L�@���w�����̓G�l���M�[�����Ȃ���Ί��ɂ悢�Ƃ������z�ł���Ă���B����ꍇ�ɂ́A�����g��Ȃ���Ί��ɗǂ��������A���f������Ȃ��Y���͊��ɂ悢�Z�p���Ƃ����A�q�����݂��m���Ɣ��f�ł���Ă���B����́A���̌����҂�o�c�҂̌l�������ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ���̂��ƌ����Ă��邾���ł���B
�����̕��������˂�check�ł���̐����K�v
�������ɗǂ��Ǝv���ĊJ�������Z�p���A��Ɋ��������̕����Ɍ����悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�O���Ɋ��Ȋw�Ɋ�Â������f��Z�p�̎Љ�I�ȉe������������Ȋw�������āA���̌��ʂ���ɁA�Z�p�̕������Ɏ��~�߂�������̐����K�v�ł���B���Y�Z�p�Ώd�̊������́A���ۑS�v�z���炢��E���邩������Ȃ����ʂ������Ă���A�����Ȃ�Ȃ����߂̂���܂ʒ��ӂ��A���͕K�v�ł���B
���Ȋw�̂��̂܂���b
���̂��߂ɕK�v�Ȍ������A�Ƃ肠�������n�����Ɍ����ďq�ׂĂ݂�ƁA���̊�b�́A���ω���������Ȋw�ƌ�����B����́A�ϑ����A�ω���������A������������A�e���̒��x��]������A�����⑼�̒n��̉e����\������A���������Ȋw�ł���B
�����K�����ڂł��鐅��Z�x�́A����I�Ɋϑ�����ND�̋L�^�������Ă��邪�A�������������ł���Ă���悤�ȃ}���l���̊ϑ��ł͂Ȃ��B�����������邽�߂̊ϑ��ł���B�����������邽�߂ƌ����Ă��A��{�����C�̂���d���ł��邱�Ƃɂ́A�ς�肪�Ȃ��B�����A�ϑ������ɏI��炸�A�]�������A�\�����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ǂ��������삪�K�v���H
�ǂ���������ŁA�������������̂��߂̊ϑ��A�]���A�\���̌������K�v���H
�@��C���A�A����i���Ԍn�Ɖ��w�����j�A�B�C��A�C�C�ہi��_���Y�f�A�t�����j�D�쐶�����A�E�A���Ȃǂ̐��Ԍn�A�F�C�m�i����ނ̐��Ԋ܂ށA���w�����j�A�G�A�W�A�A�H��ɁA�k�ɁA�����[�g�Z���V���O�Ȃǂł���B
���̒��ŁA�C�͊������܂������Ă���悤�Ɏv���B�����k��̋C��V�X�e�������Z���^�[���A�펞�Ď������Ȃ���A�V�~�����[�V�������s���Ă��邵�A���x���̍����_�����o���Ă���B�t�����́A�������t�H���[���Ă���B
�A�ɂ��āA���i�̒��������s��w���A�z�K�ɂ��ĐM�B��w���A�F�ɂ��ẮA���Q��w���p���I�Ȓ��������Ă��邪�A�K�͂͏������B�D�ɂ��āA�k��ɏ����j������B�H������B�\���Ƃ͌����Ȃ����A�����͂���B
�������A����ȊO�̔ԍ��̕���̌����́A��w�̌����҂̌l�I�ȓw�͂Ɏx�����Ă��āA�������Ă����������Ȃ��A���⍡�ł��p���I�Ȍ������Ȃ��ƌ����Ă�������������Ȃ���Ԃł���B�܂��A�p���I�Ȋϑ������Ă��鏊�ł��A10�N�Ȃ�̌X�������邱�Ƃ��ł��錤���͖ő��ɂȂ����A�V�~�����[�V�����Ȃǂ��ׁX�ł���B�ǂ̑�w�ɂ������悤�ȍ\���łP�l�Q�l�̌����҂����邪�A�܂Ƃ܂������̂͂Ȃ��B
���Ȋw�̊�b���w�ŕ��S����̐���S���ɍ�낤
���������Ɏ��������Ƃ́A���Ȋw�Ƃ��Ăǂ����Ă��K�v�Ȃ��Ƃł���B������s�����߂ɂ́A�d�_��w�܂��͌����������߁i21���ICOE�̊��Ȋw�ł݂����Ɂj�A5�N�`10�N�Ԃ̌�����ƒ������ۏ��A���̃��x���̊ϑ��A�]���A�\�����ł���悤�ȑ̐����\�z�ł���悤�ɂ��邵���Ȃ��悤�Ɏv���B
���Ȋw�Ƃ����̂́A�܂��A�������������⌤���������āA���̏�ɉ������ׂ����̋c�_���n�߂�ׂ����Ǝv���B
�܂��A����������b�����邱�Ƃ��A���w�̒��j�Ƃ��ċ@�\���A���w����Ă邱�ƂɂȂ�̂��Ǝv���B
�����̐l���x�����Ă���悤�ɁA����̃A�W�A�ł̊����͐[���ɂȂ邾�낤�B���{�ɂ͌��Q��Z�p�̒~�ς�A���������ԃG���W���̋Z�p������̂ŁA���̓_�ł́A�����̍��������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�������A���Ȋw�œ��{�ɂ߂ڂ������ʂ����邾�낤���H
�������Ȋw�̖�肩�Ƃ������̔����┭�z�́A��ɉ��Ẵ��b�Z�[�W�𗊂�ɂ��A������܂Ƃ��Ɏ~�߂āA�Ђ�����Z�p�J���Ɏ��g�ށA�������������������{�ł���Ă��邱�Ƃł���B����ł����̂��H
�䂪���̊������́A�����Ȃ��đ̂������鏉���̃��{�b�g�̂悤�Ȏp�ɁA���ɂ͌�����B�̎��I�ɂ́A���Q�����N���������Ǝ��Ă���悤�ɂ��v���B�������ɂ������A�����N���肻�����ɂ��āA�A���e�i�┻�f�͂������ʂ܂܁A�u���̎��_�v�Łu���ɂ悢�Ɨ��z����Ă��邱�Ɓv�̒B����簐i���Ă���B���ɗǂ��Ƃ͂���ȂɒP���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ɂ��S��炸�ł���B
��w�̐v�}
�����̑�w���A�Ɩ@���ɂނ��đ�w�̐v�}��`���Ă���Ǝv���B����A�����������Ȋw���K�v���Ƃ������Ƃ��l���Đv�}��`���Ăق����B
�����āA�����������Ȋw�Ȃ����̎�|�𗝉����āA�S���I�Ȋ��Ȋw�����̑�w�l�b�g���[�N���\�z����悤�ɓ����Ăق����B�����悤�Ȋ��Ȋw��������������Ă��Ӗ����Ȃ��Ǝv���B���F���錤���A���S���ׂ������m�ɂ������Ȋw�����̋��_������A���̃l�b�g���[�N�őS�̂�������悤�ɂ��邱�Ƃ�����Ǝv���B
�i����A�ɂ����āA��w���s���ׂ��A���Ȋw�����̌����ۑ�Ȃǂɂ��ăV���[�Y�ŏ����Ă����ς���ł��B�j
�G��232-2003.9.22�u�����f�F�����V�� vs �ߓ�������v
�����V�������N�̏t������A�����f�Ƀ}�����O���t�B�iX�������j��p����ׂ��Ƃ����L�����y�[����W�J���Ă���B�����́A�����̋L����ڂɂ����B�����J���Ȃ̌����ǂ́A����܂Łu50�Έȏ�̏����ɂ͌��ʂ�����̂ŁA2�N��1��A���G�f�ƃ}��������悤�Ɂv�Ƃ��Ă������A�ŋ߂ɂȂ��āA�u40�Έȏ���}�������v�Ƃ����������j��ł��o���Ă���B
�T�����t
����ɑ��A�ߓ�������i�c����w��w���u�t�A�����u���҂�@����Ɠ����ȁv����j���A�u�T�����t�v9��25�����Ŕ��_���Ă���B�u�����V���w���K�����f�x�L�����y�[���Ɉًc����I�v�Ƃ����^�C�g���B
�ߓ�����́A���̘_���Ƃ��Ĉȉ��̂��Ƃ��咣���Ă���B
1)�@���{�ł́A�}�����O���t�B�����œ����S�������邱�ƂƁA���̎������܂߂������S�������邱�Ƃ̏ؖ����Ȃ��B
2)�@�ŋ߁A���ĂŃ}�����O���t�B���f�҂Ɣf�҂ŁA�����S���������S�����ς��Ȃ��Ƃ��������������i�����Z�b�g�A2000�N�j�B������đ�_�����N���Ă��āA���_���o�Ă��Ȃ��B
3)�@�����ł̖��́A
�@���m��h�Ɣے�h�̍����ƂȂ�f�[�^������Ă���
�@���Ⴆ�A�����S�����������Ă��A�����S���ɗ^����e����������
�@�����f�ɂ��s���v�i�U�z������������A10�N�Ԏ������2�l��1�l���U�z���j
4)�@�䂪���͉��Ăɔ�ׁA������늳���A���S����1/5���x�ŁA���Ăɔ�ׂ�Ƃ���Ɍ���������
5)�@��ҁA��Ë@�ւ̗��v�̂��߂ł͂Ȃ����H
��p�Ό��ʂ��v�Z���Ă݂�
�}�����O���t�B�[�̔�p�Ό��ʂ����������ςɌv�Z���Ă݂悤
�i�ڂ����f�[�^�ł͂Ȃ��B�ق�Ƃ��ɂ����Ƃ����v�Z�j
����
1) 2�N��1��A40��ȍ~�̏����̔������}�����O���t�B���f���邱�ƂŁA�����S����2����������Ɖ���
2) 1��̔�p��10,000�~/��i�l���������z�́A5,000�~�Ƃ�500�~�Ƃ�����Ă��邪�A�����ł͎��{����@�ւ̕��S���z�j
3) ������ɂ�鎀�S�́A�قƂ��40��Ȍ�ŁA�����50��Ȍ�ɏW�����Ă���B
4) 40��ȏオ�����̐l���̔������߂�i���傫�߂̉���j
5) �䂪���̓����S���́A����10���l��15�l
�v�Z
1) 10���l�̏�����Ώۂɂ���ƁA5���l��40�Έȏ�B���̔��������f����ꍇ�̔�p�́A�N��1.25���~�i1.25�~108�j�i2�N��1����F50,000�~0.5�~10,000�~0.5�j
2) �}�����O���t�B�Ō������鎀�S�҂̐��́A�N����10���l��3�l
3) 1�l�̎��S�����炷���߂ɕK�v�Ȕ�p�́A1.25���~/3��4000���~/���S
4) 1���S�̑����]����12.6�N�Ƃ���ƁA1�N�E�l�i10���l����1�l�̖����P�N�����j�̖����~�����߂�1.25�~108/3/12.6�N��330���~
�}�����O���t�B�������S����2���팸�������Ƃ��Ă��A���\�����Ȃ��I
���ʂ��Ȃ���A���̌v�Z�͑S���Ӗ����Ȃ����B
�i�ނ��A����ȂǂƔ�ׂ�ƌ����͂������A��Ñ�̒��Ŕ�ׂ�ƌ��ʂ̊��ɔ�p�������j
Harvard��w�ł̌���
�}�����O���t�B���傢�Ɍ��ʂ�����Ƃ���Ă������̕č��ł̌����ł́A�}�����O���t�B�͔�p�Ό��ʂ����ɂ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă����iTengs��j�B�ȉ���1�N��l�̖����~�����߂̔�p�i1�h����120�~�Ŋ��Z�����j
| �}�����O���t�B���f�̑Ώێ҂ƕp�x |
��p�Ό��ʁi�~/�N��l�̎����l���j |
| 1) 50�� |
97,200 |
| 2) 50-65��3�N��1�x |
324,000 |
| 3) 40-64�ɖ��N�A����ɐG�f |
2,040,000 |
| 4) 55-64�ɖ��N |
13,200,000 |
| 5) 40-49�ɖ��N�i���݂̌��f�ɉ����āj |
22,800,000 |
���̌��ʂ�����ł͋^���Ă���킯�����A���̐��l�̌X��������ƕ����邱�Ƃ�����B�N���Ŕ�p�Ό��ʂ��傫���ς�邱�ƁA40���Ώێ҂ɉ�����ƁA��p���ɒ[�ɏオ�邱�Ƃł���B�܂�A40��͂�߂����������B�܂��A55�Έȏオ�܂܂�Ă�������������B50-55�̌��f�����ʓI�炵���B
��p�Ό��ʂ̌v�Z�����悤
�����J���Ȃ����������v�Z�����Ăق����B�}�����O���t�B���s���ɂ��Ă��A�܂���50-65��Ώۂ�3�N��1�x���炢�ɂ�����ǂ����B�}�����O���t�B�����ʓI���Ƃ������ʂ��łĂ���̂��A�قƂ�ǂ�50�Έȏ��Ώۂɂ������f�ł���B40���Ώۂɂ����}�����O���t�B�́A���ʂ��Ȃ��Ƃ����������悤�Ɏv���B
�ߓ����w�E����U�z�����͂��Ȃ�傫�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B����1993�N���X���̎�p���������B����́A�G�R�[�ɂ���X���K���̋^���Ƃ������Ƃ��������A�J�������牽���Ȃ������B��ᇃ}�[�J�[���A���ŁA�G�R�[�����Ŏ�p�ƂȂ����i����a�@���O�ȁj�B
�X�������ɗǐ��̏����Ȏ�ᇂ�����A���ꂾ���E�o���čĂѕ������̂����A���̎�p���̂ɗ^�������ׂ͂��Ȃ�傫�������B���̌���A�X���������Ƃ�������͂��������Ȃ��B���������}�C�i�X�����肤��Ƃ������Ƃ��܂߂��]�����K�v�ł���B
Tengs T. O.; Adams M. E.; Pliskin J. S.; Safran D. G.; Siegel J. E.; Weinstein M. C.; Graham J. D. (1995) Five-Hundred Life-Saving Interventions and Their Cost-Effectiveness. Risk Analysis 15(3); 369-390
�G��231-2003.9.16�u�g���t�O�ƃz���}�����v
9��13���i2003�N�j�����V���[���Ƀz���}�����g�p�g���t�O���o�ׂ��ׂ����A�p�����ׂ����̋L�����������B�z���}�����́A�z�����A���f�q�h�̐��n�t�ł���B�l�b�g��̈ӌ��Ȃǂ�����ƁA�z�����A���f�q�h�͔�������������A������g���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ����ڂɂ��B����́A�ꕔ���������A�K�������g���t�O�̏ꍇ�ɂ��Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��B
����́A�z�����A���f�q�h�̔����ɂ��āA�����ڂ����q�ׁA�Ō�Ƀg���t�O���ɂ��Ă̒����̍l�����q�ׂ�B
�z�����A���f�q�h�̔�����
�o���ێ�̏ꍇ�̔����Ȃ��F�܂����ɒ��ӂ��ׂ��́A�z�����A���f�q�h�́A�z������ꍇ�ɂ͔���������Ƃ���Ă��邪�A�o���ێ�̏ꍇ�ɂ͔����́A�����Ȃ��Ƃ�����ł͔F�߂��Ȃ��Ƃ���Ă��邱�Ƃł���B����́AEPA�̃f�[�^�x�[�X�ł���IRIS�ɂ��L�q����Ă��邵�AWHO�̕��ɂ��L�q����Ă���i�������̓��������ŗz���̌��ʂ����邪�j�B
�z���̏ꍇ�A���������Ŕ������肩��`�q����������F���b�g��}�E�X�ŁA�ċz��n�튯���L�̎�ᇁi����j������A���ɕ@�o�ɂ������ᇂɂ��ėp�ʔ����W������Ƃ����������BEPA�͂���������āA�����ߎ���p���ă��j�b�g���X�N���Z�肵�A10-5�̔����X�N�ɑ��������C�Z�x�́A0.8��g/m3�ł���Ƃ��Ă���i1991�N�j�B
WHO�������A���Z�x�̎��ɁA���b�g�ƃ}�E�X�Ȃǎ��������ɕ@�̂���������Ƃ��Ă���B
�z���̏ꍇ�̐l������probable�i���肤��j�FEPA��WHO���A�l�ɔ���������Ƃ����؋��͂���قNJm���ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A�����āg���肤��h�Ƃ������f�����Ă���B
EPA�́A�ċz��n�튯���L�̎�ᇁi������o��ᇂȂǁj�̔������l�ŔF�߂���Ə����Ă���B�܂��AWHO�́A25�̉u�w�����̌��ʂ����āA�\���ȏ؋�������Ƃ͌����Ȃ����A�z�����A���f�q�h�Ə������ᇂƂ̊Ԃɗp�ʔ����W������ƍl����Ƃ��Ă���B
�܂��A��r�I���Z�x�̖\�I�ŁA�@�o�̎�ᇂƃz�����A���f�q�h�\�I�Ƃ̊Ԃɂ����ւ�������ƕ��Ă���i��������؋��͏\���ł͂Ȃ��Ə����Ă���j�B�z�����A���f�q�h�ɂ͈�`�q�������͂��邪�A�@�̕����̎�ᇔ����@�\����l���āA���̎�ᇔ����@�\�ɂ́u臒l������v�i����p�ʈȉ��ł͔��ǂ��Ȃ��j�Ƃ��Ă���B�܂�A���̂��Ƃ́AEPA�̒����ߎ��͕s�K�ƌ����Ă���̂Ɠ��`�ł���B
�z���\�I�ł͔�������ł��A�o���\�I�̏ꍇ�ɂȂ��ɂȂ�̂́A�o���œ���z�����A���f�q�h�����̕����ƌ������Ă��邩�A���ɗn���Ă��āA�C�̏�łȂ����ƁA�������A�z�����A���f�q�h�̕������������߁A�ł��N���e�B�J���ȕ@�ɉe����^���Ȃ����߂ƍl�����Ă���B
�����l�F
�z���FWHO�́A�A��ڂȂǂɑ���h����h���ړI��0.1
mg/m3�i100 ��g/m3�j���Ă��Ă���B���̒l�́A�l������ɑ��Ă��\�����X�N���������Ƃ��Ă���B
�o���F2�N�Ԃ̃��b�g�̎����ł̑̏d�����}�����G���h�|�C���g�Ƃ����ꍇ�ANOAEL�i���e���ʁj��15 mg/kg bw/���ŁA�s�m�����W����100�Ƃ��āA�����e�ێ�ʂ�150 ��g/kg bw/���ł���Ƃ��Ă���i�����́AEPA�����������AEPA�͐������܂�߂ē����e�ʂ��A200 ��g/kg bw/���Ƃ��Ă���j�B
����������l�FWHO�͂��̒l����b�ɁA���������Ɋ܂܂��z�����A���f�q�h�̊�l�Ƃ���900 ��g/L���Ă��Ă���B�䂪���̐���������l��80 ��g/L�ł���i���N�S������j�B���݂ɁA900 ��g/L�̍����́A150�~60�ikg bw�j�~0.2/�QL��900 ��g/L�ł���B
0.2�͐�������̐ێ抄���A2�͈��2L�̐����������ނƂ������肩�炫�Ă���B
���_�́A
�܂�A�o���ێ�ł͐l�ɑ��锭����Ȃ��B�z���\�I�ł͂��邩������Ȃ����A������@�̕����̎�ᇂɌ����Ă���B�@��A�ɑ���h����h��������A����͖h����B
�����Ńg���t�O�͂ǂ����ׂ����H
�@
�ȉ��́A���̒�Ăł���B
�P�D���N�ɂ��ẮA�u�z���}�����g�p����A�������c���Ȃ��v�̕\�������ė��ʂ�������B���ɁA�o���ێ�ŁA�l�̌��N�ɖ�肪����Ƃ͎v���Ȃ�����ł���B�z���}�������g��Ȃ������l���A����ɉ����g�������͕\�����悤�B
�Q�D���N�����āA���Y���͓��c�����A�͂����肵�����_���o���ׂ����Ǝv���B���̍ہA���̂��Ƃ��l���Ăق����B
�P�j�z���}�����́A���ẮA�o���ێ�Ƌz���ێ�̋�ʂ����炩�ɂ��ꂸ�A������������ƕ���A�䂪���ł͑傫�Ȗ��ɂȂ������A���́A�o���ێ�ł͐l�������ے肳��Ă���Ƃ������Ƃł���B
�Q�j�{�B�ł́A�K���E�ۍ܂��K�v�ɂȂ邾�낤�B�����A�֎~���Ă��ʖڂ��B�z���}�����̑�֕��ɂ��Ă����X�N�]�������A�ǂ̒��x���X�N���������̂��𖾂炩�ɂ��Ăق����B�����āA���炩�Ƀz���}�����̃��X�N�������̂����������A���ʂ����\���Ăق����B
�R�j�H�i��H�ׂ�l�ւ̌��N�e���͂ނ��돬�����悤�Ɏv����B���̐����ɗ^����e����A��܂��g�������ɑ���z���\�I�ɂ�郊�X�N���l������B
�ȏ�̂��Ƃ��������āA�{���Ƀz���}���������̑�֕��ɔ�ׁA�����̂��ǂ����A�͂����肵�����_���o������ǂ����B�����Ĉ����ƂȂ�A������Ǝ�点��ׂ����B�������A���ɂ͐l�ւ̌��N�e���͂���قǑ傫���Ƃ͎v���Ȃ��B���ԉe���͋C�����������������A�����h�����@�͂���������͂����B
�Ō�ɁA���R�̐H�i���ɂ͑��ʂ̃z�����A���f�q�h���܂܂�Ă��邱�Ƃ��m���Ă����Ăق����B�H�i���Ɋ܂܂��z�����A���f�q�h�̃f�[�^�́A�ȉ��̃T�C�g�Ō��邱�Ƃ��ł���Bhttp://www.maruhi-plywood.co.jp/page008.html
�Q�l����
USEPA IRIS, Formaldehyde
WHO Regional Office for Europe(2000)�AWHO air quality guidelines, http://www.who.dk/air/Activities/20020620_1, Chapter 5.8
WHO(1993), Guidelines for drinking-water quality, second edition
�lj��@2003.9.18�u���w�V���|�W�E���v
9��10���A���䎊�����Áu���w�V���|�W�E���v��������L�����p�X�ŊJ����܂����B�����ŁA�u���w�Ƃ́@��w�̊O������v�Ƃ�����ňꎞ�Ԓ��x�b���܂����B
�b�����������A����Ȃ̎����Ɍ����Ȃ��Ǝv�����̂ł����A���䂳�njR�������Ă���̂ŁA�ق�����Ĉ����܂����B�ł��A���\�̑��e������Ă��邤���ɁA�u�����āA���\�����ȋ@��ɍl���Ă����v�Ɗ�ɋ��������C�����ɂȂ�܂����B
���̘b�������e�̂܂Ƃ߂��A���䂳��́u�������z�[���y�[�W�v�i�A�N�Z�X���������Ă������j�ɍڂ��Ă��܂��B
�i�������N���b�N�j
�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�